
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
業務用に買い物をした際、経費として会社に請求するために、「領収書をもらえますか?」と、わざわざ手書きの領収書を請求したことがありませんか。会社や個人事業の経費として計上するためには、レシートではなく、わざわざ領収書をもらう必要があるのでしょうか。今回は領収書やレシートの要件について解説します。
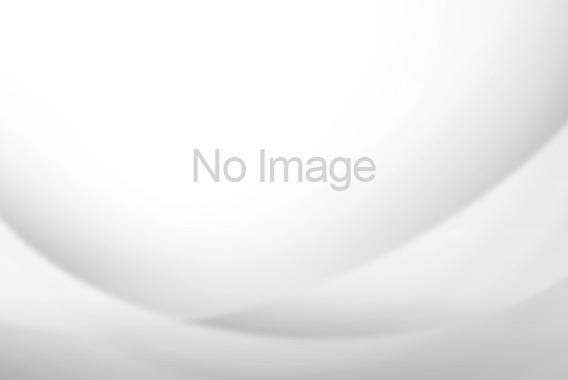 領収書とは本来、現金などについて「受け取った、受け取ってない」という紛争を防止するために、受け渡しの日付や金額、内容などを明らかにする目的で作成するものです。領収書があれば、支払いがあった事実が確かめられるので、経費を計上する根拠資料としても適しています。
領収書とは本来、現金などについて「受け取った、受け取ってない」という紛争を防止するために、受け渡しの日付や金額、内容などを明らかにする目的で作成するものです。領収書があれば、支払いがあった事実が確かめられるので、経費を計上する根拠資料としても適しています。
領収書には宛名、日付、金額、ただし書き(商品やサービスの内容)、発行者の名称や住所などが記載されるのが一般的です。また、社印や担当者印が押され、必要に応じ、収入印紙の貼付と消印がなされます。
一方、レジから出てくるレシートにも、上記のような事項は基本的に記載されています。従って、経費として処理できるかどうかという点からいえば、基本的には領収書である必要はなく、レシートで問題ありません。
レシートは商品やサービスの内容が明確に記載されているケースが多いのに対して、領収書では「お品代」など具体的な内容が分からないような記載になっているケースも少なくありません。むしろそうした領収書の方が問題です。手書きの領収書では、きちんと必要項目が記載されているか確認しましょう。
もちろん社内ルールとして、他者のレシートが流用されることを防止するためなどの理由で、領収書の入手が義務付けられている場合は、それに従うべきでしょう。
領収書には印鑑が押されているケースが多いのに対して、レシートには押されていないため不安に思う方がいるかもしれません。しかし、領収書やレシートの印鑑は必須のものではありません。また、領収書に収入印紙が貼られていない場合でも、領収書自体の効力には影響がありません。
例えば、売り上げの領収書は、印紙税法では「17号文書」と呼ばれます。17号文書では記載金額が5万円以上であれば200円の印紙が必要となります。印紙を貼っていないと法令違反となりますが、印紙を貼って消印する義務は、領収書を作成したお店にあります。受け取った側が責任を負うことはありません。
結局のところ、経費として認められるかどうかのポイントは、実際に事業に関連する支出があったかどうかです。それが証明できる根拠資料であれば種類は柔軟に捉えてよいということです。
ただし、「交際費(接待飲食費)」を計上する場合や、1人5,000円以下の飲食費を「会議費」として計上する場合には少し注意が必要です。なぜならば、これらは帳簿や書類に記載すべき事項が、それぞれ法律で決まっているからです。とはいえ、上記の領収書やレシートの基本的な記載事項にプラスして、参加者全員の氏名と所属をメモしておけば要件はクリアできますので、それだけ気を付けておけば大丈夫です。
消費税の納付義務がある課税事業者である場合にも気を付けるべき点があります。消費税の納税額を計算する際には、仕入れた商品やサービスにかかる消費税を差し引くことができます。そのためには、仕入れの根拠書類に上記の領収書の記載事項と同様の事項が記載されている必要があります。
このとき、記載者が小売業、飲食、写真、旅行業などの場合には、宛名の記載を省略できることになっています。逆にいうと、それら以外の場合では、宛名の省略が認められていないことを意味します。つまり、街でショッピングしたり、飲食したりする以外の個別的な取引では、適切に宛名が記載された請求書や領収書なりを入手して保管する必要があることに注意しましょう。
ただ、レシートが感熱紙で発行されている場合などは、時間がたつと印字が消えてしまうこともあります。コピーを取って一緒に保存しておくなど、備えが必要でしょう。
レシートや領収書は紙のままではなく、スキャニングをして電子データとして保存しておくことも可能です。スキャナ保存制度(電子帳簿保存法)に従った処理が必要ですが、平成28年度改正で、デジタルカメラやスマホで撮影した画像での保存も可能となり、より導入しやすい制度となっています。スキャナ保存制度の詳細については「スマホ撮影もOK!経理のペーパーレス化が現実的に」の記事もご参照ください。
以上のように、基本的にはレシートでも法的には問題ないので、特に理由もなく、少額の消耗品購入などでも領収書の入手を社内ルールで義務付けている場合は、そろそろ見直すべきではないでしょうか。それと同時に、スマホの利用の促進などで、より手間がかからず確実な保存方法を工夫することで、経理事務の合理化も図りましょう。
執筆=北川 ワタル(studio woofoo)
公認会計士/税理士。2001年、公認会計士第二次試験に合格後、大手監査法人、中堅監査法人にて金融商品取引法監査、会社法監査に従事。上場企業の監査の他、リファーラル業務、IFRSアドバイザリー、IPO(株式公開)支援、学校法人監査、デューデリジェンス、金融機関監査等を経験。2012年、株式会社ダーチャコンセプトを設立し独立。2013年、経営革新等支援機関認定、税理士登録。スタートアップ企業の支援から連結納税・国際税務まで財務・会計・税務を主軸とした幅広いアドバイザリーサービスを提供。
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ