
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
中小企業の事業承継問題が注目されています。経営者の平均年齢が上昇の一途をたどる一方、後継者が不在で休廃業に追い込まれる中小企業が増える可能性が指摘されています。
こうした問題に加え、株式の贈与・相続に関する納税が難しいということも承継のハードルを高くしている要因になっています。その改善に向けて、政府は事業承継円滑化のための税制対策に本腰を入れ始めました。それが2018年度税制改正に盛り込まれた「事業承継税制の特例」です。
この特例は今後10年間に期間を区切ってはいますが、従来の事業承継税制の適用要件を大幅に緩和する内容です。これにより、事業承継で障害となっていた納税面の問題が解消されるケースは増えるでしょう。
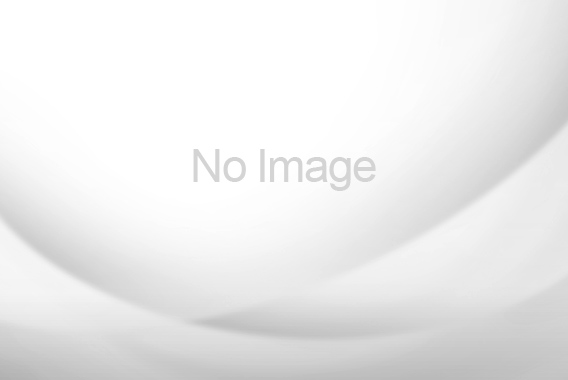 中小企業における事業承継は、オーナー経営者が保有する自社株式を後継者に相続させることに他なりません。経営権の後ろ盾でもある自社株式は、経営実態と比べて評価額が高くなることも多く、多額の贈与税や相続税が課される可能性があり、円滑な事業承継の妨げになるという問題がありました。
中小企業における事業承継は、オーナー経営者が保有する自社株式を後継者に相続させることに他なりません。経営権の後ろ盾でもある自社株式は、経営実態と比べて評価額が高くなることも多く、多額の贈与税や相続税が課される可能性があり、円滑な事業承継の妨げになるという問題がありました。
そこで、一定の要件を満たした自社株の贈与に対しては、贈与税や相続税を猶予することで、次世代経営者への事業の引き継ぎを支援する制度が2009年に創設されました。それが事業承継税制です。中小企業を対象とした事業承継税制は創設以降、制度の活用を促進するために適用要件の見直しが適宜行われてきました。
そうした過去の見直しと比べ、今回の2018年度税制改正は大幅な要件緩和が盛り込まれました。その点で今回の法改正は、事業承継を考える経営者にとっては、大きなトピックスであるといえます。その中でも主要な改正点を3つ紹介します。
1つ目は、対象株式数と猶予割合の拡大です。従来の事業承継税制では、対象となる株式数が議決権株式総数の3分の2までという制限がありました。今回の改正では、まず株式数の制限がなくなり、すべての議決権株式が対象とされます。また、贈与税に加えて相続税においても、猶予される割合が80%から100%に拡大されました。
改正前は議決権株式総数の3分の2に、猶予される80%を掛けた約53%の議決権株式のみが納税猶予の対象でした。つまり全株式を1人で相続した場合、約47%に課せられる税金は猶予なしのため期限内に納めなくてはなりませんでした。改正後は全株式で100%となりますので、実質、贈与税や相続税の負担がなくなったことになります。
2つ目は、対象者とその人数の拡大です。従来の制度では、1人の先代経営者から、1人の後継者に対する株式の贈与や相続分のみが、納税猶予の対象とされてきました。配偶者や親族、第三者といった先代経営者以外の株主からの贈与や相続は対象外だったのです。
今回の改正では、先代株主の側に関して経営者以外の株主も対象とし、人数も複数人が可能となりました。また後継者の側も、代表権を有しているなら最大3人までに拡大されました。ただし複数人が後継者となる場合は、代表権を有していることに加え議決権割合の10%以上を有している、議決権保有割合で上位3位までに入っている同族関係者に限るという条件があります。
先代株主側と後継者側を共に複数としたことは、中小企業に多い同族経営で相続が発生した場合、後継者となった子ども間で、納税猶予される人とされない人に分かれるという不均衡を是正するためともいえるでしょう。例えば、従来の事業承継税制に見られるような親から第一子への相続税のみが納税猶予され、第二子以降への相続は対象外となる。あるいは、先代株主の配偶者や親戚からの相続には課税されるといった問題の解消につながると考えられます。
3つ目は、雇用要件の弾力化です。従来の制度では、事業承継後5年間の平均で、雇用(従業員数)の8割を維持できなかった場合、納税猶予されていた贈与税や相続税を全額納付しなければなりませんでした。しかし、今回の改正では、雇用の8割を維持できなかった場合でも、すぐに納税猶予が打ち切られることはなくなりました。一定の報告義務などはあるものの、実質的には8割要件が撤廃されたといえるでしょう。
事業承継税制が2009年度に創設された際は適用要件が厳しく、納税が猶予される範囲も限られていたため、活用した事例がそれほど多くありませんでした。2015年の改正で要件が緩和されましたが、事例の増加が鈍かったため、今回、大幅な緩和に踏み切ったと考えられます。株式の贈与税・相続税を支払う現金の工面が難しいという理由で事業承継に悩んでいた経営者にとっては、明るいニュースです。
改正された事業承継税制の適用を受けるには、2018年4月1日から5年間のうちに、都道府県庁に対して「特例承継計画」を提出した上で、2018年1月1日から10年間のうちに、贈与あるいは相続により後継者が株式を取得することが要件となります。
生前贈与などによって今後10年以内の事業承継を検討している場合は、前述の特例承継計画を5年という期限内に提出しておくことを忘れないようにしましょう。
前述した3つの適用要件の緩和に加え、後継者が将来的に事業を売却あるいは廃業した場合に、一定の要件を満たせば納税額を軽減する措置などの新たな減免制度もあります。今回の事業承継税制改革は、さまざまな問題を抱える中小企業の事業承継を税制面で支援して、経営者交代による企業存続を後押しする制度です。事業承継を視野に入れている企業はぜひとも活用を検討してください。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2018年5月15日)のものです
執筆=北川 ワタル(studio woofoo)
公認会計士/税理士。2001年、公認会計士第二次試験に合格後、大手監査法人、中堅監査法人にて金融商品取引法監査、会社法監査に従事。上場企業の監査の他、リファーラル業務、IFRSアドバイザリー、IPO(株式公開)支援、学校法人監査、デューデリジェンス、金融機関監査等を経験。2012年、株式会社ダーチャコンセプトを設立し独立。2013年、経営革新等支援機関認定、税理士登録。スタートアップ企業の支援から連結納税・国際税務まで財務・会計・税務を主軸とした幅広いアドバイザリーサービスを提供。
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ