
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
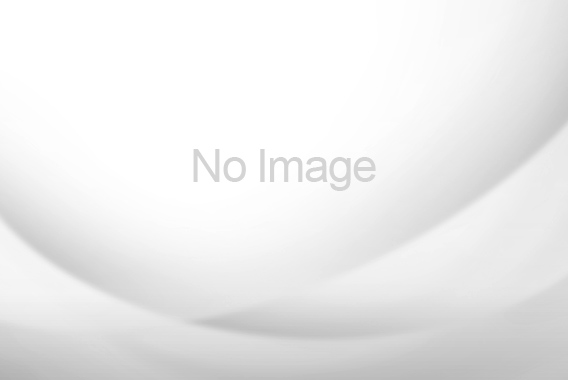
周囲の企業に税務調査が入り、修正申告や多額の追徴課税の支払いを行ったなどという話を聞いて、自分の会社は大丈夫かと心配した経験のある経営者は少なくないと思います。
実際、2018事務年度における法人税の税務調査は、調査必要度が高い法人9万9000件(前年対比101.3%)について実地調査が実施されています。このうち、法人税法違反があった法人は7万4000件(同101.8%)、申告漏れ所得金額は1兆3813億円(同138.2%)、追徴税額は1943億円(同99.8%)となっています。
つまり税務調査があった場合、約75%(4社に3社)の割合で違法が指摘され、追徴税額が発生する可能性が高くなっています。税務調査で指摘された場合、加算税および延滞税が追徴課税されるので、いかに税務調査で指摘されないかが重要です。税務調査がいつ入ってもいいように、指摘されやすい事項と注意点について確認していきましょう。
年末年始に社員旅行を計画している経営者も多いでしょう。社員旅行に関しても、場合によって修正申告が必要となるケースがありますので注意が必要です。社員旅行の費用全額が経費として認められるためには、旅行期間が4泊5日以内(海外旅行の場合、外国での滞在日数が4泊5日以内)であること、参加する社員数が全体の50%以上であることが要件です。
ただし、自己都合での社員旅行不参加者がいる場合、「平等に報いたから」などと考えて、旅行代などを支給すると給与として課税されてしまいます。この場合、さらに参加者に対しても給与扱いでの課税となることを覚えておいてください。
また、役員だけの旅行や、実質的に私的な旅行と認められる役員旅行は、役員報酬として給与課税されます。さらに、法人税の損金不算入扱いとなり、所得税と法人税双方の追徴課税がなされますので、代表取締役も含め、公私混同は禁物です。
企業側で外注費として処理していたものが税務調査で指摘を受け、給与課税されることもよくあるケースです。
外注費か給与かの判断について、「外注費」は請負契約、またはこれに準ずる契約が該当します。しかし、個人が雇用契約またはこれに準ずる契約を結び、作業時間や手順は発注元が決める権限があり、その上で業務をしている場合は、外注費ではなく「給与」に該当します。また、その区分が明確でないときの給与か外注費かの判断については、次の事項から総合的に判定されます。
<外注費の条件>
(1) 請負先の作業者が業務をできない場合、請負先による他の作業者の手配を認められているか。
(2) 請負契約の場合、作業時間や具体的方法については、請負先が自由に決められること。
(3) 業務が未完了なら代金の支払いは不要であること。
(4) 業務に必要な材料や仕事用具を支給していないこと。
(参考 国税庁:個人事業者と給与所得者の区分)
外注費として処理する場合、所得税の源泉徴収は不要です(ただし、スポーツ選手、芸能人、弁護士ほかの報酬、原稿料、講演料などで、支払いを受ける者が個人なら、源泉徴収が必要な場合もあります)。
外注先へは消費税分を加算して支払い、消費税から仕入税額控除を適用することができます。給与として処理した場合、消費税は仕入税額控除に当たらず、さらに源泉徴収と年末調整を行うため、事務負担が増えます。さらに外注費で処理したほうが税金のメリットが大きく、企業側はつい外注費として処理してしまいがちです。しかし、安易に外注費として処理すると、税務調査で指摘され痛い目を見てしまいます。
通常、賞与はその事業年度内に支給したものが損金扱いとなりますが、黒字企業で決算賞与を考えている場合、業績を期末ぎりぎりまで見極めてから、未払い計上して損金算入することができます。ただし、決算賞与は次の要件を満たさないと、損金不算入となってしまうので注意が必要です。
(A) 期末前に全ての従業員に対して、賞与の支給額を記載した書面等で通知をしていること。
(B) (A)を通知した全ての従業員に対し、通知日の事業年度終了日翌日から1カ月以内に賞与を支払っていること。
(C) (A)の通知をした期日の事業年度において損金経理をしていること。ただし、自社規定に「支給日に在職する者のみ賞与を支給する」などの条項がある場合は、決算賞与未払いの損金算入はできません。
特に期末前に通知をしていないと修正申告が必要となる可能性が高くなりますので、必ず期末前に通知を行いましょう。
このほか税務調査で指摘されやすい事項の1つに、売り上げ計上時期のずれがあります。会計処理は発生時で処理するため、例えば3月締め決算の法人で3月中に売り上げが発生し、入金は次期となる4月以降の場合であっても、その取引は3月分の売り上げとして計上します。
商品を発送基準で売り上げ計上している場合には、3月31日に商品発送したものも3月分として計上しなければなりません。忙しい中、決算業務を行っていると、期末の売り上げ計上をうっかり漏らすこともありますので、特に売り上げ計上時期については注意しましょう。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2019年11月29日)のものです
執筆=並木 一真
税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート。会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・節税対策・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等を中心に幅広く税理士業務に取り組んでいる。 https://namiki-kaikei.tkcnf.com/
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ