
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
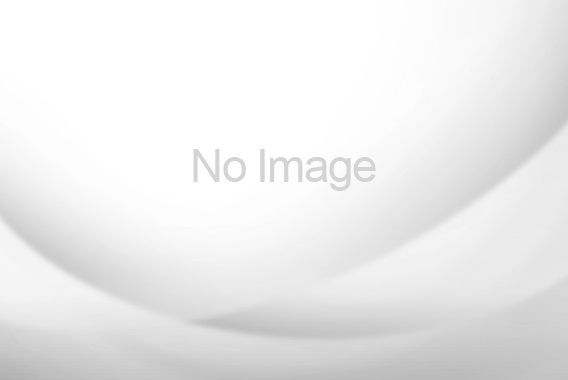 2019年10月に施行される予定である消費税の新制度に合わせて、複数税率に対応した仕入税額控除ができるように請求書などの記載事項が変更になります。変更は2段階で行われる予定です。前回の記事では1段階目である区分記載請求書等保存方式について紹介しました。今回は2段階目となる、2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)について触れていきます。
2019年10月に施行される予定である消費税の新制度に合わせて、複数税率に対応した仕入税額控除ができるように請求書などの記載事項が変更になります。変更は2段階で行われる予定です。前回の記事では1段階目である区分記載請求書等保存方式について紹介しました。今回は2段階目となる、2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)について触れていきます。
適格請求書等保存方式に移行した場合は経理処理だけでなく、取引にもさまざまな影響を及ぼすと予想されています。本記事では、適格請求書等保存方式の実務に適応する準備とともに、取引に及ぼす影響についても解説します。
前回の記事で紹介した区分記載請求書等保存方式では、消費税率ごとに記載を区分するため、現行の請求書等保存方式より記載項目が増えます。しかし、区分記載に不備のある請求書などを受領しても、取引事実に基づいて受領側で追記することで仕入税額控除が認められることになっています。また、取引の全てを区分して請求書や帳簿に記載することが困難な中小事業者などに対しては、「税額計算の特例」という計算式で仕入税額控除が行えるといった経過措置も設けられています。
不備のある請求書への追記や経過措置があるのは、軽減税率導入による経理実務の混乱を低減させるという配慮からです。事業者には軽減税率へスムーズに移行してもらうことで、より変化の大きい適格請求書等保存方式への移行時に混乱を低減させようというわけです。
その後、適格請求書等保存方式を導入すると、請求書などへの記載事項に「適格請求書発行事業者の登録番号」と「税率区分ごとの消費税額等」が追加されます。区分記載請求書では「税率区分ごとの合計請求額(税込み)」とされている部分が、適格請求書等保存方式では「税率区分ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)」と「税率区分ごとの消費税額等」に分ける必要が生じます。つまり税率ごとの合計請求額(対価の額)に加えて、それぞれの消費税額も記載しなくてはなりません。
そして、適格請求書では、記載事項に誤りがあった場合、交付を受けた事業者による追記は認められません。その点が区分記載請求書等保存方式と大きく異なります。
さらに適格請求書等保存方式では、現行方式と区分記載請求等保存方式で請求書の発行が免除されていた3万円未満の取引でも、一部を除いて発行義務は免除されません。免除の対象となる取引は、代表的なものとして公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送(3万円未満)、自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡など(3万円未満)、郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)などに限定されます。
もう1つの追加記載事項である「適格請求書発行事業者の登録番号」は、課税事業者が事前に税務署へ「適格請求書発行事業者」の申請書を提出しないと取得できません。税務署の審査に通過すれば、インターネットや税務署からの通知書をもって登録番号が通知されます。
2023年10月1日までに登録番号を取得していないと、制度導入日から適格請求書が発行できません。制度導入日までに登録を済ませるためには、申請書類を2021年10月1日から2023年3月31日までに提出する必要があると、国税庁が告知しています。ただし困難な事情がある場合には、2023年9月30日までの提出も可能ですが、制度導入日までに番号登録を確実に取得するなら、3月31日までに提出を済ませたほうが無難でしょう。
提出が遅れ、登録番号の取得が制度導入日よりも後になった場合、制度導入日から取得日までの間は適格請求書を発行できません。相手方に仕入税額控除の対象となる請求書が発行できず、迷惑をかける可能性もでてきます。
このような制度ですから、請求書を受ける側が課税事業者であれば、仕入れの取引相手が3月31日までに申請書提出済みであるということが、適格請求書等保存方式導入前から重視するポイントになるかもしれません。
区分記載請求書等保存方式では、免税事業者からの課税仕入れでも区分記載による請求書の発行と帳簿の保存で、仕入税額控除の要件を満たします。しかし適格請求書発行事業者の登録番号制度が導入されると、免税事業者は要件を満たした請求書が発行できなくなります。登録番号を申請できるのは、課税事業者のみだからです。そのため、別の経過措置が設けられる予定です。
具体的には、適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れにおける一定の金額を仕入れ税額と見なして控除するという「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」になります。一定の金額が指す具体的な割合としては、2023年10月1日からは80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%です。この場合には、区分記載請求書等保存方式の要件を満たす帳簿および請求書などの保存が必要となるほか、経過措置の適用を受けたものである旨を帳簿に記載する必要があります。2029年10月1日以後は経過措置の終了に伴い、適格請求書発行事業者以外の事業者からの仕入れは課税取引になりません。
今回紹介した適格請求書等には交付義務があり、発行事業者は取引先から要求があれば交付する必要があります。ところが、免税事業者は適格請求書を発行できません。もし登録番号を偽るなどして適格請求書等を不正交付した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金といった罰則があります。
そして適格請求書の導入によって、取引における免税事業者の社会的な立ち位置がこれまでと大きく変わるというのが、1つの懸念事項でもあります。例えば、仕入税額控除の適用ができないという理由から課税事業者が免税事業者との取引をやめたり、消費税相当額を支払わなかったりするかもしれません。
ほかにも免税事業者が適格請求書発行事業者となるために、「消費税課税事業者選択届出」を行い、やむを得ず課税事業者を選択するというケースも急増するでしょう。
これらの動きは「免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置」が終了する2029年10月1日以降に、顕著に表れると予想されます。本連載第29回から4回でわたって軽減税率に関して説明してきたことを念頭において、消費税新制度への準備を早めに進めてください。もし遅れれば、経理事務に関してだけでなく企業活動そのものに大きく影響してくるかもしれません。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2018年11月1日)のものです
執筆=伯母 敏子
プロフィール:税理士。大学卒業後、大手リース会社の営業職として中小企業経営者に向けた融資、リース契約、保険の販売等さまざまな金融商品の取り扱いを経験。その後、個人税理士事務所へ転職。平成27年に税理士試験合格。平成28年4月に税理士登録、平成29年11月に伯母敏子税理士事務所として独立開業。現在は新宿区神楽坂にて中小企業の経営、事業承継、法人成り、クラウド会計、経理事務改善の提案等のサポートを通じて中小企業経営者向けサービスを提供している。 https://uba-tax.com/
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ