
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
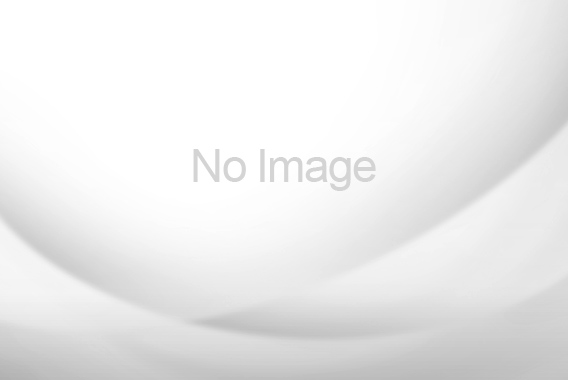
早いもので、2022年も3月となりました。この時期は、会社の期末、年度末と重なるため、転職や退職も多いとされています。以前のように「定年まで勤めあげるのが美徳」という風潮が薄れてきていることも、転職や退職が多くなっている一因と考えられます。
この退職に伴い発生するのが退職金です。勤続何年目から退職金の支給対象とするかは会社によって異なりますが、自己都合退職では勤続3年以上4年未満から退職一時金を支給する会社が約47.4%(東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)」)とされています。
ところで、令和3年度税制改正において、2022年1月1日以降に支払いを受ける「短期退職手当等」について、退職金課税が改正されていることをご存じですか。
勤続年数5年以下の従業員に多額の退職金を支払う会社は少ないと思いますが、退職所得の優遇税制である、2分の1課税適用誤りによる源泉課税漏れ防止の観点から、改正内容や背景などについて解説させていただきます。
その年中に支払いを受ける退職手当等の全てが一般退職手当等の場合には、下表のとおり、その退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額が退職所得金額とされます。
退職所得金額=(一般退職手当等の収入金額―退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は、勤続年数に応じて次のとおりとなります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
| 20年以下の場合 | 勤続年数×40万円 |
| 20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数―20年) |
(注)算出した退職控除額が80万円に満たない場合には、80万円となります
2022年1月1日以降、短期勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」とされ、その退職所得については、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下か、300万円超かで2分の1課税の適用の有無が異なることとされました。
(注)
・短期退職手当等とは、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいいます)に対応する退職手当等として支払いを受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます
・特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数(役員等として勤務した期間により計算した年数をいいます)が5年以下である人が支払いを受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。なお、この特定役員退職手当等については、300万円超の短期退職手当等と同様、2分の1課税の適用がありません。
退職金制度は終身雇用を前提として、「定年まで働き続けてほしい」との経営者側の考えから普及した制度とされていますが、退職所得は、永年の勤務に対する表彰の意味合いを持つ退職金であることや、退職後の生活資金の原資でもあるため、受け取る人の担税力を考慮し、他の所得に比べ税負担が軽減されているといった特色があります。
しながら、近年、この税負担が少なくなる仕組みを利用し、短期間の勤務についての給与に代えて退職金を受け取り、租税回避する事例が発生しています。
そこで、法人の役員等だけでなく、従業員についても勤続年数5年以下の短期の退職金については、2分の1課税の適用を除外することとしたものです。ただし、雇用などの流動化に配慮し、退職所得控除後の金額のうち300万円までは、改正前と同様に2分の1課税が適用されます。
その年中に支払いを受ける退職手当等の全てが短期退職手当等の場合には、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下か、300万円超かで下表のとおり、2分の1課税の適用の有無が異なります。つまり、退職所得控除後の残額が300万円超となる退職金が支払われる場合には、その300万円を超える部分については2分の1課税の適用がありませんので、注意が必要となります。
① 短期退職手当等の収入金額―退職所得控除額≦300万円の場合 |
② 短期退職手当等の収入金額―退職所得控除額>300万円の場合 (注)1 300万円以下の部分の退職所得金額 |
(注) その年中に支払いを受ける退職手当等が、一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち2以上の退職手当の支払いがある場合の退職所得金額の計算方法については、「源泉徴収のあらまし」(国税庁)などを参照願います。
執筆=寺澤則夫
税理士。(一社)租税調査研究会主任研究員。
国税職員時代は東京国税局法人課税課で源泉所得税畑を歩み、源泉所得税審理係長・監理係長・課長補佐などを歴任。税務大学校教授(法人税)、黒石税務署長(青森県)、東京国税局調査第四部統括国税調査官、佐原税務署長、浅草税務署長などを歴任し、2021年7月退職。同年10月より(一社)租税調査研究会主任研究員。現在、税理士会をはじめとした税理士向け研修講師など多数手がける。
監修=宮口貴志
株式会社ZEIKENメディアプラス代表取締役、TAXジャーナリスト、会計事務所ウオッチャーとして活動。一般社団法人租税調査研究会常務理事。元税金専門紙・税理士業界紙の編集長。
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ