
脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」(第98回)
"トンネル"を抜けてデータを安全にやり取り
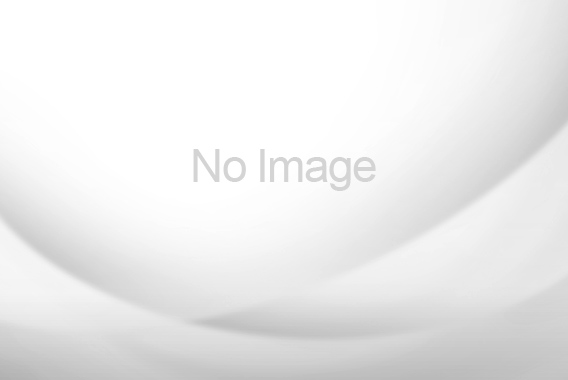
経済産業省の外局・中小企業庁と内閣府の外局・金融庁が事務局となり、中小企業関係者、学識経験者などが委員となって設置された検討会によって2012年に公表された「中小会計要領」(※1)は、中小企業の実情を考慮して作成されました。中小企業がこの会計要領を活用することで、決算書の信頼性向上が期待できる内容となっています。
※1 中小会計要領
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm
中小企業経営者が自社を存続・発展させていくには、正確な財務情報に基づき、自社の経営状況を把握して経営改善などを図り、融資を受ける金融機関などの利害関係者に情報提供していくことが極めて重要です。今回は、その要となる中小会計要領について解説します。
中小会計要領に従った決算書を作成していない中小企業経営者もいることでしょう。そこで決算書が中小会計要領に従って作成されているかどうかを確認するツールとして、日本税理士会連合会による『「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト』(※2)があります。自社の決算書がどの程度、中小会計要領に従っているのかを確認できるので、目を通すとよいでしょう。
※2 チェックリスト(PDF)
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/business/tyushoushien/indicator/youryouchecklist150325-2.pdf
中小会計要領は、中小企業の実態への配慮と、税務や事務負担軽減を図る観点から、実務で必要と考えられる項目に絞って、簡潔な会計処理のルールを示しています。主な会計処理の項目については次の通りです。
1.収益、費用
(1)実現主義
原則として、製品、商品の販売またはサービスの提供を行い、かつ、これに対する現金および預金、売掛金、受取手形などを取得したときに計上
(2)発生主義
原則として、費用の発生原因となる取引が発生したとき、またはサービスの提供を受けたときに計上
上述のように、収益は実現主義、費用は発生主義で処理し、収益とこれに関連する費用は、両者を対応させて期間損益を計算します。また、収益および費用は、原則として総額で計上し、収益の項目と費用の項目を直接に相殺してはならないとされています。
2.資産、負債
金銭債権、有価証券および固定資産などの資産は、原則として取得価額で計上し、流動負債・固定負債などの負債は債務額で貸借対照表に計上します。
3.貸倒引当金
法人税法上の法定繰入率や過去の貸倒実績率によって、貸倒引当金を見積もる方法を採ることもできます。
4.有価証券
有価証券は、原則として取得価額で計上しますが、売買目的の有価証券を保有する場合は、時価で計上します。また、評価方法は、総平均法、移動平均法(※3)などにより評価します。
5.棚卸資産
商品、製品、半製品、原材料などの棚卸資産は、原則として取得原価で計上します。評価方法は、先入先出法、最終仕入原価法、総平均法や移動平均法などがありますが、何も届け出をしていなければ、最終仕入原価法にて評価することとなります。
※3 有価証券や棚卸資産の評価法
(1)先入先出法
先に取得したものから順番に払い出されると仮定して、棚卸資産の取得原価を払い出し原価と期末原価に配分する
(2)最終仕入原価法
棚卸資産を期末から最も近い時期に取得した1単位ごとの取得価額をもって評価する
(3)総平均法
一定期間ごと、期首棚卸高+期中受入高をこれらの総数で割って単価を求める方法
(4)移動平均法
商品の受け入れ時点における平均単価をその都度算出して、その単価を払い出し単価(売上原価)として、期末における評価額を計算する
詳しい会計処理については『「中小会計要領」の手引き』(※4)の活用や、自社の担当税理士など専門家に相談することをお勧めします。
※4 中小会計要領の手引き(PDF)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/pamphlet/2012/youryou/download/0528KY-pamph.pdf
中小会計要領を導入して得られる効果としては、最初に述べたように決算書の信頼性向上が挙げられます。その結果、財務状況をより正確に把握できるようになるため、経営改善や融資、取引先拡大につながります。
融資の拡大の例としては中小会計要領に従った会計処理を適用中、または適用を予定している場合、事業計画書(当面6カ月程度の資金繰り予定表と部門別収支状況表を含む)を作成すると、日本政策金融公庫の融資制度「中小企業経営力強化資金」に申し込めます。
申し込みには他にもいくつか条件がありますが、新しい商品またはサービスを提供するなど、新市場創出や開拓(新規開業を含む)事業を行う中小企業が借り入れる際には利率を下げる仕組みもあります。この他にも上述の『「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリストを利用した金融商品を取扱う金融機関』(※5)もありますので、活用を検討してみてもよいでしょう。
※5 金融機関の一覧
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/sien/kinyukikan.htm
中小企業経営者にとっては、自社の会計を正確に知ることが大事です。さらに新たな事業展開や資金調達も期待できる、中小会計要領をぜひ確認してください。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2020年5月26日)のものです
【関連記事・参考資料】
中小企業庁:「中小会計要領について」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/about/index.htm
中小企業庁:「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリストを利用した金融商品を取扱う金融機関
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/sien/kinyukikan.htm
日本税理士会連合会:「中小企業会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/business/tyushoushien/indicator/youryouchecklist150325-2.pdf
日本政策金融公庫「中小企業経営力強化資金」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64.html
中小企業庁:中小会計要領ができました!!
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/pamphlet/2012/kihon/download/0420KaikeiYouryou.pdf
執筆=並木 一真
税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート。会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・節税対策・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等を中心に幅広く税理士業務に取り組んでいる。 https://namiki-kaikei.tkcnf.com/
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ