
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
企業の信用調査などを手掛ける東京商工リサーチによると、2019年、企業倒産と休廃業・解散件数の合計は5万1731件でした。国内全企業約358万9000社の1.4%に当たります。そのうち休廃業企業に絞って、代表者の年齢を見ると4割は70代。60代以上というくくりでは8割を超えます。
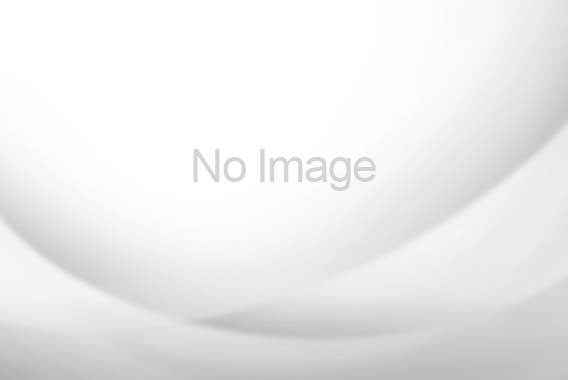
中小企業庁の第1回「事業引継ぎガイドライン」改訂検討会で配布された資料では2025年、中小企業経営者で70歳(平均引退年齢)を超える人は約245万人になると予測されていますが、約半数の127万人(国内全企業の1/3)は後継者が未定です。経済産業省・中小企業庁の試算では、このままだと2025年ごろ、直近10年間の累計で約650万人の雇用とGDP約22兆円が失われ、日本経済の損失は甚大になるようです。
こうした事態を招かないためには、中小企業の事業承継の円滑化が日本経済の大きな課題です。事業承継の時期を迎えている中小企業経営者にとっては大きな決断が必要です。中小企業の事業承継といえば、これまで、親族内で検討するケースが主流でした。親族内に適当な人材がいない場合、社員の中から後継者を見つける場合もありました。しかし、それでも後継者が見つからない企業の事業承継のために、経済産業省の外局・中小企業庁が取り組んでいるのが、第三者承継支援総合パッケージです。
第三者承継支援総合パッケージとは、親族以外の“第三者”への事業承継をスムーズに行うためのさまざまな支援策をまとめたものです。第三者への事業承継は、見方を変えれば中小企業に対するM&A(合併・買収の対象は会社組織自体だけでなく、企業内事業の場合も含む)ということになります。
同パッケージは10年間に集中実施され、黒字廃業の可能性がある60万件の第三者承継の実現をめざし、技術・雇用など中小企業の経営資源を次世代の意欲ある経営者に承継・集約させていく構想です。
中小企業庁と民間委員による検討会を重ねながら事業引継ぎガイドラインを改訂し、経営者が適正な仲介業者・手数料水準を見極めるための指針を整備、第三者承継を経営者の身近な選択肢になるように手直しします。サポートする事業引継ぎ支援センター(中小機構)では事業承継の無料相談体制が強化され、事業引継ぎポータルサイト、事業承継支援の取り組みや事例を確認できます。2014年から始まった後継者人材バンク(今後全国の同センターに設置予定)という後継者不在の小規模事業者と起業家をマッチングするためのデータバンクもあります。
同パッケージには、政府系金融機関融資の無保証化拡大と新たな信用保証制度の創設が盛り込まれています。また、2014年2月より運用されている事業承継での「経営者保証ガイドライン」特則策定・施行が2020年4月より開始され、個人補償の二重取りを原則禁止します。
これは、経営者保証(企業が金融機関から借り入れする際に経営者個人が保証人となること)が事業承継の足かせとなり、後継未定経営者の多くが経営者保証を理由に事業承継を断られている現状に対応するためです。経営者保証解除に向け、中小企業の支援(専門家による経理の透明性確保や財務内容の改善策など)や、金融機関の経営者保証なし融資実績(KPI)公表なども行われます。
また、政府系機関や民間などが出資した事業承継ファンドで、希望する中小企業に投資を行い、企業価値を向上化させた上で承継させるスキームづくりも行われます。引継ぎ相手には、国の政策実施機関・中小企業投資育成会社を通じた出資によって資金調達を支援し、資金を得た後継経営者(従業員や取引先などが出資する場合も)がSPC(特別会社)設立後、先代経営者の所有株式をSPCにより買い取り(資金不足なら銀行融資で調達)、円滑に承継する策などが講じられます。
ほかには「事業引継ぎ支援データベース」を民間事業者に開放したり、スマートフォンアプリを活用したマッチングを可能にしたりするなど、事業承継をスムーズに実現する仕組みを提供します。
事業承継では、新社長就任に向けた後継者教育、承継後の経営戦略なども大きな課題となっています。それについても関連分野の専門家を派遣し対応を強化します。また、第三者承継に伴い不動産の権利移転が生じる場合には、登録免許税・不動産取得税を軽減(2021年度末まで延長)、許認可承継がある場合の特例も措置して、承継後の負担が軽減されるように対処します。
新たな事業や取り組みに挑戦する企業を後押しする事業承継補助金制度(最大1200万円)もあり、今後は、ベンチャー型事業承継枠などの新設と事業譲渡者の廃業費用にも補助対象が広がる予定です。
現在、後継者が決まらないまま、不安を抱えて事業を続けている経営者は少なくないかと思います。今後は「第三者承継支援総合パッケージ」も含めて、国のサポートがさらに充実していく見込みです。まずは、前述の事業引継ぎ支援センターの無料相談を活用して廃業以外の選択肢を探ってはいかがでしょうか。
※掲載している情報は、記事執筆時点(2020年2月24日)のものです
【関連記事・参考資料】
中小企業庁「事業承継・創業政策について」
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kihonmondai/2019/download/190205kihonmondai02.pdf
中小企業庁「第三者承継支援総合パッケージ」
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191220012/20191220012-1.pdf
執筆=並木 一真
税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート。会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・節税対策・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等を中心に幅広く税理士業務に取り組んでいる。 https://namiki-kaikei.tkcnf.com/
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ