
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
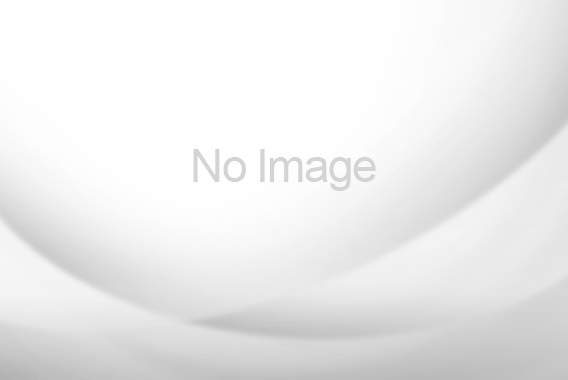
2021年4月1日より、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主に対し、定年を70歳まで引き上げるなどの措置(高年齢者就業確保措置。以下、就業確保措置といいます)を講じることを努力義務とする改正高年齢者雇用安定法(以下、高年法といいます)が施行されています。
同改正は、少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、労働者の70歳までの就業機会を確保しようとするものです。
同改正の下、今後、企業による高年齢者の雇用が進むと想定されますが、就業確保措置の実施に当たっては、事業主と労働者(高年齢者)との間で、無用なトラブルが生じないよう留意する必要があります。
そこで、本稿では、高年法改正の流れについて概観した上で、就業確保措置を講じるに当たって、事業主が留意すべき事項について見ていきます。
高年法は、2004年の改正により、事業主が雇用する労働者の定年を定める場合には、60歳を下回ることはできないとされました(8条)。また、労働者の65歳までの安定した雇用を確保するために、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、①定年の引き上げ、②継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入、③定年制の廃止のいずれかの措置を講じなければならないとされました(9条)。
ただし、このときの改正では、②の継続雇用制度については、定年後の継続雇用者を事業場の労使協定の定める基準によって選別できるものとされました(旧9条2項)。つまり、事業者は必ずしも希望者全員について継続雇用を義務付けられているわけではありませんでした。
ところが、その後、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ段階的に引き上げられることに伴い、高年齢労働者の生計維持のため、②の継続雇用制度について、事業主に希望者全員を継続雇用することを義務付ける必要性が生じました。
そのため、2012年の改正により旧9条2項は削除され、事業主は60歳未満の定年制を設けることはできなくなりました(8条)。また、労働者の65歳までの雇用を確保するために、①定年の引き上げ、②希望者全員に対する継続雇用制度の導入、③定年制の廃止のいずれかの措置を講じなければならない(9条)とされました。
このようにして2012年改正以降、事業主は希望する労働者全員に対して、65歳までの雇用を確保する法的義務を負うことになりました。
そして、2021年の改正では、従来の労働者に対する65歳までの雇用確保義務を前提として、さらに、雇用する労働者に70歳までの就業確保措置を講じることが事業主の努力義務として定められました(努力義務とは、法的拘束力のない努力目標という意味です)。
改正法の定める就業確保措置は、次の5つです(10条の2)。
① 70歳までの定年引き上げ
② 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
③ 定年制の廃止
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下a又はbの事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
これらは、1つだけではなく、複数の措置の組み合わせも可能です。その場合、対象者にいずれの措置を適用するかは、本人の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定することが望ましいとされます。
以上を踏まえ、事業主が就業確保措置を講じるに当たり、留意すべき事項について見ていきます。
1.対象者基準について
就業確保措置を講じることはあくまでも努力義務ですので、事業主がこれを導入する際に、対象者を限定する基準を設けることは可能です(ただし、①と③については性質上対象者を限定することは不可)。平たく言えば、事業主は、雇用を継続する労働者について一定の基準を設けて選別することができます。
もっとも、対象者基準を設けるに当たっては、全くの自由というわけではありません。以下の2点に留意する必要があります(詳しくは厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要(詳細版)」3~4ページを参照してください)。
ⅰ.対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるが、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましい。
ⅱ.労使間で十分に協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に一部の高年齢者を排除しようとするものなど、本法の趣旨や他の労働関係法令・公序良俗に反するものは認められない。
このことから、例えば事業主が、70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)を導入する場合に、対象者を選定する基準として「会社が必要と認めた者に限る」などとすることは、恣意的に一部の高年齢者を排除することが可能になるので、本法の改正の趣旨に反し許されません。
2.継続雇用後の賃金・処遇の引き下げについて
では、事業主が70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)を導入して、高年齢労働者を継続雇用する際に、その者の賃金や処遇を引き下げることは可能でしょうか。
これについては、2021年改正前の継続雇用制度で同様のポイントが争われた裁判例が参考になります。
まず、賃金や処遇の引き下げを認めた裁判例として、学究社事件(東京地裁立川支部平成30年1月29日判決)があります。
この事案は、定年退職後、嘱託再雇用された進学塾の専任講師について、継続雇用後の賃金・処遇の引き下げ(定年時年俸638万円から60~70%減)が、無期と有期の労働者間の不合理な待遇差を禁止した旧労働契約法20条(現パートタイム・有期雇用労働法第8条)に反しないか争われたものです。
判決は、定年退職前の正社員としての労働時間、業務内容、業務に伴う責任の程度など比較し、また、定年後継続雇用者の賃金を定年退職前より引き下げることは一般的に不合理であるとはいえないとして、本件の賃金・処遇の引き下げは旧労働契約法20条に反しないと判示しました。
これに対し、賃金・処遇の引き下げを認めず、定年後再雇用の対象となる労働者に会社に対する慰謝料請求を認めた裁判例として、トヨタ自動車ほか事件(名古屋高裁平成28年9月28日判決)があります。
この事案は、定年時に事務職の主任であった正社員の定年後再雇用につき、会社が、1年間のパートタイマー(1日4時間、時給1000円)としてシュレッダー機ゴミ袋交換、業務用車掃除などの単純労務作業に従事させる取り扱いをしようとしたところ、当該労働者がこれを拒否し、そのまま定年退職になったというものです。
判決は、「・・定年後の継続雇用としてどのような労働条件を提示するかについては一定の裁量があるとしても、提示した労働条件が、無年金・無収入の期間の発生を防ぐという趣旨に照らして到底容認できないような低額の給与水準であったり、社会通念に照らし当該労働者にとって到底受け入れがたいような職務内容を提示するなど実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない場合には、当該事業者の対応は改正高年法の趣旨に明らかに反するものであるといわざるを得ない・・」などと判示し、当該労働者の会社に対する慰謝料請求を認めました。
この2つの裁判例から読み取れるポイントは、高年齢労働者を継続雇用する際に、その者の賃金や処遇を引き下げることは可能であるとしても、実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない場合には、改正高年法の趣旨に反し認められないということでしょう。
このポイントは、2021年の改正高年法における70歳までの継続雇用制度を導入する際にも該当すると考えられます。
なお、高年法の観点とは別に、同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法第8条)の観点からも、賃金や処遇の引き下げが問題となり得るので、この点は注意が必要です(上記の学究社事件のほか、長澤運輸事件、最高裁平成30年6月1日判決を参照)。
執筆=上野 真裕
中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。平成15年弁護士登録。小宮法律事務所(平成15年~平成19年)を経て、現在に至る。令和2年中小企業診断士登録。主な著作として、「退職金の減額・廃止をめぐって」「年金の減額・廃止をめぐって」(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話