
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
2020年4月7日、新型コロナウイルス対策として、政府による新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正法に基づく「緊急事態宣言」(同法32条)が出されました。そして、対象地域においては、法的根拠に基づく外出の自粛が要請されるに至りました。また、それに先立ち東京都では、ウイルスの感染拡大防止のため、「テレワーク、時差通勤、在宅勤務」が奨励されています(3月23日都知事会見)。
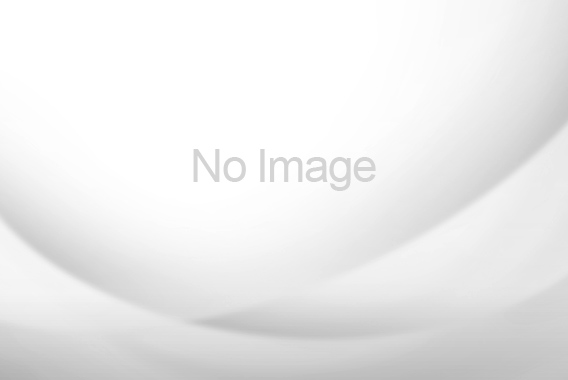
テレワークとは、労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務のことをいい、(1)在宅勤務(2)サテライトオフィス勤務(3)モバイル勤務の3つの形態があります。テレワークは働き方改革の一環として、近年、導入を進める企業が増えてきました。しかし、この状況下で、制度は未整備なまま、急に導入することになった企業が少なくないでしょう。
そこで今回は、テレワークを導入・実施する場合の法務上の留意点について、厚生労働省の「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(以下:「ガイドライン」)、「テレワーク導入のための労務管理等Q&A集」(以下:「Q&A」)、「テレワークモデル就業規則~作成の手引き~」(以下:「手引き」)などを参考に解説します。
テレワークを行う労働者にも、労働基準法をはじめとする各種労働基準関係法令が適用されます。導入・実施に当たっては、これらの法令に違反してはなりません。またテレワークは、労働時間の管理が難しい、仕事と仕事以外の切り分けが難しい、長時間労働になりやすいなどの問題点が指摘されています。実施に当たっては、こうした点について適切な労務管理を行うことが鍵になります。
テレワークを導入するに当たっては、最初に社内の基本方針やルールを定めておく必要があります。「Q&A」には、次の手順が挙げられています。急に導入することになった企業は、この手順を踏むことが難しかったケースもあるかと思いますが、導入後になったとしても、少なくとも【2】は至急、実行する必要があるでしょう。
【1】テレワークの対象業務と対象者の範囲を決定する
このうち、対象業務は、テレワークで実施しやすい業務(入力作業、データの修正・加工、資料の作成、企画などを思考する業務など)を選定します。対象者は、周囲の理解を得られるよう明確な基準を設けることが重要です。
また、個々の労働者がテレワークの対象となる場合であっても、実際にテレワークをするかは、本人の意思によるべきとされます。ただし、就業規則などにテレワークを命じる規定があれば、本人の意思にかかわらずこれを命じることができると考えられます。
【2】就業規則などにテレワークに関する規定を定めておく
テレワークを導入する場合、労働者が常時10人以上の会社では就業規則にテレワークに関する規定を定めておくことが必要です(労働基準法89条)。
具体的には、下記の3項目について定めておく必要があります。
<1>在宅勤務などテレワークを命じることに関する規定(10号参照)
<2>在宅勤務などテレワーク用の労働時間を設ける場合、その労働時間に関する規定(1号参照)
<3>通信費などの負担に関する規定(5号参照)
これらの規定は、就業規則に直接規定する場合と、「テレワーク勤務規定」といった個別の規程を定める場合があります。
後者の場合には、就業規則の「適用範囲」に関する規定に「従業員のテレワーク勤務(在宅勤務、サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務をいう。以下、同じ)に関する事項については、この規則に定めるもののほか『テレワーク勤務規定』に定めるところによる。」などと就業規則に委任規定を設けることにより、「テレワーク勤務規定」に就業規則と同様の効力を持たせることができます。
なお「手引き」には、モデル「テレワーク就業規則」(在宅勤務規程)が掲載されていますので、これからテレワークの導入を急ぐ企業は、 これをカスタマイズして活用することをお勧めします。
【3】テレワーク利用者とオフィス勤務者とのコミュニケーションの方法について取り決めておく
あらかじめ通常時または緊急時の連絡方法について、労使間で取り決めておくことが望ましいとされます。
【4】テレワーク導入に当たっての教育・研修を実施する(テレワーク利用者だけでなく、上司・同僚にも行う)
教育・研修によって、テレワークの実施目的などについての認識を共有するとともに、テレワーク実施時の不安や疑問を解消することができます。
上記の順に従って取り決めた基本方針やルールについては、労使間で認識に齟齬(そご)が生じないよう、あらかじめ導入目的や対象業務、対象者の範囲、テレワークの実施方法などについて、労使委員会(労働者側は、労働組合がある場合には労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者が参加)などで十分に協議した上で、これを文書に保存するなどの手続きを経ることが望ましいとされます。
さらに作成した文書は、社内に周知するため配布することが望ましいと考えられます。これらについても、急な導入時には対応できなかったとしても、できるだけ早く対応するようにしましょう。
就業規則に直接規定する場合も、「テレワーク勤務規程」などの個別の規程を定める場合も、テレワークに関する規程を作成・変更したときには、所定の手続きを経て、労働者代表の意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出ることが必要です。
以上に加え、労働契約を締結している者に対して新たにテレワークを行わせる場合には、就業の場所として「労働者の自宅」などと明示した書面を交付する必要があります(労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条第1項第1の3号)。また、テレワークの実施と併せて、始業および終業の時刻の変更などを行うことを可能とする場合には、労働者に対し、その旨の明示をしなければなりません(労基法施行規則第5条第1項第2号)。
前述した通り、テレワークの実施に際しては、適切な労務管理を行うことが鍵となります。この点について、いくつか留意点を述べます。
●労働時間の把握
使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録しなければなりません。ただ、テレワークにおいては、業務時間中の在席確認がしづらいという固有の問題があります。そのため、テレワークの労働時間の管理方法について社内で確認し、ルールを決めておく必要があります。例えば、次の通りです。
≪1≫ テレワークにおいても通常の労働時間制(1日8時間、1週40時間の原則に基づき就業規則で労働時間を規定。労基法第32条)を採用する場合には、始業・終業時刻の管理は、Eメール、電話、勤怠管理ツールによるほか、業務中に常時通信可能な状態にしておくことが考えられます。
在席確認は、Eメール、労務管理ツール、労働時間(在席)中は常に電話連絡できる状態にすることのほか、テレワークのパソコン作業画面を閲覧できるようにする方法が考えられます。なお、休憩時間については、労基法上、労働者に一斉付与することが原則ですが(同34条2項本文)、労使協定によりこれを変更することができます(同条項ただし書き)。
実際の取り組みとしては、テレワークする労働者が勤務に入るとき、休憩の前後、退社時刻に上司にメールを送ることにより労働時間を管理し、業務内容は前日に翌日行う業務内容について連絡してもらい、翌日の業務終了時に成果物を出してもらって確認するというルールを定めている企業があります。
また、パソコンの起動開始、終了時間のログをソフトで自動的に収集し、その時間と申告した残業時間に差異があるような場合には管理職に問い合わせをして確認する方法を採用している企業もあります。この企業では、業務開始時に、会社がテレワークをする者に、今日、何の業務をするのか確認するものの、1日で終わる仕事がなく同時並行的に複数の業務を行うことから、月次で必ずやらなければならない仕事や、特命事項について期日を守れば、細かいことは個々の社員に任せているとのことです。
≪2≫ テレワークに際して生じやすい事象として、いわゆる中抜け時間があります。例えば、テレワークをする労働者が、育児・介護など私用のために一定時間業務から離れるというものです。このような時間について、労働者が使用者から業務の指示をされずに自由に利用することを保証されている場合には、その開始と終了の時間を報告させることにより、休憩時間として扱い終業時刻を繰り下げたり、あるいはその時間を時間単位の年次有給休暇として取り扱ったりすることが可能です。
ただし、終業時刻を繰り下げる場合には、あらかじめ就業規則に規定しておくことが必要であり、年次有給休暇として取り扱う場合には、労使協定の締結が必要となります。
≪3≫ 上記≪1≫の場合と異なり、テレワークにより労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務した場合において、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難なときには、事業場外労働のみなし労働時間制が適用され、テレワークを行う労働者は、就業規則などで定められた所定労働時間を労働したものと見なされます(労基法第38条の2第1項本文)。
これは、以下の3つの要件を全て満たした場合に適用されます。
{1}テレワークが、起居寝食など私生活を営む自宅で行われること
{2}テレワークで使用しているパソコンが使用者の指示により常時通信可能な状態になっていないこと
{3}テレワークが、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
実際の取り組みとしては、1日の標準労働時間7時間30分と設定し、テレワークや直行直帰する場合、みなし労働時間として所定時間勤務したものとし、各自が基本的に自主管理して記録します。月単位で総労働時間を集計し、それを上長が承認するというやり方をしている企業があります。
●長時間労働対策
前述した通り、テレワークは長時間労働になりやすいという問題点が指摘されており、企業は単にテレワークをする労働者の労働時間を管理するだけでなく、長時間労働による健康障害防止を図ることが求められます。その手段としては、(A)時間外、休日または深夜におけるメール送付の抑制(B)深夜・休日のシステムへのアクセス制限(C)テレワークを行う際の時間外・休日・深夜労働の原則禁止(D)長時間労働を行う労働者への注意喚起などが考えられます。
●通信費、情報通信機器などのテレワークに要する費用負担の取り扱い
これらの費用は、通常の勤務と異なり、テレワークを行う労働者がその負担を負うことがあり得ます。そこで、労使のどちらが負担するか、また、使用者が負担する限度額、労働者が請求する場合の請求方法などについて、あらかじめ労使で十分に話し合い、就業規則などに定めておく必要があります(労基法第89条第5号)。
●労働災害の補償
テレワークの場合も、労働者は労働者災害補償保険法の適用を受け、業務災害または通勤災害に関する保険給付を受けることができます。ただし、私的行為など業務以外が原因のものについては、業務上の災害とは認められません。使用者は、この点を十分に周知させることが望まれます。
以上のように、労働関連法規を遵守してテレワークを導入・実施するためには、かなりの作業が発生します。今回、事業継続のために急いで導入した場合でも、対応が必要になります。これだけの手間をかけるのですから、テレワークを新型コロナウイルス対策として一時的に導入するだけでなく、働き方改革を実現するための方策として位置付けて、経営に生かすことを考えるべきでしょう。そうすれば、導入や管理の手間は生産性向上と相殺できます。
※記事の内容は4月8日時点の情報に基づいています
執筆=上野 真裕
中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。平成15年弁護士登録。小宮法律事務所(平成15年~平成19年)を経て、現在に至る。令和2年中小企業診断士登録。主な著作として、「退職金の減額・廃止をめぐって」「年金の減額・廃止をめぐって」(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話