
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
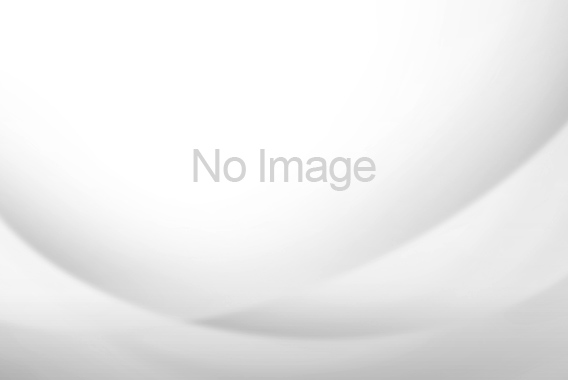
2024年11月1日より改正道路交通法が施行され、自転車の酒気帯び運転についても、罰則が適用されることになりました(第117条の2の2第1項第3号〔罰則〕、第65条第1項〔酒気帯び運転の禁止〕)。また、自転車の酒気帯び運転をする恐れのある者に酒類を提供しまたは飲酒をすすめた者にも罰則が適用されます(第117条の3の2第2号〔罰則〕、第65条第3項〔酒類提供罪〕)。
コロナ禍を契機とした健康志向の高まりにより、近時、自転車通勤は増加傾向にあるようです。また、以前から通勤の全部ではなく、最寄りの駅まで自転車を使っているケースは少なくありません。
企業が従業員の自転車通勤を導入する場合の進め方と注意点は、本連載においてすでに取り上げました(企業における自転車通勤導入の進め方と注意点)。今回、自転車の酒気帯び運転について罰則が適用されるようになり、企業にとって思わぬリスクを生じさせる恐れがあります。忘年会、新年会、送別会、プロジェクトの打ち上げ会など会社組織として開催する酒類を提供する行事があるときは、特に注意が必要です。
そこで今回は、自転車の酒気帯び運転、ほう助、それに対する罰則について定めた改正道路交通法の概要について説明します。あわせて本改正による企業にとってのリスクやリスクを避けるための注意点について解説します。
冒頭に述べたとおり、改正道路交通法では、自転車の酒気帯び運転についても、罰則が適用されます(第117条の2の2第1項第3号〔罰則〕、第65条第1項〔酒気帯び運転の禁止〕)。
これまでも、飲酒して自転車を運転することは禁止されていましたが(第65条第1項)、処罰の対象とされたのは、酩酊(めいてい)状態(アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態)で運転する「酒酔い運転」のみでした(第117条の2第1項、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
しかし、今回の改正により「酒酔い運転」に至らない「酒気帯び運転」についても、罰則の対象となりました(第117条の2の2第1項第3号、3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転することをいいます。
これは、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、罰則の対象を「酒気帯び運転」にも広げて、自転車による交通事故の抑止を目的としたものです。
自転車の酒気帯び運転をした者だけでなく、自転車の酒気帯び運転をする恐れのある者に酒類を提供しまたは飲酒をすすめた者にも罰則が適用されます(第117条の3の2第2号〔罰則〕、第65条第3項〔酒類提供罪〕)。
具体的には、自転車の酒気帯び運転をする恐れのある者に酒類を提供しまたは飲酒をすすめ、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合、酒類を提供しまたは飲酒をすすめた者に対して、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。なお、自転車を運転する者が、酩酊(めいてい)状態で運転する「酒酔い運転」に至っていた場合には、酒類を提供しまたは飲酒をすすめた者に対して、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(第117条の2の2第1項第5号)。
他にも、自転車の酒気帯び運転をする恐れのある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合には、自転車の提供者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(第117条の3の2第4号〔罰則〕、第65条第2項〔車両提供罪〕)。
さらに、自転車の運転者が酒気を帯びていると知りながら、当該運転者に対し、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合には、同乗した者に対して、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(第117条の3の2第3号〔罰則〕、第65条第4項〔同乗罪〕)。自転車を運転する者が、酩酊(めいてい)状態で運転する「酒酔い運転」に至っていた場合には、同乗者に対して、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(第117条の2の2第1項第6号)。
今回の自転車の酒気帯び運転やそのほう助に関する道路交通法の改正は、自転車通勤を認めている企業に、思わぬリスクを生じさせる恐れがあります。
すなわち、企業が自転車通勤規定を定め、それに基づいて自転車通勤をする従業員に対して自転車通勤許可申請書兼誓約書の提出を求めているなど、従業員の自転車通勤の実態を把握している場合において、当該企業で開催する忘年会・新年会など酒類を伴う宴席や会合に、自転車通勤をしている従業員を参加させ酒類を提供することは、主催者や上司が、自転車の酒気帯び運転をする恐れのある者に酒類を提供しまたは飲酒をすすめたとして、酒類提供罪に該当し、罰則が科される恐れがあります。
このようなリスクを避けるためには、企業では、日頃から自転車通勤をしている従業員に対して、酒類を伴う宴席や会合に参加するときには、通勤に自転車を利用しないようアナウンスしておき、宴席や会合のときにも、改めて、自転車を運転して帰宅しないよう告知をするなど積極的な働きかけが大切です。
企業における酒類を伴う宴席や会合の際に、従業員による自転車の酒気帯び運転が横行するようであっては、企業のコンプライアンスの観点からも問題視されます。こうした事態を避けるためにも、今回の自転車の酒気帯び運転やそのほう助に関する道路交通法の改正について、社内への周知徹底が望まれます。
執筆=上野 真裕
中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。平成15年弁護士登録。小宮法律事務所(平成15年~平成19年)を経て、現在に至る。令和2年中小企業診断士登録。主な著作として、「退職金の減額・廃止をめぐって」「年金の減額・廃止をめぐって」(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話