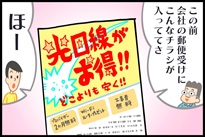
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線

新型コロナウイルスが日本で初めて確認されてから、1年4カ月が過ぎました。コロナ禍はいまだ終わりが見えず、企業としてもコロナウイルス対策に十分な注意を払いながら事業運営せざるを得ない状況が続いています。そこで、今回は、従業員が新型コロナウイルスに感染してしまった場合の補償や、企業として講じるべき対策のポイントなどについてご説明します。
ア.新型コロナウイルスと労災補償制度
労働者が業務中や通勤中にけがを負ったり病気を患ったりした場合のために、法律上一定の補償を行う制度(労災補償制度)が用意されています。新型コロナウイルスに感染した場合も、労働基準監督署長から労災であると認定されれば、労働者は補償を受けることができます。
新型コロナウィルス感染症に係る労災認定事例
実際に、職場での新型コロナウイルス感染が労災にあたると認定された事例については、以下の厚生労働省の資料(令和3年2月1日付)をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf
イ.労災補償の概要
労災であると認定された場合に、労働者が受けることができる補償の概要は、以下のとおりです。
(1)療養補償給付
指定医療機関等では、無料で治療や薬剤の支給を受けることができます。また、近くに指定医療機関などがなく、それ以外の医療機関等にかかった場合には、その療養にかかった費用の給付を受けることができます。
(2)休業補償給付
療養のために仕事を休んだことにより賃金が4日以上支給されない場合には、休業1日につき基礎日額の60%相当額の支給などを受けることができます。
(3)障害補償給付
業務上の傷病が治ったものの一定の障害が残った場合に、後遺障害の程度に応じて一定額の金銭の支給を受けることができます。
(4)遺族補償給付
業務上の傷病により労働者が亡くなった場合に、その遺族が一定額の金銭の支給を受けることができます。
ウ.労災認定の要件
病気が労災であると認定されるためには、業務起因性(業務によりその病気を患ったこと)が認められる必要があります。感染症の場合、業務起因性が認められるためには、通常、感染経路の特定が必要です。
しかし、新型コロナウイルスの場合、現時点における感染状況と、症状が出なくとも感染を拡大させるリスクがあるという特性から、「調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合」には、労災として認定されるという通達が出ています。
例えば、複数の感染者が確認された労働環境下での業務や、顧客などとの接触の機会が多い労働環境下での業務は、相対的に感染リスクが高いと考えられています。
このような環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、(新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況などを調査した上で、医学専門家の意見も踏まえての判断となりますが)感染経路が特定できなくとも、労災と認定される可能性が十分にあります(※)。
※なお、医療従事者などが感染した場合は、原則として労災保険給付の対象となります。
企業が十分な感染防止策を講じていなかった場合、業務中に新型コロナウイルスに感染してしまった従業員は、労災補償の請求に加えて、勤務先企業に対して安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求をすることも考えられます。
ただし、この請求が認められるためには、前述の業務起因性に加えて、勤務先企業が安全配慮義務に違反し、当該義務違反により感染したといえることが必要です。
企業としては、従業員が業務中に新型コロナウィルスに感染しないよう、「職場における新型コロナウィルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料」(厚生労働省)や「業種別ガイドライン」(内閣官房(令和3年4月6日付)/PDF表示)などを参考に、十分な対策を講じながら事業を運営する必要があります。
加えて、どのような対策を講じていたのかについて、記録を取っておくことも重要です。まず、記録付けを習慣化することにより、間接的に日々の感染症対策漏れの防止につながり得るでしょう。また、残念ながら従業員との間で安全配慮義務違反を理由とする訴訟になってしまった場合に、当該記録は、企業が安全配慮義務に違反していないことを示す重要な証拠として、企業を守る資料になり得ます。
新型コロナウイルスは感染力が非常に強いため、十分な対策を講じても、従業員が業務中に感染してしまうことはあり得ます。このような場合、企業としては、労災と認められれば補償が受けられることを伝えるなどして、感染してしまった従業員を積極的にサポートすることが大切でしょう。
執筆=福原 竜一
虎ノ門カレッジ法律事務所 弁護士 2009年弁護士登録。企業法務及び相続法務を中心業務とする。主な著作として、「実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパクトガイド」(編著:2019年10月:ぎょうせい)がある。2019年8月よりWEBサイト「弁護士による食品・飲食業界のための法律相談」を開設し、食に関わる企業の支援に力を入れている。https://food-houmu.jp/
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話