
脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」(第98回)
"トンネル"を抜けてデータを安全にやり取り
2017年5月26日、民法の一部を改正する法律が成立しました。一部の規定を除いて2020年4月1日から改正された民法(以下:「新法」)が施行されます。契約のルールは民法により定められていますから、改正によって契約書の条項について見直しが行われるケースが出てくるでしょう。
今回は、金銭消費貸借契約やそれに付随する保証契約について、新法に対応した見直しが行われる中で、借り主や保証人の立場として、どのような点に注意をする必要があるか解説します。
なお、契約書の変更では、その契約書に改正前の民法(以下:「旧法」)と新法のいずれが適用されるのかを明確に意識することが重要です。新法が施行された後にもかかわらず、依然として旧法で使われていた条項を用いている場合、あえて旧法の規定に従った合意をしていると解釈される可能性があります。この点に注意を払いながら契約書の条項をチェックする必要があります。
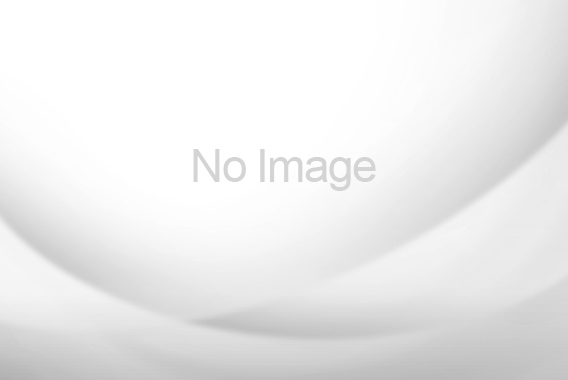 企業活動においては、銀行などの金融機関から融資を受ける場合や、重要な取引先やグループ会社に対する資金融通が実施される場合など、金銭消費貸借契約を締結するケースが少なくありません。金銭消費貸借契約については、旧法では要物(ようぶつ)契約とされており、実際に金銭が交付されないと契約が成立しないものとされていました。
企業活動においては、銀行などの金融機関から融資を受ける場合や、重要な取引先やグループ会社に対する資金融通が実施される場合など、金銭消費貸借契約を締結するケースが少なくありません。金銭消費貸借契約については、旧法では要物(ようぶつ)契約とされており、実際に金銭が交付されないと契約が成立しないものとされていました。
新法ではこの点について、書面または電磁的記録により消費貸借契約が締結されれば、実際に金銭などを交付しなくても消費貸借契約が成立することになりました(新法587条の2第1項)。
これにより貸主に金銭を貸し付ける義務が生じました。そのため、例えば貸主が借り主に対し、貸し付け実行日に金銭を交付できなかった場合は、貸主は債務不履行責任を負うこととなり、借り主に生じた損害を賠償する責任を負うことになります。また、理論上は借り主の債権者が、金銭消費貸借契約上の金銭交付請求権を差し押さえるといった事態も想定されます。
貸主がこのような事態を万一にでも防ぎたい場合、金銭消費貸借契約自体の効力に関して、一定の停止条件を設けたり、金銭の交付について前提条件を設けたりすることで、契約締結と同時に金銭を貸し付ける義務を生じさせない契約書を作成することが考えられます。そうした条項が契約書に入っている場合、借り主としては条件が貸主に有利なものとなっていないかチェックする必要があります。
新法では、金銭消費貸借契約を締結した後でも、借り主は金銭の交付を受けるまでの間、契約を解除することができるようになりました(新法587条の2第2項)。例えば借り主に資金需要がなくなった場合などには、こうした行為が生じる可能性があります。これにより貸主に損害が生じた場合、新法では借り主は貸主に生じた損害を賠償しなければならないことが規定されています。
この点、貸主にとって、金銭を貸し付ける機会を喪失したことにより損害が発生したことを立証することは容易ではありません。そこで、貸主が円滑に損害賠償請求権を行使できるようにするため、契約書において具体的な損害額を定めた違約金条項が設けられることが想定されます。借り主としては、事業計画の変更などにより資金調達が不要になる可能性も視野に入れながら、違約金条項を受諾してよいか検討することが必要でしょう。
新法では、主債務者(本稿では金銭消費貸借契約における借り主を指します。以下同様)の委託を受けた個人の保証人が、主債務が事業のために負担する債務の保証をする場合などには、主債務者が保証人に対し、主債務者の財産収支の状況や主たる債務以外に負担している債務などの情報を提供する義務が生じました(新法465条の10第1項および第3項)。
簡単にいえば、事業について融資を受ける借り主(主債務者)は、保証人になってくれた個人に対して、財産の収支や他の借入金について知らせなくてはならないということです。主債務者がこの情報提供義務に違反して情報提供を怠ったり、虚偽の情報提供を行ったりした結果、保証人が主債務者の財産状況などを誤認して保証契約が締結されてしまった場合、主債務者がそのことについて悪意有過失であれば、保証人は保証契約を取り消すことができます(新法465条の10第2項)。
債権者である貸主にとって、保証契約を取り消されることは根本的なリスクです。貸主としては、保証契約を取り消されるリスクを防止するないし軽減するため、借り主に対し、金銭消費貸借契約書において主債務者が保証人に対してきちんと情報提供を行ったことを表明させた上で保証させることが考えられます(このように一定の事項を表明、保証させることは一般的に「表明保証」と呼ばれる)。併せて、貸主から、きちんと情報提供を受けたという確認書を保証人から取得することを要求される可能性もあります。
借り主としては、金銭消費貸借契約書の中に表明保証に関する条項や、保証人からの書面取得を義務付ける条項があるかどうかチェックして、それらの条項がある場合は契約違反にならないよう注意をすべきであるといえます。
新法では、個人による保証のうち事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約などについて、保証人になろうとする者が保証契約を締結する1カ月以内に公正証書でその旨を意思表示しなければ保証契約の効力が生じないことが原則となりました(新法465条の6第1項及びおよび第3項)。
この原則には例外があり、主債務者が法人である場合で、その法人の取締役や一定の議決権を有する株主などが保証人となる場合は例外的に公正証書の作成は不要とされています(新法465条の9)。中小企業では法人の取締役が保証人となるいわゆる経営者保証が通常ですから、この例外により公正証書の作成が不要になる場合がほとんどであると考えられます。
不要になるとはいえ、貸主としては保証契約が無効になるかどうかの重要なポイントですので、保証人となる取締役が単なる名目上の取締役や登記簿上の取締役ではなく真実に取締役であることや、取締役に選任されたことを裏付ける書類の適法性や真実性について保証契約で表明保証させられることが考えられます。そのような条項がある場合は、提出した株主総会議事録などの書面が適法なものであるかチェックして、表明保証違反にならないよう注意をする必要があります。
執筆=近藤 亮
近藤綜合法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属) 平成27年弁護士登録。主な著作として、『会社法実務Q&A』(ぎょうせい、共著)、『少数株主権等の理論と実務』(勁草書房:2019、共著)、『民事執行法及びハーグ条約実施法等改正のポイントと実務への影響』(日本加除出版:2020、共著)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話