
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
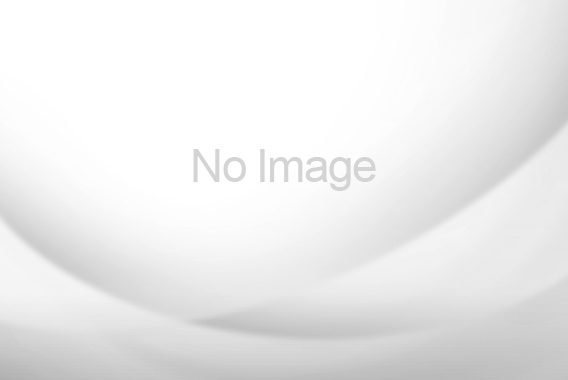
新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年春以降、リモートワークが続いている人は多い。仕事のスタイルも変わり、社内の会議だけでなく、取引先との打ち合わせなどについても、Zoom、Microsoft Teams、Google Meetなどを用いたWEB会議で行われることが増えています。それにつれて、新聞やTVなどで、リモートワーク環境におけるハラスメントを意味する「リモハラ(リモートハラスメント)」という言葉が用いられるようになっており、ハラスメントの一類型として認識されてきています。
例えば具体的なリモハラの例として、こんなものがあります。経営者の皆さまは特に参考にしてください。
・業務上必要な範囲を超えてWEB会議の開催を求める
・WEB会議の際に、カメラをオンにするように求める、壁紙を使わないように求める、全身を写すように求める
・カメラに映った室内の様子や私物に関して私的な質問を過度にする、業務外の私生活について説教をする、家族の紹介を求める
・オンライン飲み会への参加を強く求める……など
WEB会議に特有のコミュニケーション方法だけでなく、これまで、出勤して面と向かってのやり取りでは表立って問題とされなかった行動でも、WEB会議で問題となりやすくなったものもあり、注意が必要です。
特に、WEB会議の場合、対話者間での閉鎖された空間になりやすい反面、録画・録音をすることも容易であり、やり取りの内容が客観的な記録として残りやすいという特徴があります。このため、ハラスメント行為による休業などが発生した場合には、WEB会議でのやり取りが証拠として提出される可能性があります。また、リモハラのみで高額の損害が発生する場合ではなくとも、解雇や残業代請求に関する請求がされた場合、原因として記録が付加される可能性があります。
では、リモハラが発生するのを防止するために、どのように対処すればよいでしょうか。
上記の例では、これまで人格権を侵害するハラスメント行為などとして問題とされてきた、(1)パワーハラスメント(2)セクシュアルハラスメント(3)プライバシー侵害に該当するものであり、同様の観点で対処をしていく必要があります。
以下では、問題ごとに分けて、基本的な考え方を説明します。
特にパワーハラスメント、セクシュアルハラスメントの詳細については、下記の厚生労総省のホームページをご参照ください。職場におけるハラスメントの防止について説明しています。
「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
パワーハラスメントについては、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が大企業に対して2020年6月1日から施行されており、中小企業に対しても2022年4月1日から施行されます。
職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより(3)労働者の就業環境が害されるものです。(1)~(3)までの要素を全て満たすものをいうとされています。もっとも客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
厚生労働省のガイドラインでは、以下の6つの類型が挙げられています。過小な要求や、個の侵害もパワーハラスメントとされていることに、注意が必要です。
1)身体的な攻撃:暴行・傷害
2)精神的な攻撃:脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
また、労働施策総合推進法で事業主に対して義務付けられた措置として、例えば相談に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備があります。具体的には、相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること、相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすることが求められています。
男女雇用機会均等法11条1項では、以下のように記されています。
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
ここで「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所をさし、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれるとされています。リモートワークで在宅勤務している場合でも、「職場」に該当します。
また、「性的な言動」とは、性的な内容の発言および性的な行動とされており、典型的なものとして、次の例が挙げられています。
<例1>性的な内容の発言
性的な事実関係を尋ねること
性的な内容の情報(噂)を意図的に流布すること
性的な冗談やからかい
食事やデートへの執拗な誘い
個人的な性的体験談を話すこと など
<例2>性的な行動
性的な関係を強要すること
必要なく身体へ接触すること
わいせつ図画を配布・掲示すること
強制わいせつ行為
強姦 など
セクシュアルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たり個別の状況を考慮する必要があることに注意してください。
具体的には、「労働者の意に反する性的な言動」および「就業環境を害される」の判断に当たっては、労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると客観的な視点も必要となります。
プライバシーの概念は広く、判例における違法なプライバシー侵害の判断に当たっては、基本的には、人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えているか否かが基準とされています。特に、労働者に対する違法なプライバシー侵害となるか否かは、使用者による情報取得の必要性と方法を勘案しての具体的判断になると解されています。
Web会議の場合における侵害例として考えられるものとして、以下の例が考えられます。
・カメラをオンにするように強要する
・参加者に、壁紙を使わないように指示する
・カメラに映った室内、私物に関して、私的な質問をする
いずれの場合も、使用者による情報取得の必要性があるかなどによって、違法なプライバシー侵害となり得ることを前提に、対応をすることが重要です。
企業で、リモハラの発生を防止するためには、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、プライバシー侵害などが生じないように、在宅勤務時におけるWEB会議の利用について、一定のルールを設けることも検討が必要となります。長時間労働対策やワークライフバランスの観点からも、休日や深夜におけるWEB会議の実施を避けることも重要となります。その際、違反があった場合懲戒処分の対象となる就業規則の扱いにするか、管理職用の心得のようなものとするかについても検討が必要です。
また、ルールの策定と併せて、特に管理職の職員に対しては、リモハラの加害者とならないように、ルールや注意点の周知や、研修を行うことが重要となります。そのほか、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントに関しては、従業員用の相談窓口を設置し、相談できる体制を設けることが必要です。
最後になりますが、リモハラの発生を避けるためには、リモートワークの際におけるコミュニケーションは面と向かった場合よりはるかに難しいことを認識した上で、相手の人格を尊重する意識を持ち、態度に示すことが何より重要です。
執筆=渡邊 涼介
光和総合法律事務所 弁護士 2007年弁護士登録。元総務省総合通信基盤局専門職。2023年4月から「プライバシー・サイバーセキュリティと企業法務」を法律のひろば(ぎょうせい)で連載。主な著作として、『データ利活用とプライバシー・個人情報保護〔第2版〕』(青林書院、2023)がある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話