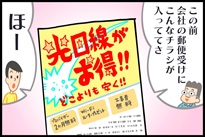
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
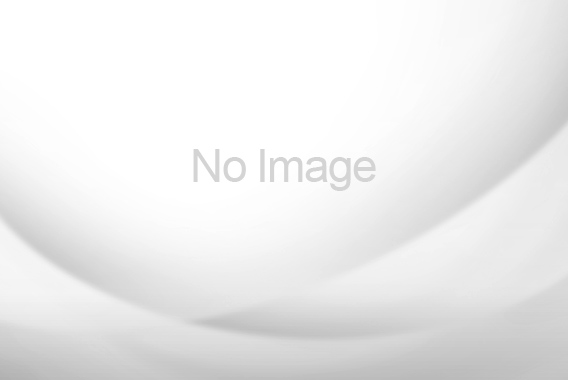
道路交通法が改正され、2023年4月から「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」と、自転車運転者のヘルメットの着用が努力義務化されたことが話題になりました。
自転車は、プライベートで使う以外に通勤にも使われています。通勤の全部ではなく、最寄りの駅まで自転車を使っているケースは少なくありません。
そこで、本稿ではこうした最近の状況を踏まえて、自転車活用推進官民連携協議会「自転車通勤導入に関する手引き」(以下:「手引き」)を参考に、企業における自転車通勤導入のメリットを確認した上で、自転車通勤において生じうる法的問題について明らかにし、その進め方と注意点を解説します。
従業員の自転車通勤は、事業主にとって通勤手当や固定経費などの経費の削減、従業員の時間管理能力や集中力の向上による生産性の向上、会社のイメージアップ、雇用の拡大(従業員の自転車通勤を認めれば雇用範囲が広がり、雇用の拡大につながります)といったメリットがあります。
他方、従業員にとっても、通勤時間の短縮(自転車は近・中距離での通勤時間の短縮に効果的であり、定時性に優れています)、心身の健康増進といったメリットがあります。
こうした事業主・従業員双方にとってメリットのある自転車通勤ですが、従業員が自転車事故を起こした場合、当該従業員は、①対人・対物の損害賠償などの民事上の責任、②(重)過失致死傷罪などの刑事上の責任、③自動車運転免許の停止などの行政上の責任を負う場合があります(注1)。このうち①の民事上の損害賠償責任については、5000万円~1億円近い高額の賠償金が課せられた裁判例がいくつかあるので、注意が必要です(手引き24ページ)。
また、従業員が自転車事故を起こした場合、それが「事業の執行」の際のものであれば、事業主は「使用者責任」(民法715条)を負い、従業員が第三者に加えた損害について責任を負う場合があります。この「事業の執行」については、被害者保護の観点から、外形上職務の範囲内のように見えるかを基準にし(外形標準説といいます)、広範に解されています。例えば、従業員が自転車通勤途中に私用のため通勤経路を外れた場合であっても、事業者名の出ている自転車で事故を起こしたときには、事業主が損害賠償責任を負う場合があります。
他方、従業員が自転車通勤途中に事故に遭って負傷した場合には、労働災害(通勤災害)として、労災保険により医療費や事故に遭わなければ得られるはずの賃金などが補償されます。労働災害(通勤災害)と認められなければ健康保険が適用されるものの、医療費の3割や生活費は従業員自身の負担となります。そのため、通勤災害に該当するか否かの区別は、従業員のみならず事業主にとっても大切です。
以上の通り、自転車通勤において生じうる法的問題としては、従業員が自転車事故を起こした場合の、①従業員自身の責任、②事業主の責任および従業員が自転車通勤途中に事故に遭って負傷した場合の、③労働災害(通勤災害)が挙げられます。
自転車通勤においては、上記のような法的問題が生じうるため、中小企業がこれを導入する場合は事業主として、まず、従業員自身が自転車事故を起こさないようにする配慮が求められます。
また、万一従業員が自転車事故を起こした場合、現場で適切な対応がなされ、かつ被害者に対して必要十分な損害賠償がなされるよう配慮する必要があります。さらに、従業員が自転車通勤途中に事故に遭った場合の補償についても配慮が必要です。
具体的な自転車通勤導入の進め方としては、こうした点について配慮した自転車通勤規程を定め、それに基づいて自転車通勤をする従業員に対して、自転車通勤許可申請書兼誓約書の提出を求めることが考えられます。手引きでは、自転車通勤規程について、以下の内容を設けています(法的問題に関わらない部分は割愛します)。
(1)対象者・・・・・・自転車を運転可能な健康状態にある従業員であること。
(2)対象とする自転車・・・・・・自転車の安全に関わる装備が法律に準拠し、正しく装着されていること、定期的な点検・整備を行っていること。
(3)目的外使用の承認・・・・・・用務場所への直行直帰や私事目的での立ち寄りの許容範囲など。
(4)通勤経路・距離・・・・・・合理的な通勤経路や距離とすること。
(5)公共交通機関との乗り継ぎ・・・・・・自宅から勤務地までの合理的な経路上で、自転車と公共交通機関を乗り継げるとすること。
(6)日によって異なる交通手段の利用・・・・・・天候などの理由により、日によって交通手段の変更を認めること。
(7)安全教育・指導とルール・マナーの遵守・・・・・・自動車の交通安全に関する教育・指導を受講すること、交通規制や自転車の利用マナーを遵守すること。
(8)事故時の対応・・・・・・事故時に事業者・従業員の双方が行うことの明確化、緊急連絡体制など。
(9)自転車損害賠償責任保険などへの加入・・・・・・自転車通勤をする従業員自身のけがによる入院・通院などが補償される保険、従業員が事故を起こした場合の対人・対物の賠償責任を補償する保険にそれぞれ加入すること、シェアサイクルを利用する場合もこれらの保険へ加入することなど。
(10)ヘルメットの着用・・・・・・自転車通勤をする場合、ヘルメットの着用に努めること。
(11)申請・承認手続き・・・・・・自転車通勤をする場合、あらかじめ主管する部署に自転車通勤許可申請書兼誓約書などの所定の申請様式を提出し、事業主の許可を得ること、事業主は許可した者に対して「許可証シール」を交付し、許可を受けた者は、それを自転車の視認できる箇所に貼付することなど。
このうち(3)~(6)は、事業主たる会社が責任を負う範囲や通勤災害と認定されるか否かを画するために求められたものと考えられます。また、(9)に関連して補足すると、従業員が事故を起こした場合の対人・対物の賠償責任は従業員が負いますが、前記の通り、それが事業活動中の事故である場合には、事業者も使用者責任を問われる場合があります。そこで事業者も、対人・対物への賠償責任を補償する「自転車損害賠償責任保険等」への加入が必要となります。
そして、上記規程に対応して自転車通勤を希望する従業人に提出を求める自転車通勤許可申請書兼誓約書には、許可申請期間、申請理由、防犯登録番号、任意保険の有効期間、通勤ルート、通勤距離、所要時間などを記載させ、安全に関する事項について誓約を求めます。
以上のように進めると、事業主たる会社は、生じうる法的問題に対応しつつ、自転車通勤の導入が可能となります。
なお、自転車通勤規程、自転車通勤許可申請書兼誓約書のいずれも手引き38ページ以下にテンプレートがありますので、これらをベースに会社の実情に応じてカスタマイズして利用すればよいでしょう。
注1:③については、意外に思われるかもしれませんが、自転車は道路交通法上の軽車両として同法が適用されるため(同法2条1項11号)、自転車事故が「・・自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」に該当する場合、自動車運転免許の停止処分の対象となります(同法103条1項8号)。
執筆=上野 真裕
中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。平成15年弁護士登録。小宮法律事務所(平成15年~平成19年)を経て、現在に至る。令和2年中小企業診断士登録。主な著作として、「退職金の減額・廃止をめぐって」「年金の減額・廃止をめぐって」(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話