
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
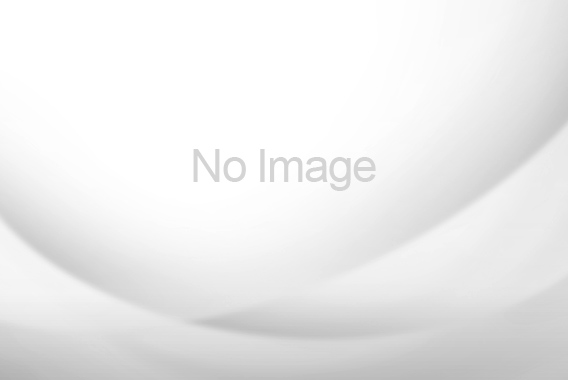 1つの会社に勤め続けることが一般的だった時代から、転職が当たり前の時代になっています。転職の際には、1から新しいことを学ぶ必要がない同業種を選ぶケースも少なくないでしょう。そうなると、競合するライバル企業への転職も考えられます。
1つの会社に勤め続けることが一般的だった時代から、転職が当たり前の時代になっています。転職の際には、1から新しいことを学ぶ必要がない同業種を選ぶケースも少なくないでしょう。そうなると、競合するライバル企業への転職も考えられます。
従業員がライバル企業に転職することを防ぐことはできません。しかし、転職に伴って社内の情報が流出してしまうことは、最小限度に抑えたいもの。企業秘密の流出については、不正競争防止法や著作権法である程度阻止できます。ただ、法律による対応には限界があるので、就業規則にも明記しておくことが必要です。
今回は、従業員の業務上の成果物が会社のものであることを証明して、転職先で使われることを防ぐ対策について紹介します。
最初の対策は、不正競争防止法に基づくものです。不正競争防止法は、不正な方法で営業秘密を取得すること、取得した営業秘密を使用することなどを禁止しています。従業員の作成した資料が不正競争防止法上の営業秘密に該当すれば、その使用に対し差し止めや損害賠償請求、また刑事告訴などの法的な対抗策を取ることができます。
不正競争防止法で「営業秘密」として保護されるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
(1)秘密管理性(秘密として管理されていること)
(2)有用性(営業上または技術上、有用な情報であること)
(3)非公知性(公然と知られていないこと)
流出すると困るような情報であれば(2)と(3)の要件は満たすことが多いでしょうから、問題になるのは(1)です。
(1)の秘密管理性の要件を満たす条件は、企業が秘密として管理している、もしくは客観的にも秘密として管理されている状態です。また、その意思が従業員にも認識されている状態になります。
それを端的にいえば、従業員の作成した資料に何らかのアクセス制限が設けられている状態です。つまり鍵をかけた保管庫やパスワードを設定したデータストレージなどに保存している資料には秘密管理性があるということです。逆に、社内で誰でも閲覧可能な状態に置かれている資料については、営業秘密として保護されないということになります。
次の対策が、著作権法に基づくものです。著作権法では、著作権は著作物を創作した個人に帰属するのが原則です。それに従うと従業員が創作した著作物の著作権は、創作をした従業員個人となります。
ただしこの原則には例外があり、以下の要件を満たす場合には、契約や勤務規則などに別段の定めがない限り、創作したのは個人ではなく、所属する会社とされます。著作権が会社に帰属することを「職務著作」といいます。
(A)法人その他使用者(法人等)の発意に基づいて創作されたこと
(B)法人などの業務に従事する者が職務上作成したこと
(C)法人などが自己の著作名義の下に公表すること
要件(A)や(B)については、裁判例でも比較的緩く解釈されています。従業員が会社の業務の一環として作成したものであれば、従業員個人名で公表された、あるいはそれが予定されているものでない限りは、職務著作に該当すると考えてよいでしょう。
要件(C)についても、公表の予定がないものは、著作名義が企業となっている前例があると、該当するとされています。
職務著作に該当する成果物の場合は、転職先で使用する行為は著作権侵害となりますので、法的な対抗策が可能となります。
しかし上記のような不正競争防止法の営業秘密に該当するための要件や、職務著作の要件を満たさない場合は、これらの法律に基づく対応はできません。
そのような場合に備えるためには、営業秘密や職務著作に該当しない成果物についての流用を、就業規則で禁止することが有用です。
具体的には、営業秘密に該当するか否かを問わず、在職中に職務上作成した資料データの持ち出しや退職後の使用を禁止する、著作権法上の職務著作の要件を満たさない場合であっても、成果物の著作権は会社に帰属する、といった規定を就業規則に設けることです。
コンテンツ制作会社などを除くと、就業規則にこのような規定を設けている会社は少ないのではないでしょうか。しかし営業秘密や著作権はあらゆる企業の社内資料で、起こりうる問題となるものですから、このような対応はすべての企業に必須と考えておくべきです。こうした就業規則を設けることによって、業務上の成果物が流出した場合、損害賠償を求めることもできます。
業務上の制作物が上記のように、不正競争防止法、著作権法の対象になることがあり、さらにそれでカバーできない部分についても就業規則で流用を禁止していることについて、従業員に周知徹底しておくことが、被害を未然に防ぐためには非常に重要です。
執筆=桑野 雄一郎(studio woofoo)
骨董通り法律事務所 弁護士 早稲田大学法学部卒業後,1993年弁護士登録後,2003年骨董通り法律事務所を設立。弁護士業務の傍ら、法科大学院等において刑事訴訟法及び知的財産法の講義を担当している。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話