
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
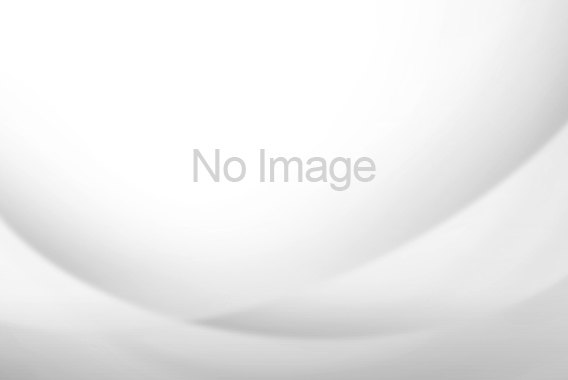
新型コロナウイルスの感染拡大は、我が国の企業活動に深刻な影響を及ぼしており、さまざまな法律問題が生じています。
一例として、商品の製造を受託していた製造業者の方が、新型コロナウイルス感染拡大の影響で原材料を仕入れることができず、商品を製造して納品することができないなどの事態が生じています。
このように、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、契約に従った債務の履行ができない場合、取引先に対して債務不履行責任を負うことになるのでしょうか。
2020年4月1日に施行された改正民法では、債務不履行についても見直されました。しかし、施行日(2020年4月1日)より前に締結された契約に関して生じた債務不履行には、改正前の民法が適用されることになります。新型コロナウイルスの影響によって債務不履行が問題となる契約は、その大半が2020年4月1日より前に締結されたものでしょうから、以下では改正前民法を前提にご説明します。
改正前民法においては、債務不履行を理由として損害賠償請求や解除をするためには、債務不履行について「債務者の帰責事由」が必要だと考えられています。「帰責事由」とは、「故意・過失または信義則上これと同視すべき事由」をいうとされています。とても大ざっぱに説明すると、債務不履行について「債務者に責任がある場合」を意味すると考えてよいでしょう。
つまり、債務者に「帰責事由」が認められない場合、債権者は、債務不履行を理由に損害賠償請求をしたり、契約を解除したりすることはできません。従って、新型コロナウイルスの感染拡大を原因とする債務不履行についても、「債務者の帰責事由」の有無が問題となります。
※なお、契約書に別途の規定がある場合は異なりますので、注意が必要です
また、「帰責事由」と関連するものとして、「不可抗力」という概念があります。これも大ざっぱに説明すると、債務不履行について「誰の責任でもない場合」をいいます。例えば、洪水、台風、地震、津波、地滑り、火災、伝染病、戦争、大規模騒乱など、外部から生じ、かつ相当の注意をしても防止できない事由とされています。
契約書には、債務不履行に関する条項のほかに、不可抗力に関する条項も規定されることが多くあります。帰責事由と不可抗力とは別個の概念ですが、「不可抗力」に該当する場合には「債務者の帰責事由」はない(債務不履行があっても免責される)と考えられています。
従って、今回の新型コロナウイルス感染拡大が「不可抗力」に該当する場合には、契約通りの債務が履行できなくとも、「債務者の帰責事由」はないとして、債務不履行があっても免責されるという主張ができそうです。
しかし、たとえ新型コロナウイルスの影響によって債務を履行できなかったとしても、常に「債務者の帰責事由」はないと判断されるわけではありません。これは、契約書に不可抗力事由として、「疫病・感染病」などの条項がある場合でも同様です。
それでは、どのような場合に、不可抗力に当たる・債務者の帰責事由はないと判断されるのでしょうか。以下では、裁判例を参考に検討していきます。
それでは、新型コロナウイルスによる影響を原因として債務不履行をした債務者は、どのような場合に免責されるのでしょうか。
例えば、業者が商品を製造するに当たり、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により原材料の調達が遅れ、それによって商品の納入が遅滞したとします。一般的に、製造業者は、(商品の種類や取引規模・頻度などにもよりますが)特定の調達先からの原材料の調達が滞っても対応できるよう、複数の調達先を確保しておくことが望まれます。
しかしながら、今回の新型コロナウイルスの感染拡大のように、世界的に影響が広がっている事態においては、複数の調達先を用意するなどの合理的な措置を事前に講じていても、納期に納品することは不可能……といったことが十分あり得ます。このような場合は、不可抗力に当たる(債務者である製造業者に帰責事由はない)として、債務不履行責任を負わないという判断も十分考えられるでしょう。
ただし、裁判例からすると、今回の新型コロナウイルス感染拡大のような状況下においても、債務不履行を避けるために、債務者として一定の措置を講じる必要はある点に注意が必要です。講じるべき措置の内容・程度については、以下の裁判例が参考になります。
裁判例1
(債務不履行責任の否定例:新潟地裁長岡支部判平成12・3・30判タ1044・120)
スキーウェアの製造業者(注文者)がスキーウェアの材料を発注したところ、折からのナイロンブームの影響で、スキーウェアの材料の納品が遅れたという事案です。注文者はスキーウェアの材料の供給業者(受注者)に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求をしました。
結論として、ナイロンブームは不可抗力であり、受注者は善管注意義務を尽くして納品したなどとして、損害賠償請求は棄却されました。
この裁判例では、受注者は、注文者と頻繁に連絡を取り、下請け先を変更したり、自費で検査機関に持ち込むなどしたりして、納期の遅れを取り戻すための努力をしていたことが、債務者(受注者)にとって有利な事情として考慮されています。
裁判例2
(債務不履行責任の肯定例:東京地判平成28・4・7判例秘書L071311032)
建物建築工事の請負契約において、東日本大震災の影響により外壁タイルの納期が遅れ、請負業者が納期までに建物を完成させて引き渡さなかったという事案です。注文者は請負業者に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求をしました。結論として、請負業者は当初予定されていたタイル業者以外の業者を選定するなどして工事を進めることができたのに、これを怠ったなどとして、損害賠償請求は一部認容されました。
この裁判例では、債務者(請負業者)において注文者の意向を確認して代替的手段を講じることができたのにそれをしなかったことが、債務者にとって不利な事情として考慮されています。
裁判例2は、東日本大震災の影響下で起きた材料調達の遅れについて判示したものですが、債務者として尽くすべき努力を尽くさなかったことが考慮され、債務不履行責任が認められています。東日本大震災のような未曽有の災害が影響した場合でも、常に免責されるわけではないことがお分かりいただけるかと思います。
以上の裁判例からも明らかな通り、新型コロナウイルスの感染拡大によって材料が調達できず、納品が遅滞したとしても、一律に債務不履行責任を免れることができるわけではありません。代替手段を講じるなど、納期の遅れを取り戻すための努力をしていたかどうかなどの個別事情によって、判断が変わってくる可能性があります。
新型コロナウイルスの影響は長引くことが想定され、今後もさまざまな経済活動に重大な支障を及ぼすことが見込まれます。
そのため、今後に備え、契約書の内容を確認し、場合によっては改定の交渉を行うと共に、代替手段の確保などの対応を取るべきでしょう。また、仮に契約書通りの債務が履行できなくなった(または近いうちに債務が履行できないことが見込まれる)としても、取引先との信頼関係がなるべく壊れないよう、積極的にコミュニケーションを取り続けることが重要であるといえるでしょう。
執筆=福原 竜一
虎ノ門カレッジ法律事務所 弁護士 2009年弁護士登録。企業法務及び相続法務を中心業務とする。主な著作として、「実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパクトガイド」(編著:2019年10月:ぎょうせい)がある。2019年8月よりWEBサイト「弁護士による食品・飲食業界のための法律相談」を開設し、食に関わる企業の支援に力を入れている。https://food-houmu.jp/
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話