
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
2018年6月に成立した「働き方改革関連法」が、2019年4月から順次施行されています。中でも、絶対に取り組まなければならないのが、「年5日以上の有給休暇取得義務付け」。企業規模に関係なく適用され、違反すれば罰則があるからです。
今回は、その内容と順守するにはどうすればいいのか、厚生労働省のモデル就業規則 の規定例や、その他の資料を参考に解説します(以下の内容は、厚生労働省等の「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」 (以下:わかりやすい解説)を基にしています。詳細は、同解説をご参照ください)。
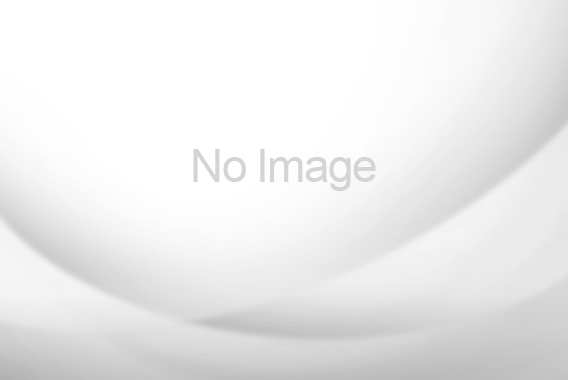 労働基準法(以下:「労基法」)では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇(以下:年休)を与えることを規定しています(労基法第39条)。
労働基準法(以下:「労基法」)では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇(以下:年休)を与えることを規定しています(労基法第39条)。
しかし、与えられた年休を取得するかは、基本的に労働者各自に委ねられています。そのため、これまでは職場への配慮やためらいなどの理由から取得率は低調であり、年休の取得促進が課題となっていました。政府は2020年までに年休取得率を70%にする目標を掲げていますが、2017年の取得率は51.1%にすぎず、実現は困難な状況でした。
そこで、打開策として労働基準法を改正し、2019年4月から、使用者に「年5日以上の有給休暇取得義務付け」を課すことにしたのです。具体的には、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季(季節と具体的時期)を指定して取得させることが必要になりました(労基法第39条第7項)。
「年5日以上の有給休暇取得義務付け」は、「休暇」に関する事項なので、まず、就業規則に規定しなければなりません(労基法第89条1号)。厚生労働省のモデル就業規則では、次のように定められていますから、参考にしてください。
「第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。」(第22条第3項)
ポイントは3つあります。第1に、使用者は、年10日以上の年休が付与される労働者に対して、そのうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6カ月経過日から1年ごとに区分した期間の初日)から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて年休を与えなければなりません。制度の最も基本的な内容です。
第2に、使用者が時季を定めるに当たっては、労働者の意見を聴取することを要し、当該労働者の意見を尊重するよう努めなければなりません。つまり、使用者が労働者の意向を無視して一方的に年休取得日を指定することは許されません。使用者が労働者に取得時季の意見を聴取する方法は、面談、年休取得計画表、メール、システムを利用した意見聴取など、任意の方法で構いません。
第3に、労働者自らの請求または労使協定による計画的付与により年休を取得した日数分については、使用者が時季を定めて年休を与えることを要しません。つまり、使用者による時季指定、労働者自らの請求・取得、計画年休のいずれかによって労働者に年5日以上の年休を取得させれば足ります。また、これらのいずれかの方法で取得させた年休の合計が5日に達した時点で、使用者から時季指定をする必要はなくなり、また、することもできなくなります。
「年5日以上の有給休暇取得義務付け」を実施するに当たって、使用者は、労働者ごとに時季(年休を取得した日付)、年休の取得日数および基準日を明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、それを、当該年休を与えた期間中および当該期間の満了後3年間保存しなければなりません(労基法施行規則第24条の7)。
これは、労働者ごとに年休の取得状況を把握し、年休の付与義務に違反することのないよう適切に管理するためです。年次有給休暇管理簿は、必ずしも独立した書類である必要はなく、労働者名簿または賃金台帳と合わせて調製することもできます。つまり、労働者名簿や賃金台帳に、時季、日数および基準日を記載しておく方法もあります。もちろん、システム上で管理することも差し支えありません。
なお、年次有給休暇管理簿のフォーマットについては、山口労働局のウェブサイト、「年次有給休暇を取得できる職場環境を整えましょう~H31.4改正労働基準法対応~」が、分かりやすくお勧めです。このサイトには、関連する他のフォーマットもいくつか掲載されており、実用的です。
最初に述べた通り、使用者が、「年5日以上の有給休暇取得義務付け」に違反した場合、罰則が科されることがあります。
具体的には、使用者が、労働者に年5日の有給を取得させなかった場合は、労基法第39条第7項違反となり、30万円の罰金が科されます(労基法第120条)。
また、「年5日以上の有給休暇取得義務付け」に関する規定を就業規則に記載していない場合は、労基法第89条違反となり、 30万円の罰金が科されます(労基法第120条)。さらに、労働者の請求する時季に所定の年休を与えなかった場合は、労基法第39条(第7項を除く)違反となり、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます(労基法第119条)。
30万円という罰金はたいしたことがないように思えるかもしれません。しかし、罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われることになります。対象者が多い場合には莫大になりかねないので、甘く見るわけにはいきません。
違反した場合、罰則が科される場合がありますから、使用者にとって、労働者の年休を管理しやすくすることは重要です。例えば、労働者ごとに入社日が異なる職場などでは、基準日が労働者ごとに異なるため、誰がいつまでに年休を5日取得しなければならないのかを把握することは容易ではありません。
これについて、「わかりやすい解説」では、人員規模の大きな事業場や新卒一括採用をしている事業場では、基準日を年始や年度始めに統一することが、また、中途採用を行っている事業場や比較的小規模な事業場では、基準日を月初などに統一することが、それぞれ推奨されています。
さらに、労働者が年5日の有給を確実に取得できるようにするため、「わかりやすい解説」では、以下の方法が推奨されています。
| 方法1: | 基準日に、職場で年次有給休暇取得計画表を作成し、労働者ごとの休暇取得予定を明示する。 |
| 方法2: | 基準日から一定期間が経過したタイミング(半年後など)で年休の請求・取得日数が5日未満となっている労働者に対して、使用者から時季指定をする。(ただし、この場合、使用者が労働者の意向を無視して一方的に年休取得日を指定することが許されません) |
| 方法3: | 年休の計画的付与制度(計画年休、労基法第39条第6項)を活用する(計画年休とは、簡単に言えば、労使協定によって年休日を特定して、個々の労働者を拘束するものです。計画年休の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります)。 |
以上のように、「年5日以上の有給休暇取得義務付け」の導入には、就業規則への規定や年次有給休暇管理簿の作成・保存といった準備をした上で、これを実現するための工夫も必要です。すでに手を付けている企業も多いと思いますが、改めて進行状況を確認してください。
執筆=上野 真裕
中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。平成15年弁護士登録。小宮法律事務所(平成15年~平成19年)を経て、現在に至る。令和2年中小企業診断士登録。主な著作として、「退職金の減額・廃止をめぐって」「年金の減額・廃止をめぐって」(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話