
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
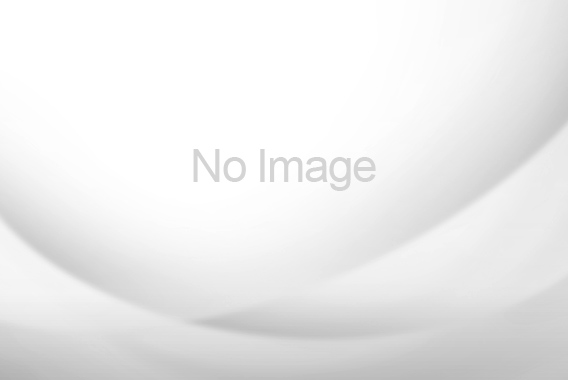
2023年4月1日より、企業は従業員に支払う給与などの賃金について、PayPay(ペイペイ)、LINEペイなどスマートフォン決済サービスなどを提供する資金移動業者の口座へのデジタル払いが認められます。
これは、労働基準法(以下:労基法)上の賃金支払い諸原則のうち通貨払いの原則に新たな例外を認めるものであり、その実施にあたっては、いくつかの要件があります。そこで今回は、企業が賃金のデジタル払いを実施するための要件やポイントについて解説します。
賃金は、「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とされています(労基法24条1項)。このうち、「通貨で」の部分を通貨払いの原則といいます。労基法が通貨払いの原則を採用しているのは、賃金は労働の対価として労働者の生活の糧となることから、労働者に確実に支給されるように、価格が不明瞭で換価にも不便な現物給付を禁止するためです。
ただし、同条項書において、「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」には、通貨以外のものでの支払いが認められています。そして、これを受けて、労働者の同意がある場合には、賃金の銀行口座などへの振り込みが認められています(労基法施行規則第7条の2)。これにより、近年は現金手渡しでなく、銀行振込が多くなっているのはご存じの通りです。
賃金のデジタル払いは、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様が進む中、資金移動業者の口座への資金移動を給与などの受け取りに活用するニーズが一定程度見られることを踏まえ、この例外の一つとして、新たに認められたものです(改正労基法施行規則7条の2、第3号)。
企業が賃金のデジタル払いを実施するには条件があります。まず、従業員が引き続き銀行口座などへの振り込みを選択できるようにすること。そして、次に掲げる①から⑤の事項について説明した上で、当該従業員の同意を得なければなりません。
こうした条件を設けているのは、賃金は労働者の生活の糧となることから、労働者に確実に支給されるようにしなければならないとする通貨払い原則の趣旨から導かれるものといえます(なお、②のみは、資金移動業者の口座の資金は「預金」ではなく、「送金」や「決済」を目的としていることに基づく制約です)。
① 資金移動業者が破産などにより債務の履行が困難になったときは、企業が従業員に対して負担する債務(給与など)を速やかに保証する仕組みを有していること。
② 資金移動業者の口座残高上限額を100万円以下とし、100万円を超えた場合は、速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。
③ 企業が従業員に対して負担する債務(給与など)について、従業員の責めに帰すことができない事由によって口座の資金が不正に出金され、それにより従業員に損失が生じたときは、当該損失を補償する仕組みを有していること。
④ 資金移動業者口座の口座残高が最後に変動した日から少なくとも10年間は口座残高が有効であること。
⑤ 現金自動支払機(ATM)の利用などによって、資金移動業者口座の資金を1円単位で払い出すことができ、かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担せず払い出すことができること。また、資金移動業者口座への資金移動が1円単位でできること。
なお、企業が利用する資金移動業者は、厚生労働大臣の指定を受ける必要があり(指定資金移動業者)、指定の要件として上記①~⑤のほか、次に掲げる⑥、⑦を満たす必要があります。
⑥ 賃金の支払いに関する業務の実施および財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有していること。
⑦ ①~⑥のほか、賃金の支払いに関する業務を適正かつ確実に行える技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
以下では、企業が賃金のデジタル払いを実施する際の注意ポイントをいくつか挙げておきます(1~4は、厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」「3. よくあるご質問への回答(労働者、使用者向け)」より)。
1.賃金のデジタル払いは、賃金の支払方法に関する選択肢の一つであり、従業員が希望しない場合は選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座などで賃金を受け取ることができます。企業は、希望しない従業員への強制は許されません。従業員は、賃金の一部をデジタル払いで受け取り、残りを銀行口座などで受け取ることも可能です。
2.賃金のデジタル払いにおいて、現金化できないポイントや仮想通貨での支払いは認められません。
3.賃金のデジタル払いが可能となるには、以下の段階を経る必要があります。
(1)資金移動業者による厚生労働大臣への指定申請(2023年4月1日より)
(2)厚生労働大臣による審査・指定(審査には、数カ月かかると見込まれています)
(3)各事業場における、利用する指定資金移動業者などを記載した労使協定の締結(これは、法や規則で要請されておらず、厚労省が“推奨”している手続きといえます)
(4)企業の従業員に対する賃金のデジタル払いに関する留意事項の説明、従業員による同意書の提出
4.上記3の(4)の同意書は、厚生労働省のWebサイトにフォーマットが掲載されています。企業による説明事項や従業員の同意を得るにあたり必要な事項について網羅されているので、積極的な活用が望まれます。
5.以上のほか、賃金の支払い方法は、就業規則の必要的記載事項であり(労基法89条2号)、労働契約締結の際における労働条件の明示義務の対象であることから(労基法15条1項)、これらへの記載が必要となります。
今後、賃金のデジタル払いがどのようにして、どの程度普及していくのか予想することは困難です。とはいえ、中小企業の生産性向上は、今日のわが国の最重要課題であり、生産性向上のためのDX化の推進は、すべての中小企業において避けては通れません。
そうした観点から、スマートフォン決済サービスが広く社会に浸透している現在において、賃金のデジタル払いの導入は、比較的取り組みやすいDX化の一つともいえます。その意味で、生産性向上のために、X化の一つの取り組みとして、賃金のデジタル払いを積極的に導入する意義は大きいのではないでしょうか。
執筆=上野 真裕
中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。平成15年弁護士登録。小宮法律事務所(平成15年~平成19年)を経て、現在に至る。令和2年中小企業診断士登録。主な著作として、「退職金の減額・廃止をめぐって」「年金の減額・廃止をめぐって」(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話