
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
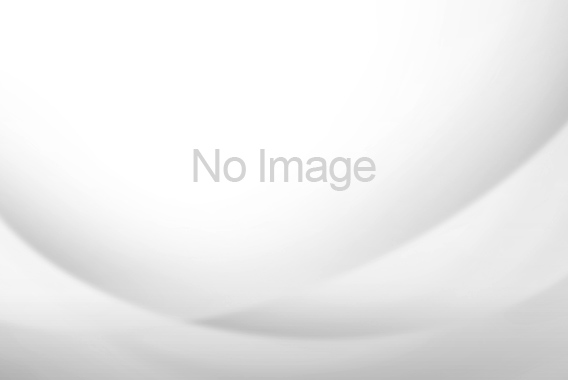
新型コロナウイルスの感染拡大により事業所の閉鎖・縮小を検討される事業者の方も少なくないかと思います。事業用建物の賃貸借契約が終了するときによく問題となるのが、「原状回復義務」です。賃借人の費用負担で原状回復をすべき範囲はどの程度なのでしょうか。本記事は、原状回復義務の概要や注意点について説明するものです。まずは基本的な考え方から解説していきます。
原状回復義務とは、民法上、賃借物を受け取った後に生じた損傷を、賃貸借の終了時に、原状に復する義務と定められています。もっとも、通常損耗(通常の使用・収益によって生じた損耗をいい、経年変化(建物・設備などの自然的な劣化・損耗など)を含みます)は、原状回復義務の対象外です。また、その損傷が賃借人の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、賃借人は原状回復義務を負いません。
つまり、「原状」回復といっても、借りた当時の状態(原状)に戻す必要が常にあるわけではありません。本記事では、原状回復義務のポイントを下記3つに整理した上で、それぞれについて説明します。
・通常損耗については賃貸人が負担し、それを超える損耗(特別損耗)については賃借人が負担する。
・特別損耗としての賃借人の負担は、合理的な範囲に限られる。
・通常損耗について賃借人が負担する特約を結ぶことができる。しかし、このような特約が有効と認められるためには一定の条件を満たす必要がある。
それぞれ具体的にどのようなことなのか、次に詳しく見ていきます。
賃貸借契約とは、賃借人が建物を一定期間使用する代わりに賃料を支払う契約であることから、通常損耗に対する修繕費用はあらかじめ賃料に含まれていると考えられています。そのため、上記の通り通常損耗は、賃借人の負担ではないが(賃貸人負担)、通常損耗を超える損耗(特別損耗)は、賃借人の負担とすることが原則です。
具体的には、家具の設置による床・カーペットのへこみ・設置跡や、壁に開いた画びょう・ピンの穴で下地ボードの張り替えまでは不要なものなどは、通常損耗として、賃貸人が負担すべきであると考えられています。
他方、賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ・染みや、壁に開いたくぎ・ネジの穴で下地ボードの張り替えまで必要なものなどは、特別損耗として、賃借人が負担すべきであると考えられています。
上記の通り、通常損耗を超える特別損耗については賃借人負担というのが原則です。しかし、その賃借人が負担すべき修繕の部位と費用負担の割合は、原則として、合理性が認められる範囲に限られます。
まず、原状回復義務による修繕をすべき部位は、必要最小限の範囲に限られます。例えば、壁の1面についた染みを除去するため壁紙の張り替えをする場合、染みの付いていない他の面の壁紙まで張り替える必要は基本的にないだろうということです。
また、賃借人が特別損耗を理由とする修繕工事を行うに当たり、通常損耗に係る部分の工事が含まれる場合もあります。このような場合、修繕費用のうち通常損耗に相当する分は賃貸人が負担すべきであると考えられています。
ここまでが原状回復義務の原則です。しかし、当事者が合意して特約を結ぶことで、通常損耗についても賃借人に原状回復義務を負わせることができます。そのため、どの契約でも上記の原則の通りとは限りません。
本来、契約(特約も含まれます)は、賃貸人と賃借人の意思表示の合致さえあれば成立します。しかし、上記の原則よりも賃借人の負担を加重する特約(通常損耗補修特約といいます)については、最高裁判例により、意思表示の合致に加えて、合意の明確性もなければ有効にならないとされています。最高裁は、以下の2つのいずれかに当たるような場合には、合意の明確性が認められるとしています。
①賃貸借契約書の条項自体に、賃借人が修繕費用を負担することになる通常損耗の範囲が明記されている場合
②(賃貸借契約書に明記されていないが)賃借人が負担することになる通常損耗の範囲を賃貸人が口頭で説明し、賃借人がそれを明確に認識して、両者の合意内容としたという状況が認められる場合
ただ、こうした点をクリアしたとしても、居住用建物の賃貸借など、一般の個人消費者(事業者でない賃借人)との契約では、消費者契約法との関係で、その特約は無効と判断されてしまう可能性があります。
具体的には、任意規定から導かれる上記の原則などに比べて、消費者に対して権利制限・義務加重となる場合で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するときは、その特約は無効とされてしまいます。これは、賃貸人(不動産会社や大家)と賃借人(個人消費者)との間には、交渉力や情報に大きな格差があるため、過度の不均衡を是正すべきであると考えられているためです。例えば、賃貸人が賃借人に通知した場合には当然に原状回復義務が発生するといった特約は消費者契約法10条に違反して無効と判断した裁判例があります。
他方、事業用建物の賃貸借など、事業者間の契約については、公序良俗に反するなどとされない限り、特約は有効です。消費者契約法は消費者との間の契約についてのみ適用されるものなので、事業者間の契約では問題になりません。したがって、事業用建物の賃貸借契約においては、原状回復義務の内容として、「既存の床板や天井パネルなどについても、すべて賃借人の負担で新しいものに取り換える」など、特別損耗だけでなく通常損耗・経年劣化の分も賃借人の負担とする特約を定めていても、合意の明確性が認められれば原則として有効になります。
事業用建物の原状回復義務については、上記の通常損耗補修特約以外にも、さまざまな特約がありえます。例えば、以下のようなものです。
・原状回復工事において工事業者を賃貸人指定業者とする特約
・原状回復工事は賃貸人が行い、工事費用を敷金から差し引いて清算する特約
・原状回復義務を免除する特約(備え付けた造作について残置することを認める特約)
・原状回復義務の内容としてスケルトン状態にして明け渡す旨の特約
・内装設備をそのままにして退去する、いわゆる居抜きに関する特約
契約締結時点において、どのような特約が定められているのか、十分に注意して検討すべきでしょう。不安があれば契約締結前に、専門家である弁護士などにチェックしてもらうことが望ましいといえます。
原状回復義務については、国交省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が公表されています。これは民間賃貸住宅の賃貸借を念頭に置いたものですが、事業用賃貸借についても妥当すると判断した裁判例もあり、原状回復義務の検討に当たり重要な指標になるものです。国土交通省のウェブサイトに掲載されていますので、併せてご覧ください。
執筆=福原 竜一
虎ノ門カレッジ法律事務所 弁護士 2009年弁護士登録。企業法務及び相続法務を中心業務とする。主な著作として、「実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパクトガイド」(編著:2019年10月:ぎょうせい)がある。2019年8月よりWEBサイト「弁護士による食品・飲食業界のための法律相談」を開設し、食に関わる企業の支援に力を入れている。https://food-houmu.jp/
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話