
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
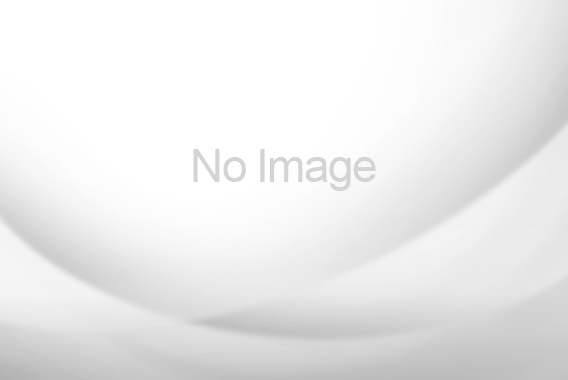
前編では、フリーランス新法の対象となる当事者・取引、フリーランスとの取引を適正化するための規制について解説しました。後編では、フリーランスの就業環境の整備に関する規定と、発注事業者が本法に違反した場合への対応などについて解説します。また、本法に類似する法律である下請法(下請代金支払遅延等防止法)との関係についても触れておきます。
前編で述べたとおり、本法は、1人の「個人」であるフリーランスと「組織」である発注事業者との間に格差が生じやすいという背景から制定されました。その観点から、本法ではフリーランスが安心して働けるよう、就業環境の整備について以下のような規定を置いています。
第1に、発注事業者が広告等によって募集情報を提供するときは、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、情報は、正確かつ最新の内容に保たなければなりません(12条)。
これは、広告等に掲載された募集条件と実際の取引内容が異なり、発注事業者とフリーランスとの間で取引条件に関するトラブルが生じたり、フリーランスがより希望に沿った別の取引をする機会を失ったりすることを防ぐための規定です。ここでいう「情報」とは、委託事業者、報酬、業務を行う場所や期間・時期に関するものが想定されています。
第2に、発注事業者は、継続的業務委託において、フリーランスからの申し出に応じて、フリーランスが育児介護等と両立して業務委託に係る業務を行えるよう必要な配慮をしなければなりません(13条1項)。
これは、フリーランスの多様な希望や働き方に応じて発注事業者が柔軟に配慮を行い、フリーランスが育児介護等と両立しながら、その有する能力を発揮しつつ業務を継続できる環境を整備することを目的とした規定です。「配慮」の内容としては、「妊娠検診の受診のための時間を確保し、就業時間を短縮する」「育児や介護等と両立可能な就業日・時間とし、オンラインで業務を行うことができるようにする」などが考えられます。
第3に、発注事業者は、ハラスメント行為によりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません(14条1項)。また、発注事業者は、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として、業務委託契約の解除その他の不利益な取り扱いをしてはなりません(14条2項)。
セクシュアルハラスメント、妊娠・出産に関するハラスメント、パワーハラスメントといったハラスメント行為は、フリーランスの尊厳や人格を傷つけ、これによりフリーランスの就業環境の悪化、心身の不調、事業活動の中断や撤退を生じさせるので、これらを防止するために設けられた規定です。
「相談対応のための体制整備その他の必要な措置」としては、雇用関係にある従業員のハラスメント対策の場合と同様、①方針の明確化、従業員に対する周知・啓発(文書配布、研修実施等)、②相談担当者の選任、外部機関への相談対応の委託等、③ハラスメントが発生した場合の迅速かつ適切な対応(事実関係の把握、被害者に対する配慮措置等)などが想定されます。
第4に、発注事業者は、継続的業務委託を中途解約する場合や契約期間満了後に更新しない場合には、原則として、中途解約日などの30日前までにフリーランスに対して予告しなければなりません(16条1項)。また、その期間中にフリーランスから契約解除の理由について開示を求められた場合には、原則として、遅滞なく理由を開示しなければなりません(16条2項)。
本条は、一定期間継続する取引において、発注事業者からフリーランスに対し、契約の中途解約や不更新についてあらかじめ知らせ、フリーランスが次の取引に円滑に移行できるようにすることを目的とした規定です。
発注事業者の本法への違反が疑われる場合や、その他の発注事業者・フリーランス間の業務委託取引上のトラブル一般について、フリーランスは、弁護士にワンストップで相談できる「フリーランス・トラブル110番」という窓口に相談し、アドバイスを受けられます。フリーランス・トラブル110番は、厚生労働省から第二東京弁護士会が受託して運営しています。料金は無料で匿名でも受け付けてもらえるので、相談しやすいと思います。
法違反が疑われるケースの相談では、必要に応じて相談窓口で法所管省庁(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)への申告についての案内も受けられます(なお、フリーランス・トラブル110番を経由せずに、直接法所管省庁の窓口に申告することもできます)。
フリーランスから発注事業者による法違反の事実が申告されたときは(6条1項、17条1項)、法所管省庁は必要な調査を行います。違反の事実が認められた場合、公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣は発注事業者に対し違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令といった履行確保措置を取ることができます(6条2項、7条~9条、11条、17条2項、18条~20条、22条)。
発注事業者がそれに従わない場合(命令違反、検査拒否など)、50万円以下の罰金に処せられます(24条)。これは法人両罰規定があり、法人の代表者が罰せられる場合には、法人も同様に罰せられます(25条)。
最後に、本法に類似する法律である下請法(下請代金支払遅延等防止法)との関係について、簡単に触れておきます。
下請法も本法と同様、下請事業者保護のために親事業者に対し、書面の交付などの義務を課し(同法3条)、受領拒否などの禁止事項(同法4条)について定めています。そのため、本法との関係が問題となりますが、両者は基本的に次の点で異なります。
第1に、下請法の適用のある親事業者は資本金1000万円超であるのに対し(同法2条7項)、本法は、「個人」であるフリーランス保護の観点から、発注事業者が資本金1000万円以下であっても適用されます。
第2に、本法では、1人の「個人」であるフリーランスが安心して働けるよう、本稿で解説した各種の就業環境の整備に関する規定が置かれていますが(12条以下)、下請法にはこのような規定はありません。
このように、両者は義務を負う主体や環境整備に関する規定の有無などの点で異なります。なお、両者の適用が競合する場合も考えられますが(例えば資本金1000万円超の会社がフリーランスに製造委託し、取引内容の明示に違反している場合など)、そのような場合、いずれの法違反を主張することも可能と考えられます。
執筆=上野 真裕
中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。平成15年弁護士登録。小宮法律事務所(平成15年~平成19年)を経て、現在に至る。令和2年中小企業診断士登録。主な著作として、「退職金の減額・廃止をめぐって」「年金の減額・廃止をめぐって」(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話