
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
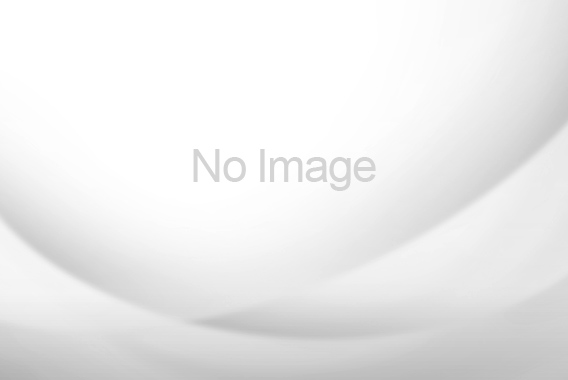 2018年6月13日、成年年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを内容として、民法が一部改正されました。改正の趣旨は、主に18歳・19歳の若者が自身の判断によって人生を選択できる環境を整備する点および18歳・19歳の若者の積極的な社会への参加を促し、社会を活力あるものとする点にあるとされています。
2018年6月13日、成年年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを内容として、民法が一部改正されました。改正の趣旨は、主に18歳・19歳の若者が自身の判断によって人生を選択できる環境を整備する点および18歳・19歳の若者の積極的な社会への参加を促し、社会を活力あるものとする点にあるとされています。
改正によって、2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の若者は、その日に成年に達することになります。そのため、改正の影響をまず受けるのは2002年4月2日から2004年4月1日までに生まれた方です。これに対して、2004年4月2日以降に生まれた方は、それぞれの18歳の誕生日に成年に達することになります。
そもそも、民法の成年年齢には、
(1)単独で有効に契約を締結できる年齢
(2)父母の親権に服さなくなる年齢
の2つの意味があります。
以下では、成年年齢引き下げのビジネス上の影響について、(1)(2)の意味ごとに説明します。
(1)単独で有効に契約を締結できる年齢
民法上、未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人(本稿では便宜上、「親権者」とします)の同意が必要であり、同意を得ないでした法律行為は取り消すことができます(民法5条1項、2項)。
そのため、18歳・19歳の若者との間で携帯電話の購入に関する契約を締結した場合、改正前においては、親権者の同意がないことを理由に契約を取り消される可能性があります。しかし、改正後においては、18歳・19歳の若者は成年者として単独で有効な法律行為ができるようになるため、親権者の同意がないことを理由に契約を取り消されることはなくなります(当然のことながら、詐欺や錯誤など、他の取り消し原因がある場合には、当該取り消し原因に基づく取り消しが認められます)。
(2)父母の親権に服さなくなる年齢
民法上、親権者は未成年の子に対して、居所指定権などを有しています(民法821条等)。なお、居所指定権とは、親権者が子の監護・教育のため、子の居所(生活の中心となる場所)を指定する権利のことをいいます。
成年年齢の引き下げにより、18歳・19歳の若者は、自ら賃貸物件のオーナーと賃貸借契約を締結することなどで、自分の居所を自由に決めることができるようになります。
各種サービスの提供などに当たり定められている約款や利用規約には、「“20歳未満”の利用者は、サービスの利用に当たり法定代理人の同意が必要」などとして、年齢が明記されているものが少なくありません。
しかし、改正法が施行される2022年4月まで、成年年齢は20歳のままですので、現時点で約款等の規定を“18歳未満”を未成年者とする内容に変更することはできません。
そこで、年齢を明記せず、「“未成年”の利用者は、サービスの利用に当たり法定代理人の同意が必要」などと改定することが考えられます。このような内容に改定しておけば、改正法の施行日前後で、慌ただしく規定を改定する必要がなくなります。
民法改正に先んじて、公職選挙法は既に改正されており、選挙権年齢は18歳以上に引き下げられています。
また、これまでは婚姻開始年齢に男女差がありました(男性18歳、女性16歳)。しかし、社会・経済的な成熟度の観点からは男女間に特段の違いはないと考えられるとの理由から、今回の改正により、婚姻開始年齢は統一され、男女共に18歳となります(民法731条)。
さらに、18歳・19歳の若者の保護を念頭に、消費者契約法も一部改正されました。例えば、消費者の社会生活上の経験不足を不当に利用し、不安をあおる告知を行ったり、恋愛感情などを乱用したりするなどして契約させた場合(いわゆるデート商法)、当該消費者は契約の取り消しが可能となります(消費者契約法4条3項3号、4号)。
加えて、特定商取引法についても、18歳・19歳の若者の知識・判断力不足に乗じて行う訪問販売や連鎖販売取引(いわゆるネズミ講)を規制する改正をすべきである旨、提言されています。
なお、民法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられた後も、お酒やタバコに関する年齢制限や、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)の年齢制限は、従来通り20歳のままですので、注意が必要です。
執筆=福原 竜一
虎ノ門カレッジ法律事務所 弁護士 2009年弁護士登録。企業法務及び相続法務を中心業務とする。主な著作として、「実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパクトガイド」(編著:2019年10月:ぎょうせい)がある。2019年8月よりWEBサイト「弁護士による食品・飲食業界のための法律相談」を開設し、食に関わる企業の支援に力を入れている。https://food-houmu.jp/
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話