
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
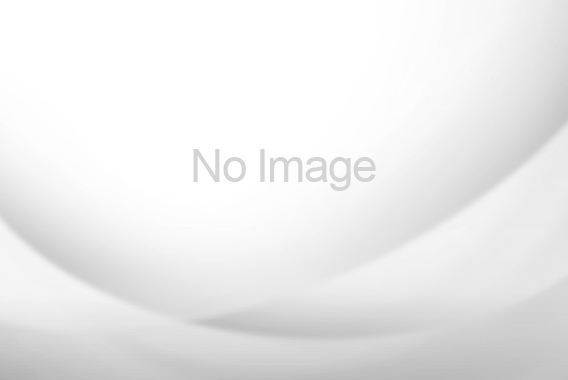
長年デフレ基調が続いた日本経済ですが、近年、ようやくインフレ基調へと変化しつつあります。これにより労務費、原材料費、エネルギーコストなどの上昇が目立ち、企業の取引にも大きな影響を与えています。
こうした経営環境の変化の中で、政府は「成長と分配の好循環」の実現に向けて、中小企業が賃上げの原資を確保できるように、取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できる環境の整備を進めています。
まず、2021年12月27日に閣議で了解を得た「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(以下:転嫁円滑化施策パッケージ)が策定され、政府はこれに基づいてコスト上昇分の適切な転嫁に一体となって対応すると決めています。
さらに2023年11月29日には、内閣官房および公正取引委員会(以下:公取委)が連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針について」(以下:労務費指針)を公表し、原材料費・エネルギーコストと比較して転嫁率(転嫁の要請に対して引き上げられた金額の割合)の低い労務費について、重点的に転嫁を促すとしています。
転嫁円滑化施策パッケージや労務費指針では、転嫁に向けた独占禁止法や下請法の執行強化もうたわれているので、企業はこれらの法律違反および、それに伴うレピュテーションリスク(企業に対するネガティブな評価・評判が広まることによる経営リスク)を避けるための対応が求められます。本連載では、前編と後編の2回に分けて、転嫁円滑化施策パッケージおよび労務費指針について概観するとともに、独占禁止法・下請法違反を問われないための注意点について解説します。
転嫁円滑化施策パッケージは、内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・公正取引委員会の連名で公表されており、次のような取り組みを含んでいます。
1 政府横断的な転嫁対策の枠組みの創設【内閣官房】
2 価格転嫁円滑化に向けた法執行の強化【公取委・中小企業庁・事業所管省庁】
3 労働基準監督機関における対応【厚生労働省】
4 公共調達における労務費等の上昇への対応 【デジタル庁・経済産業省・厚生労働省等】 5 公共工事品質確保法等に基づく対応の強化【国土交通省】
6 景品表示法上の対応【消費者庁】
7 大企業とスタートアップとの取引に関する調査の実施と厳正な対処【公取委】
8 パートナーシップ構築宣言の拡大・実効性強化【中小企業庁・経済産業省等】
9 関係機関の体制強化【公取委・中小企業庁・厚生労働省】
10 今後の課題検討【公取委】
※【】は担当省庁など
このパッケージに含まれる取り組みのうち、公取委が担当する「価格転嫁円滑化に向けた法執行の強化」には、執行を強化する前提として、独占禁止法・下請法の適用や解釈の明確化が盛り込まれています。
このため、公取委は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正、公取委のWebサイトに掲載している「よくある質問コーナー(独占禁止法)」の更新を通じて、下記囲みの①②は、独占禁止法違反(優越的地位の濫用)または下請法違反(買いたたき)として問題となるおそれがあると明確にしています(「よくある質問コーナー(独占禁止法)」Q20参照)。
① 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと
② 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引き上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと
経営者および外部企業との取引担当者は、まず、公取委が示した解釈・考え方について、しっかり理解しておく必要があります。
公取委では、上記囲み①②に該当する行為が疑われる事案に関する実態を把握するため、2022年には緊急調査を、2023年には特別調査を実施し、これらの結果を公表しています。2023年の特別調査の結果、原材料価格やエネルギーコストと比べて、労務費の転嫁が進んでいないと明らかになりました。コスト別の転嫁率を中央値で比較すると、原材料価格(80.0%)・エネルギーコスト(50.0%)に対して、労務費(30.0%)という結果でした。2023年11月の労務費指針は、こうした結果を踏まえて策定・公表されたものです。
公取委は、厳格な法執行に向けて、積極的に端緒情報の収集を行うとともに、違反被疑事件の審査を行い、独占禁止法や下請法上問題となる事案については、対象となる事業者に事業者名の公表を伴う命令、警告、勧告など、これまで以上に厳正な執行をしていくと明らかにしています。
この宣言の通り、公取委は緊急調査・特別調査の結果に基づき、相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据え置きが確認された事業者名を、2022年4月に13社、2024年3月に10社公表しています。また、公取委は2024年3月7日に、自動車の大手メーカーに下請法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたとして、勧告を行ったと公表しています。
デフレ基調が長期化したわが国では、安く仕入れることを優先する取引が定着しているとの指摘があります。しかし、公取委の一連の取り組みからも明らかな通り、今後はこうした取引を一定程度改めていかないと、思わぬ法違反を指摘されかねません。
後編では、労務費の転嫁に係る価格交渉で、発注者・受注者双方の立場から12の行動指針を取りまとめた労務費指針について解説し、法違反を回避するための方策を探ります。
執筆=植松 勉
日比谷T&Y法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)、平成8年弁護士登録。東京弁護士会法制委員会商事法制部会部会長、東京弁護士会会社法部副部長、平成28~30年司法試験・司法試験予備試験考査委員(商法)、令和2年司法試験予備試験考査委員(商法)。主な著書は、『会社役員 法務・税務の原則と例外-令和3年3月施行 改正会社法対応-』(編著、新日本法規出版、令和3年)、『最新 事業承継対策の法務と税務』(共著、日本法令、令和2年)など多数。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話