
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
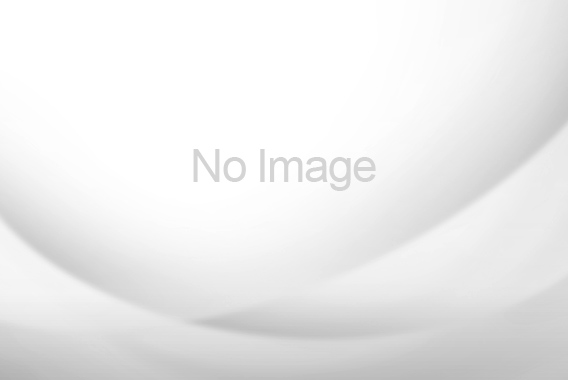 いわゆる「働き方改革関連法」では、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消をめざして、“同一労働同一賃金”が導入されます。施行は、2020年4月1日からとされていますが、中小企業(資本金の額または出資の総額が3億円以下である事業およびその常時使用する労働者の数が300人以下である事業主)では2021年4月1日からとされています。
いわゆる「働き方改革関連法」では、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消をめざして、“同一労働同一賃金”が導入されます。施行は、2020年4月1日からとされていますが、中小企業(資本金の額または出資の総額が3億円以下である事業およびその常時使用する労働者の数が300人以下である事業主)では2021年4月1日からとされています。
ただし、派遣社員に関しては、2020年4月1日、同一労働同一賃金が盛り込まれた改正派遣労働者法が施行されます。こちらは規模による施行時期の違いはありませんから、注意が必要です。来る改正労働者派遣法への対応も含めて、派遣社員を雇う場合の現状の注意点について、説明します。
最初に、改正法施行前の、現時点(2019年10月)において派遣社員の雇用に問題がないか、次の項目をチェックしてください(厚生労働省ウェブサイト「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」参照)。
ア)派遣可能期間が3年を超えていないか。
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則3年が限度です。 派遣先が3年を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合は、派遣先事業所における過半数労働組合(過半数労働組合が存在しない場合、事業所の労働者の過半数を代表する者)の意見を聞く必要があります。
イ)派遣契約の締結に当たって、次の事項を満たしているか。
➀ 派遣労働者への事前面接は行っていない。
➁ 派遣禁止業務への派遣受け入れではない。
➂派遣契約に定めるべき事項はすべて網羅している。
➃ 派遣元事業者が労働者派遣事業の許可を有している。
ウ)派遣就業に当たって、次の事項を満たしているか。
➀ 自社を離職して1年以内の人の受け入れではない。ただし、60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されている。
➁ 社会・労働保険の加入の確認をしている。
➂ 派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成を行っている。
➃ 派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇に関する配慮義務を理解している。
エ)派遣契約の中途解除に関して次の注意事項を満たしているか。
➀ 派遣先は派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ、相当の猶予期間をもって派遣元事業主に派遣契約の解除の申し入れを行うことが必要。
➁ 派遣先は派遣先の関連会社での就業をあっせんするなど、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることが必要。
オ)労働契約申込みみなし制度についての確認
派遣先が偽装請負など一定の違法派遣を受け入れた場合、その時点で派遣先から派遣元事業主との労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約が申し込まれたものと見なされます。派遣労働者が承諾をした時点で労働契約が成立します(派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ知らなかったことに過失がなかったときは除かれます)。
以上に問題がなければ、現時点では適切に派遣社員を活用していることになります。しかし、それで安心してはいられません。次に同一労働同一賃金を盛り込んだ改正労働者派遣法に対応しなくてはなりません。
まずは、労働者全体に関する「同一労働同一賃金」について説明しましょう。同一労働同一賃金の実現をめざして、企業は、➀不合理な待遇差を解消するための規定の整備、および、➁労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化すること)が義務とされています。さらに、➂ 行政はこれらの義務について、履行確保措置および行政ADR(裁判外紛争解決手続)を整備することとされています。
上記➀ の不合理な待遇差を解消するための規定の整備では、短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化すること、有期雇用労働者の均等待遇規定を整備することとされています。
改正労働者派遣法にもほぼ同様の内容が盛り込まれ、派遣元(派遣会社)に順守が義務付けられています。つまり、改正への対応が主に必要なのは派遣元になります。ただし、派遣先もやるべきことがあるので注意しましょう。
改正労働者派遣法では、派遣労働者の待遇について、 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇とする「派遣先均等・均衡方式」か、一定の要件を満たす労使協定による待遇とする「労使協定方式」のいずれかを選択することを派遣元に義務付けています。
派遣元が前者を選択した場合、派遣先は 比較対象となる労働者の待遇情報を派遣元に提供しなくてはなりません。待遇情報は次の通りです。
➀ 比較対象労働者の職務の内容および配置の変更の範囲ならびに雇用形態
➁ 比較対象労働者を選定した理由
➂ 比較対象労働者の待遇に関するそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)
➃ 比較対象労働者の待遇に関するそれぞれの性質および当該待遇を行う目的
➄ 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項
後者を選択した場合でも、待遇の中で、教育訓練と施設利用に関しては派遣先の通常の労働者と均等・均衡を確保する必要があります。そのため派遣先は、派遣元にそれに関する情報を提供しなくてはなりません。
以上のように、法改正に従って派遣元は2つの方式のいずれかを選び、派遣労働者の待遇を決定します。それを前提として、派遣元は派遣先と派遣料金の交渉を実施します。交渉ですから、派遣先は条件に納得がいかなければ、契約を結ぶ必要はありません。ただ、改正派遣労働者法では、派遣先は派遣料金に関して配慮するように求めています(法第26条第11項)。
派遣労働者を活用している企業は、改正法施行の来年4月に向けて、待遇情報の提供や派遣料金の交渉などが必要になることを覚えておいて、適切に対応しましょう。
執筆=渡邊 涼介
光和総合法律事務所 弁護士 2007年弁護士登録。元総務省総合通信基盤局専門職。2023年4月から「プライバシー・サイバーセキュリティと企業法務」を法律のひろば(ぎょうせい)で連載。主な著作として、『データ利活用とプライバシー・個人情報保護〔第2版〕』(青林書院、2023)がある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話