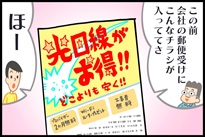
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
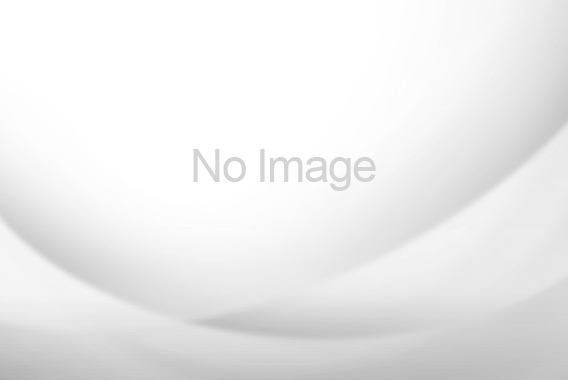
新型コロナウイルスの影響でマスクを着用した生活が長く続いています。多くの人が感染予防に有効であるとされるマスクを着用していますが、ニュースなどではマスクの着用を拒否したことによるトラブルも散見されます。このようなマスクの着用拒否については、どのように対応すればよいのか分からない経営者の方もいるのではないでしょうか。
今回は、マスクの着用拒否に対する対応に加えて、感染予防に関するガイドラインや「まん延防止等重点措置」などの企業が取るべき感染予防対策について見ていきたいと思います。
飲食店などの店舗を運営する企業では、顧客が入店するに当たりマスクの着用を義務付けていることも多いと思われます。では、顧客がマスクの着用を拒否した場合はどのように対応すればよいでしょうか。
この点、法令で特別の定めがある一定の業種を除き、企業がその顧客と契約を締結するかどうかは自由ですし、企業側に自己の管理する建物に立ち入るかどうかを決める管理権もありますので、マスクの着用を拒否する顧客の入店を拒否することは可能であると考えられます。
次に、自社の従業員がマスクの着用を拒否する場合はどのようにしたらよいでしょうか。まず、企業は雇用する労働者に対し、その業務遂行について必要な範囲で業務命令を発することができます。
企業は、労働者が生命身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする「安全配慮義務」を負っていますので、職場での他の従業員への感染拡大を防止するための措置を取る義務があります。このように企業は安全配慮義務を負っているため、労働者にマスクの着用を義務付けたとしても、それは必要かつ相当な範囲の業務命令であると考えられます。
では、労働者が業務命令に従わず、マスクの着用をかたくなに拒否する場合はどのようにすればよいでしょうか。このような場合は、就業規則に基づき、労働者に対する懲戒処分を検討することになります。
ただ、懲戒処分は一定の場合には権利乱用として無効になりますので、労働者がマスク着用を拒否したからといって直ちに懲戒処分をしてよいわけではありません。懲戒処分をするに当たっては、労働者がマスクの着用を拒否する理由に合理性があるかどうか、業務命令に従わない頻度・回数、企業の事業活動に及ぼした影響などのさまざまな事情を検討する必要があります。
企業がきちんとした感染予防対策を怠ったことで、クラスターなどが発生してしまった場合は信用問題に関わりますし、万が一労働者が新型コロナウイルスに感染してしまった場合は安全配慮義務違反を問われる可能性もあります。従って、きちんとした感染予防対策を講じることは企業のリスク管理として重要であるといえるでしょう。
この点、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」などを受けて、各業界団体では、感染予防対策について「業種別ガイドライン」を作成しています。それぞれのガイドラインについては、内閣官房が管轄する新型コロナウイルス感染症対策推進室のホームページで情報がまとめられていますので、自社に関係する業種のガイドラインについてはチェックしておきましょう。こうした業種別のガイドラインを順守して、企業活動に対応した適切な感染予防対策を行うことが重要です。
2021(令和3)年2月に新型インフルエンザ等対策特別措置法などの一部を改正する法律が改正されたことにより、新たに「まん延防止等重点措置」が創設されました。その中では、正当な理由なく都道府県知事の要請に応じない事業者への命令と罰則が規定されました(なお、緊急事態宣言下において出される「緊急事態措置」の内容も見直されました)。
「まん延防止等重点措置」は、緊急事態宣言が発出される前のステージでも集中的に対策を講じられる措置であり、原則として区画や市区町村単位で行われるものです。「まん延防止等重点措置」では、都道府県知事が、事業者に対し、営業時間の短縮を要請できることのほか、従業員に対する検査を受けることの勧奨や正当な理由なくマスクの着用などの感染防止措置を講じない者の入場禁止などを要請できることになります。この要請に事業者が正当な理由なく応じない場合には、都道府県知事は命令をすることができ、この命令にも従わない場合は、事業者は20万円以下の過料に処せられることになります。
なお、マスクの着用などを拒否する者の入場禁止について、例えば入場者が有する疾患などによりマスクの着用が困難な場合や、窒息や熱中症のリスクが高いとされる2歳未満の子どもである場合は「正当な理由」に該当するとされています。
一方で、マスクを着用しない客が連日のように入店しているにもかかわらず、客にマスクの着用や、着用しないときには退店することを促すこともせずに見逃しているような場合には、要請に応じていないと評価され得るとされています。
執筆=近藤 亮
近藤綜合法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属) 平成27年弁護士登録。主な著作として、『会社法実務Q&A』(ぎょうせい、共著)、『少数株主権等の理論と実務』(勁草書房:2019、共著)、『民事執行法及びハーグ条約実施法等改正のポイントと実務への影響』(日本加除出版:2020、共著)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話