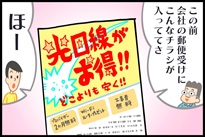
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
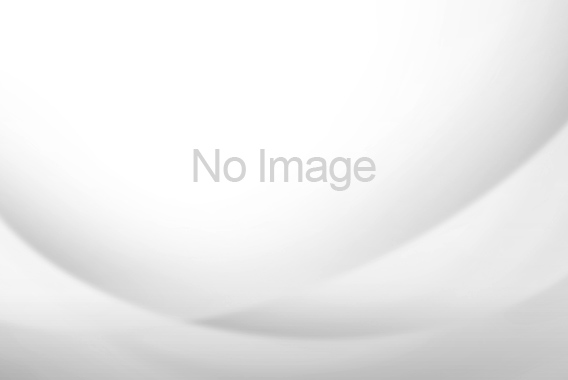
2021年4月に成立・公布された「民法等の一部を改正する法律」(以下:「2021年改正法」)が、2023年4月1日以降順次施行されます。この改正は所有者不明土地問題を契機として、従来の民法や不動産登記法などのルールを見直すものです。
所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しないか、判明しても所在が不明で所有者に連絡がつかないような土地のことです。所有者が死亡しても相続登記がされていないなどの原因で近年増加しており、土地取引・公共事業の停滞や、周辺への悪影響などを生じさせ、大きな問題となっています。
2021年改正法により、所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化が期待されています。改正法が適用される場面は多岐にわたりますが、本コラムでは、不動産関連の相続に関わる事項のポイントを3回に分けて解説します。今回は、不動産の登記に関する改正点のうち、相続への影響が大きい事項を中心に、その概要を説明します。
国土交通省実施の2017年度地籍調査によると、所有者不明土地の割合が全体の約22%に上りました。そのうち、相続登記が未了である土地の割合は約66%、住所変更登記が未了である土地の割合は約34%でした。
このような登記手続きの未了が所有者不明土地発生の主な要因になっているとして、2021年改正法では、不動産登記法を改正し、これまで任意だった相続登記や住所変更登記などが義務付けられるようになりました。なお、所有者不明による弊害は建物についても同様に生じるので、不動産登記法の改正の対象は、土地の登記だけでなく建物の登記にも及びます。
具体的には、相続等による所有権移転登記の申請を義務付ける改正不動産登記法(以下:「改正不登」)76条の2が新設されました(2024年4月1日施行)。相続や特定財産承継遺言、遺贈により不動産を取得した相続人は、自己のために相続などの開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記などの所有権移転登記を申請しなければならないとされました。
加えて、この義務を果たした場合でも、法定相続分に応じた相続登記の申請がされた場合で、後に成立した遺産分割によって申請者が法定相続分を超える所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければならないとされました(改正不登76条の2第2項。2024年4月1日施行)。
この相続登記の義務化に関する規定は、改正不動産登記法76条の2の施行日(2024年4月1日)以前に開始された相続にも遡及的に適用されます。具体的には、施行日より前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合、相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日、または施行日のどちらか遅い日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請する必要があります。
また、遺産分割による追加的義務についても遡及適用があり、施行日の2024年4月1日より前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合、分割の日または施行日のどちらか遅い日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請する必要があります。登記申請義務者が正当な理由なくこの申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます(改正不登164条1項。2024年4月1日施行)。
2021年改正法ではさらに、上述した相続登記申請義務の実効性を確保するため、さまざまな対応策が導入されました。以下では、重要と思われる4つを紹介します。
①相続人申告登記制度の新設
②登記権利者による所有権移転登記の単独申請の可能化
③所有不動産記録証明制度の新設
④登記名義人の死亡情報の符号の新設
まず、①相続人申告登記制度が新設されました(改正不登76条の3。2024年4月1日施行)。相続人による相続登記申請義務の履行を容易にすることを目的とするものです。
相続人申告登記制度は、相続人が、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と自らがその相続人である旨を、申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。登記官は、申出について所要の審査の上、申出をした相続人の氏名・住所などを職権で所有権の登記に付記することになります。
これにより、登記簿を見れば相続人の氏名や住所を容易に確認できるようになります。なお、申出に当たっては、特定の相続人が単独で申出可能であり、法定相続人の範囲および法定相続分の割合の確定も不要となります。具体的には、自らが被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本などを提出すればよいとされており、現行法下の手続きと比較して、相続人の手続的負担が軽減されます。
なお、相続人申告登記がされた場合でも、その申出を行った者が後に成立した遺産分割によって所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければなりません(改正不登76条の3第4項。2024年4月1日施行)。
次に、②登記権利者による所有権移転登記の単独申請も可能になります。具体的には、相続関連の登記手続きを促進する観点から、特定財産承継遺言、相続人に対する遺贈のいずれであるかを問わず、これによる所有権移転登記も登記権利者による単独申請が可能となります(改正不登63条3項。2023年4月1日施行)。
また、③所有不動産記録証明制度が新設されました(改正不登119条の2。2026年4月までに施行)。これは、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくして、相続登記の申請にかかる当事者の手続的負担を軽減するとともに、登記漏れを防止する観点から、被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し証明するというものです。
さらに、④登記官が、住基ネットなどの公的機関から取得した死亡情報に基づき、不動産登記に死亡の事実を符号によって表示する制度も新設されます(改正不登76条の4。2026年4月までに施行)。この制度により、登記を見れば当該不動産の所有権の登記名義人が死亡した事実を確認できます。
今回の改正では、住所などの変更登記も義務付けられています。所有権の登記名義人について登記上の氏名・名称または住所に変更があった場合、当該変更の日から2年以内に当該変更の登記を申請しなければならなくなりました(改正不登76条の5。2026年4月までに施行)。登記申請義務者が正当な理由なくこの申請を怠った場合にも、5万円以下の過料に処せられます(改正不登164条2項。2026年4月までに施行)。
その他、不動産登記の公示機能をより高める観点などから、外国に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先の登記など、さまざまな改正がされています。詳細については、法務省のWEBサイトなどをご参照ください。
以上のとおり、今回は不動産の登記に関する改正点のうち、相続の影響が大きい事項を中心に概要を説明しました。次回は遺産分割に関する改正点について説明します。
執筆=福原 竜一
虎ノ門カレッジ法律事務所 弁護士 2009年弁護士登録。企業法務及び相続法務を中心業務とする。主な著作として、「実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパクトガイド」(編著:2019年10月:ぎょうせい)がある。2019年8月よりWEBサイト「弁護士による食品・飲食業界のための法律相談」を開設し、食に関わる企業の支援に力を入れている。https://food-houmu.jp/
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話