
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
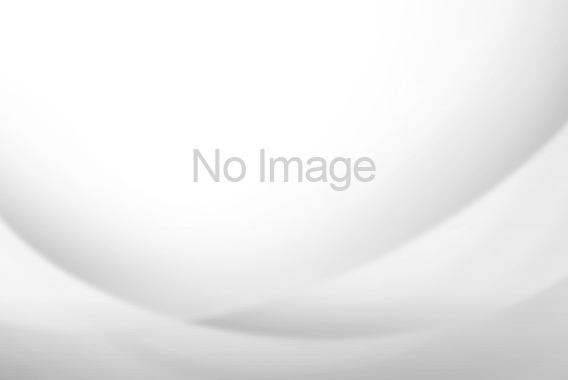
退職者による企業の技術情報や顧客情報などの漏えい事件が後を絶ちません。2021年に入ってからも、大手通信企業の元従業員が企業情報を不正に持ち出していたとして逮捕されました。
企業の技術情報や顧客情報などは、不正競争防止法上の「営業秘密」と認められると、不正な使用に対して差止めを求めたり、刑事罰を科したりすることが可能になり、企業はより強固な保護を受けることができます。他方、今日では、元従業員から営業秘密を不正に取得したとして、元従業員の転職先の企業が訴えられるケースも見受けられます。
転職先が不正を承知で転職元の営業秘密を取得したのであれば、許されないのは当然です。しかし、転職先が意図していないにもかかわらず、転職者が持ち込む情報の中に転職元の営業秘密が含まれていると、転職先は営業秘密の不正取得などを疑われ、法的紛争に巻き込まれてしまうかもしれません。すなわち、企業は、営業秘密の漏えい対策のみならず、「営業秘密の混入リスク(コンタミネーション・リスク)」についても備えておく必要があるのです。
この「営業秘密」の認定について、一連の裁判における判断や行政の指針には、変遷が見受けられるように思われます。本稿では、営業秘密に関する認定の変遷と、混入リスクへの対応について解説します。
企業の技術情報や顧客情報などが、不正競争防止法上の「営業秘密」と認められるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
[1]その情報が秘密として管理されていること(秘密管理性)
[2]その情報が事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
[3]その情報が公然と知られていないこと(非公知性)
(1)裁判所による判断の変遷
このうち、特に裁判で問題となることが多いのは、「秘密管理性」の要件です。以前は、比較的緩やかに秘密管理性を認める裁判例もあったのですが、平成15年頃からは、厳しく判断する裁判例が続きました。すなわち、裁判所は秘密管理性について、比較的高度な管理を求めるようになっていきました。
例えば、大阪高裁平成17年2月17日判決は、高周波電源装置の「図面」について、保管されていたキャビネットには「持ち出しはダメ」と表示されていたことは認定しつつ、そのキャビネットは施錠されていなかったことなどを指摘して秘密管理性を否定し、営業秘密には当たらないとの判断をしています。
しかし、平成19年以降、あまり高度な管理は求めずに、ある情報について、アクセス者が秘密情報と認識できるような措置を取っていれば、秘密管理性を肯定する旨の裁判例が再び現れるようになっています。
大阪地裁平成19年5月24日判決は、水門開閉機用減速機の「部品図」について、無施錠の棚に保管され営業秘密である旨の表示もなかったとしつつも、顧客の求めがあっても当然には交付しない扱いをしていたことなどから、「部品図を秘密とする旨を社内的に認識させる措置をとっていた」として、秘密管理性を肯定し、営業秘密に当たるとの判断をしています。
(2)行政による指針の変遷
経産省の「営業秘密管理指針」も、平成27年の改訂で、「秘密管理性」の説明を改めています。
同指針では秘密管理性について、従来は、〈1〉当該情報へのアクセス制限、〈2〉当該情報にアクセスした者が営業秘密であると認識できるようにされていること(認識可能性)、の2つが判断要素となる旨説明していました。しかし、平成27年の改訂では、〈2〉を重視する立場に改め、〈2〉を満たす場合に十分なアクセス制限がないことを根拠に秘密管理性が否定されることはないと説明するに至っています。
これは、一部の裁判例などで秘密管理性の認定が厳しいとの指摘や、認定の予見可能性を高めるべきとの指摘があったことなどを踏まえて議論された結果によるものです。
このように、裁判所の判断や行政の指針には変遷が見受けられますが、「営業秘密と認定されるか」という問題と「漏えい対策」は、別次元の問題なので注意が必要です。すなわち、保管棚の施錠を含めたアクセス制限などを十分に行っておかないと、企業の営業秘密がいつ漏えいするとも限りません。漏えいしてから当該情報が営業秘密に該当すると主張して法的保護を求めるよりも、そもそも漏えいを防ぐことが先決です。従って、裁判例などの変遷にかかわらず、営業秘密の漏えい対策には、高いレベルで取り組むことが求められます。
さらに、今日においては、営業秘密の漏えい対策のみでは不十分で、転職者などによって持ち込まれる営業秘密の混入リスク(コンタミネーション・リスク)の対策が求められています。すなわち、転職元などの他社の営業秘密を“意図せずに”取得してしまうことで、他社の利益を侵害するのを防がなければなりません。
(A)混入リスク対策の必要性
裁判などで営業秘密と認められるハードルが下がっている傾向が見受けられることについてはすでに解説しました。このようにハードルが下がるということは、転職者などによって持ち込まれた情報についても、営業秘密と認められる範囲が広がることを意味します。その結果、意図しない混入リスクはより高まることとなるのです。
不正競争防止法によれば、営業秘密の不正な開示(例えば、守秘義務に違反した開示)と知りつつ転職者などから開示を受けて営業秘密を取得・使用するなどの行為は、差止めなどの対象とされます。そして、注意すべきは、不正開示とは知らずに開示を受けて情報を取得・使用するなどした場合であっても、その情報が営業秘密に当たり、かつ、不正開示と知らなかったことに「重大な過失」が認められると、やはり差止めなどの対象とされてしまいます。
従って、転職者などを介した営業秘密の混入リスク(意図せぬ侵害リスク)対策は、こうした「重大な過失」が認められないようなものとすることがポイントになります。
(B)混入リスクに対する具体的な対策
では、具体的にはどのような対策が有効でしょうか。転職者を受け入れる場合を念頭において、経産省の「秘密情報の保護ハンドブック」などを参考に、いくつか挙げてみたいと思います。
【1】転職者の契約関係の確認
転職者を受け入れるに当たっては、その転職者が転職元との関係で負っている秘密保持義務などの有無、その具体的内容について、確認することが重要です。転職者が転職元に秘密保持の誓約書を差し入れているようなケースでは、その誓約書のコピーなどで確認します。
【2】転職者採用時における誓約書の取得
転職者の採用時に、「転職元などの第三者の秘密情報を含んだ媒体を一切持ち出していないこと」、「秘密保持義務に違反した情報の開示をしないこと」などにつき、書面で誓約してもらうことが考えられます。
【3】採用後の管理
転職者の従事する業務内容を定期的に確認したり、転職者の私物のUSBメモリなどを業務で使用することを禁じたりすることなどが考えられます。
混入リスクは、転職者を受け入れる場合のほかにも、例えば他社との共同研究開発・他社からの受託研究開発、日常の委託契約や請負契約に基づく取引、外部の研究者などによる技術情報・営業情報の売り込みなどでも生じることが考えられます。企業は、自社がどのような場合に他社の秘密情報を取得する可能性があるか、まずはこうした取得機会を全社的に洗い出し、それぞれの機会ごとに対策を講じるとよいでしょう。
執筆=植松 勉
日比谷T&Y法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)、平成8年弁護士登録。東京弁護士会法制委員会商事法制部会部会長、東京弁護士会会社法部副部長、平成28~30年司法試験・司法試験予備試験考査委員(商法)、令和2年司法試験予備試験考査委員(商法)。主な著書は、『会社役員 法務・税務の原則と例外-令和3年3月施行 改正会社法対応-』(編著、新日本法規出版、令和3年)、『最新 事業承継対策の法務と税務』(共著、日本法令、令和2年)など多数。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話