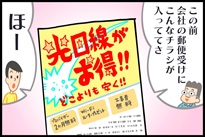
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線

消費者取引においては、消費者と事業者との間に情報や交渉力の格差があるため、消費者が意図せず契約を締結してしまうなど、トラブルに発展する場合も少なくありません。消費者契約法(以下「法」といいます)には、こうしたトラブルから消費者の利益を保護する目的があります。
超高齢社会化やオンライン取引の普及といった社会経済情勢の変化に伴い、規制のあり方を見直す必要が生じました。2022年5月25日には、「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。この法律は、消費者契約法と消費者裁判手続特例法の改正を、その内容とするものです。
今回は、2023年6月1日に施行される改正消費者契約法(以下「改正法」といいます)の概要を説明していきます。主な改正点は、以下の4点です。
① 事業者の努力義務の拡充
② 違約金等に関する説明の努力義務
③ 免責範囲が不明確な条項の無効
④ 契約の取消権に係る類型の追加
これらの改正点について、それぞれ詳しく見ていきます。まずは 、改正点①「事業者の努力義務の拡充」です。
改正法は、消費者と事業者間の情報や交渉力の格差に配慮するため事業者に課されていた努力義務を、以下のとおり拡充しました。
(1)契約内容に関する情報提供(改正法3条1項2号)
〔改正のポイント〕
事業者が、消費者の「年齢」や「心身の状態」を知ることができた場合には、消費者の知識及び経験のみならず、それらの事情も考慮した上で、消費者が契約内容について理解を深めることができるよう情報提供する努力義務を負う
改正法では、事業者が勧誘に際して考慮すべき消費者の事情として、「消費者の知識及び経験」に加えて、消費者の「年齢」「心身の状態」が規定されました。事業者は、これらの事情について、積極的な調査をしなければならないわけではありません。ただ、知ることができた事情については、それらを総合的に考慮して、必要な情報を提供するよう努める必要があります。
(2)定型約款の表示請求権に関する情報提供(改正法3条1項3号)
〔改正のポイント〕
定型約款表示請求権の行使を可能とするための情報を提供する努力義務を負う
不特定多数の消費者を相手方とする取引においては、契約内容が予め画一的に定められた定型約款を用いるときがあります。この場合、消費者は、事業者に対し契約内容を確認するため、定型約款の内容を表示するよう請求することが原則として可能です(民法548条の3第1項本文)。
しかし、消費者としては、表示請求権の存在自体を知らない場合も多いと考えられます。そこで改正法は事業者に対して、消費者が定型約款表示請求権を行使するために必要な情報を提供するよう努めなければならない旨、規定しました。ただし、事業者が定型約款の内容を容易に知りうる状態にしている場合には、このような情報を提供する必要性はないといえますので、事業者はかかる努力義務を負わないとされています。
(3)解除権の行使に関する情報提供(改正法3条1項4号)
〔改正のポイント〕
消費者の要請に応じて、解除権を行使するために必要な情報を提供する努力義務を負う
任意解除権の存在や行使方法が分かりにくいと、結果として消費者による任意解除権の行使を妨げる結果となってしまう場合があります。
契約の任意解除権に係る事項については、改正法3条1項2号によって、勧誘時の情報提供努力義務の対象となっていますが、係る事項は、消費者において実際に解除しようと考える段階で最も関心が高まるといえます。そのため、勧誘時のみの情報提供では不十分と考えられます。そこで改正法は、事業者は契約の勧誘時点に限らず、消費者の求めに応じて、解除権の行使に関して必要な情報を提供するよう努めなければならない旨規定しました。
(4)適格消費者団体の要請に応じる努力義務(改正法12条の3から5)
適格消費者団体は、事業者が不特定かつ多数の消費者との間において、不当な契約条項(法8条から10条)を用いている場合などについては、事業者に対して差止請求権を行使できます(法12条3項・4項)。改正法施行前においても、適格消費者団体は、事業者等に対して、かかる差止請求権の行使に先立ち、任意に契約条項の開示等を求める場合がありましたが、任意の開示要請に応じない事業者の存在が問題視されていました。
そこで改正法では、一定の要件を満たす場合には、適格消費者団体が、事業者(またはその代理人)に対し、契約条項の差止請求(法12条3項・4項)に先立つ契約条項の開示を要請できるようになりました(改正法12条の3第1項)。事業者は、この要請に応じる努力義務が課されています(同条2項)。
また、差止請求権の行使を実効的なものとするため、一定の要件を満たす場合に、適格消費者団体は、事業者(またはその代理人)に対し、差止請求後の措置の開示を要請できるようになりました(同条の5第1項)。事業者は、この要請に応じる努力義務が課されています(同条2項)。
さらに、違約金等に関する説明についても改正がされていますが(法12条の4)、こちらは、次の改正点②「違約金等に関する説明の努力義務」を参照ください。
続いて、改正点②「違約金等に関する説明の努力義務」について説明します。
改正法は、消費者に対する説明の努力義務(法9条2項)と、適格消費者団体に対する説明の努力義務(法12条の4)の2つを定めています。事業者は、消費者から違約金等について説明を要請された場合、その算定根拠の「概要」を説明する努力義務が課されました。例えば、算定根拠の「概要」としては、以下のような事項を説明するように努めなければなりません。
例)イベント会場利用契約の解除と解約金の定め
「当社では、イベント当日の2週間前に契約を解除された場合には、キャンセル料として料金の3割に相当する代金をいただいております」
↓
「当社では、イベント当日の2週間前までに、イベントで使用する装飾品や人員の用意を済ませており、その分の費用が発生しております。そのため、2週間前に契約を解除された場合、キャンセル料として料金の3割に相当する代金をいただいております」
これに対し、適格消費者団体からの説明要請は、事業者の定める違約金等が平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるときになされるものです。事業者は、適格消費者団体に対し、違約金等の額の検証ができるよう具体的な費用項目や算定式などの算定根拠を説明するよう努めなければなりません。消費者に対する場合と異なり、その対象が算定根拠自体(概要にとどまらない)という点が重要です。
なお、その算定根拠について、当該事業の利益率など、営業秘密が含まれる場合などについては、事業者は説明を免れることができます。ただし、営業秘密が含まれることを理由に、全く説明しなくてもよいわけではなく、営業秘密に該当しない部分についての説明の努力義務は残ると考えられていますので、ご注意ください。
以上の通りですので、事業者としては違約金等について算定根拠をしっかり整理しておくべきといえるでしょう。
3番目は、改正点③「免責範囲が不明確な条項の無効(改正法8条3項)」です。
事業者に故意または重過失がある場合について、その損害賠償責任の一部を免除する条項は、8条1項2号・4号によって無効となります。しかし、このような免除条項に「法律で許される範囲において」という趣旨の留保文言がついていれば、無効とはならないと考えられてきました。
しかし、法的知識が十分でない消費者の場合、このような条項では、事業者に対してどのような損害賠償請求ができるのか不明確であり、結果として消費者による損害賠償請求権の行使を妨げる結果にもなりかねません。そこで改正法は、損害賠償責任の一部免除条項で、事業者に軽過失が認められる場合に限って適用されることが明らかになっていないものは、無効となるとしました。
例)
×:法律上許される限り、弊社はユーザーから支払いを受けた額を超えて責任を負わない。
◯:弊社に故意または重過失がある場合を除き、賠償限度額を〇〇円とする。
最後は、改正点④「契約の取消権に係る類型の追加」です。
これまでも、法は、事業者による不当な勧誘行為によって困惑し、消費者契約を締結してしまった消費者について、契約締結の意思表示の取り消しを認めてきましたが(法4条3項各号)、消費者被害の態様が多様化する現状に照らして、改正法は取消権の対象となる困惑類型の不当な勧誘行為として以下の3つを追加しました。
(1)退去困難な場所への同行後に行う勧誘(改正法4条3項3号):
退去意思の表明が困難な状況で、消費者に想定外の勧誘への対応を強いるケース
例)
友人から山登りに誘われて車に同乗していたところ、車でなければ引き返せない場所にある小売店に連れて行かれ、そこで商品の購入を勧められて断れないままに契約してしまった。
(2)相談連絡の妨害(改正法4条3項4号):
威迫的な態度で、相手方に相談の連絡をさせず、単独での判断を迫るケース
例)
買い物途中にサプリメントの購入を勧められ、詳しい友人に相談してから購入するかを決めたいと言ったところ、「こんなことぐらい1人で決めないと」などと迫られ、契約をしてしまった。
(3)契約締結前における目的物の現状変更(改正法4条3項9号):
契約上の義務の実施とはいえない形で目的物の現状を変更し、その原状回復を困難にすることで、消費者をして契約を締結しなければならないと思わせるケース
例)
不用品買い取り業者に指輪の買い取りを依頼したところ、指輪に付いていた宝石を鑑定するために必要などと言われて宝石を指輪から取り外されたため、買い取りに応じるしかなくなってしまった。
以上、改正法の施行により事業者の立場で気をつけるべき注意点を概説してきました。自社のビジネスが改正の影響を受ける可能性がある場合には、対応をご検討ください。
執筆=福原 竜一
虎ノ門カレッジ法律事務所 弁護士 2009年弁護士登録。企業法務及び相続法務を中心業務とする。主な著作として、「実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパクトガイド」(編著:2019年10月:ぎょうせい)がある。2019年8月よりWEBサイト「弁護士による食品・飲食業界のための法律相談」を開設し、食に関わる企業の支援に力を入れている。https://food-houmu.jp/
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話