
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
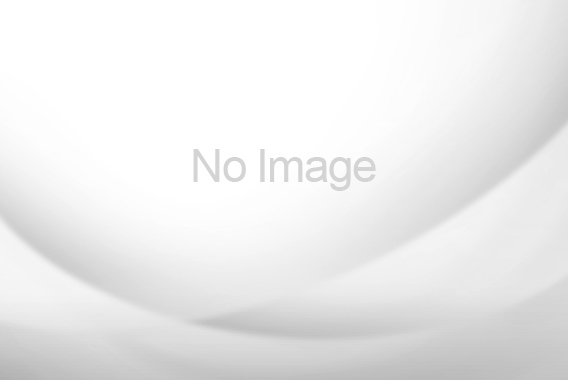 4月14日、民法の改正案が衆議院を通過し、成立する見通しとなりました。約120年ぶりにルールが変わることになります。
4月14日、民法の改正案が衆議院を通過し、成立する見通しとなりました。約120年ぶりにルールが変わることになります。
その内容は「契約のルール」に関する改正となります。これまでのルールを変更するものだったり、これまで明文化されていなかったルールが明文化されたりなど、初めて契約ルールの抜本的な見直しに着手しています。
実際に、どのようなところが変わるのでしょうか。4つの例を取り上げてみましょう。
まず大きく変わるのが「約款」です。約款とは契約に関する細かい条件のことで、あらかじめ誤解を招きそうなポイントについて明記しておくことで、企業側と顧客側の意識を合わせ、余計なトラブルを避ける効果があります。保険やネット通販といった取引においても、約款が存在するケースが多いです。
しかし、これまで民法では約款について特に明文化されていませんでした。そのため、約款の効果について不安定な側面がありました。
改正案では、ついに約款について規定が加えられました。
今回加えられたのが「定形約款」というものです。定形約款については、改正案にて「定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう)において、契約の内容とすることを目的として特定の者により準備された条項の総体」と規定されています。
簡単にいえば、ネット通販やウエブサービスのような、不特定多数の人を相手とした取引においては、定形約款が成立することになります。
この定形約款に該当すると、顧客側は約款を契約内容とすることを表示しただけで、個別の条項についても合意をしたものと見なされることになりました。要は、顧客側が約款について内容を確認しなくても、顧客は約款に明記されたことを守らざるを得なくなります。
もっとも、顧客側の権利を制限したり、義務を加重したりするような内容が含まれている場合、特に顧客の利益を一方的に害する場合には、約款について合意をしなかったものと見なすという規定もあります。どんな約款を盛り込んでもよいというわけではありません。
民法が改正される前に、自社の約款が民法上の定型約款に該当しているのか否か。該当する場合はその内容が社会通念的に問題はないかを再検討をしておくことをお勧めします。
改正前の民法では、未払い金や滞納金といった「債権」の消滅時効は、原則として10年とされています。
しかし改正案では、この原則が変更されます。権利が行使できると知った時から5年後に、債権が消滅時効となることが定められました。簡単にいえば、未払い金や滞納金を請求するための期間が短くなるということになります。
もし自社に長い期間回収できていない滞納金がある場合は、「10年もあるから大丈夫だろう」ではなく、「5年しかなくなったから早く請求しなければ」と、意識を切り変える必要があります。
改正案では、事業のために金融機関から借り入れをする際の個人保証において、経営者とは関係のない第三者が保証人になる場合――契約締結前1カ月以内に、公正証書で保証人が債務を支払う意思表示をしていなければ無効になる、と変更されています。
また保証人の契約時には、主債務者が保証人に対し、主債務者の財産状況などを情報提供すべきと規定されました。これに違反があり、「債権者が悪意または有過失であった」と見なされる場合には、保証契約が取り消すことができると規定されました。つまり、無理やり保証人にさせられ、大きな損失を被ることはないということになります。
一方で、金融機関など債権者側から見れば、保証契約が取り消されてしまう可能性が高くなることになります。保証人の支払い意思の確認方法や、主債務者の情報提供の方法などを、前もって検討をしておくべきでしょう。
改正案では、不動産賃貸契約でよく見られる「敷金」に関するルールも新たに定められました。
敷金は、賃借人(部屋を借りる人)が賃貸人(大家さん)に預けておく保証金のことです。改正案では、敷金について「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と規定されました。つまり、たとえ名目が「敷金」でなくても、敷金に該当しうることが明らかになりました。
そして敷金は、原則として「賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない」と定められました。つまり、「敷金は原則として(賃借人に)返還すべき」ということです。
上記ルールが明示されたため、無条件で一定の金額を返還しない制度は今後違法となる可能性が高くなります。例えば西日本の一部地域では、敷金のうち一定額を返還しない「敷引き」という習慣がありますが、今後は違法となる恐れもあります。賃料を含めて、運用自体を見直す必要があるでしょう。
今回の改正は、契約のルール全般を改正するものです。やがてはこの改正案が新たなスタンダードになるため、早く準備に着手して困ることはありません。
新しい民法は2019年頃に施行される見込みとなっています。幅広い改正ですから、自社の業務に関連することがないか、慎重に検討してください。
執筆=本間 由也
1982年生まれ。2004年明治学院大学法学部法律学科卒業、2007年明治学院大学法科大学院法務職研究科法務専攻卒業。翌2008年に司法試験合格。紀尾井町法律事務所での勤務を経て、2011年1月法テラス西郷法律事務所初代所長に就任。2014年2月こだまや法律事務所を東京都国分寺市に開所、現在に至る。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話