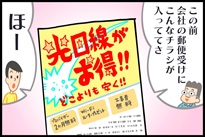
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
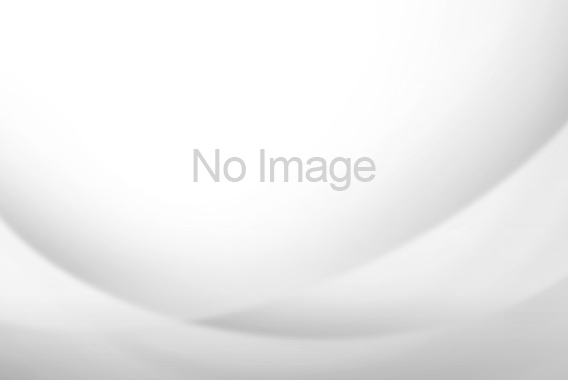
近年、企業に勤める人たちの副業や兼業(以下、「副業など」)への関心が高まっています。2017年には副業などを行っている人の数は128万人を超え(総務省「就業構造基本調査」 副業者数(雇用×雇用)の変化)、年々増加傾向にあります。
最近では、デジタル分野で活躍が目立ち、本業のノウハウを生かし、中小企業のネット通販や業務の効率化を支援するなど、副業で本業並みの収入を稼ぐ「パワフル副業者」も現れ始めているとの報道もあります。
国は、こうした副業などへの高い関心を踏まえ、2018年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を定めました。また、それに合わせてモデル就業規則に、副業などに関する条項が設けられました。
本連載では、第50回(2018年11月)で、従業員の副業などに関する企業の基本的な対応について解説しましたが(「社員の副業・兼業、どう認める?どう規制する?」)、その後、2020年9月にガイドラインが改正され、労働時間管理と健康管理について新たな指針が加えられました(厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年9月改定)」(PDF表示))。
そこで、改正されたガイドラインの内容を踏まえ、今一度、従業員の副業などに関する企業の労務管理のポイントについて解説します。ガイドラインは多岐にわたるため、本稿では焦点を絞り、労働時間の管理に関して見ていきます。
労働基準法(以下、「労基法」)第38条は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定しています。ここでいう「事業場を異にする場合」とは、職場が異なる場合をも含むとされています(労働基準局長通達(昭和23年5月14日基発第769号))。
従って、A社に勤める従業員Bさんが他社(C社)で労基法の労働時間に関する規定が適用される副業などをしている場合(BさんがC社と雇用契約を締結して副業している場合が典型例)、A社はBさんのC社での副業などの労働時間を把握する必要があります。
そして、A社は、Bさんが勤務した自らの事業場(A社)における労働時間と他の使用者(C社)の事業場における労働時間とを通算して、自らの事業場(A社)の労働時間が法定労働時間(労基法第32条・第40条)を超える場合には、その超える部分について時間外労働(労基法第36条)として、Bさんに対して所定の割増賃金を支払う必要があります。なお、前提として、いわゆる三六協定の締結が必要となります。
また、長時間労働を抑止するために設けられた時間外労働の上限規制である、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件(労基法第36条第6項第2号および第3号)は、従業員Bさん個人の労働時間に着目して、当該個人Bさんを使用する使用者(A社とC社の双方)を規制するものです。
そのため、上限規制を超えていないかを判断するに当たっては、自らの事業場(A社)における労働時間と他の使用者の事業場(C社)における労働時間を通算しなければなりません。
このように時間外労働の割増賃金を算定するため、あるいは、時間外労働の上限規制を順守するため、企業(A社)は、従業員Bさんの他社(C社)での副業などの労働時間を把握する必要があります。
では、A社は、どのようにしてBさんのC社での労働時間を把握すればよいのでしょうか。
これについて、ガイドラインでは、「使用者は、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認する」として、企業(A社)は、従業員Bさんの「申告等」により、他社(C社)での労働時間を把握することを求めています。
また、その方法については、「就業規則、労働契約等に副業・兼業に関する届出制を定め(ること)が考えられる」として、就業規則や労働契約において副業などの有無・内容を確認するための仕組み(届出制)を設けておくことが望ましい、としています。
そして、副業などの内容として確認する事項としては、以下のようにまとめています。
(1) 他の使用者(C社)の事業場の事業内容
(2) 他の使用者(C社)の事業場で労働者Bさんが従事する事業内容
(3) 労働時間通算の対象となるか否か
が考えられる、としています。
その上で、労働時間の通算の対象となる場合には、さらに、下記の項目を確認しましょうと促しています。
(4) 他の使用者(C社)との労働契約の締結日、期間
(5) 他の使用者(C社)の事業場での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻
(6) 他の使用者(C社)の事業場での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数
(7) 他の使用者(C社)の事業場における実労働時間等の報告の手続
(8) これらの事項について確認を行う頻度
これらについておのおのの使用者(A社とC社の双方)と労働者Bさんとの間で合意しておくことが望ましい、としています。
従って、A社は、C社で副業をするBさんのC社での労働時間について、就業規則などによって定める届出制により、Bさんに上記(1)~(8)を申告させることにより、把握しておくことになります。
以上の方法によって、A社が、BさんのC社での副業などの労働時間を把握して通算した結果、自らの事業場での労働時間が法定労働時間を超え、時間外労働になる場合、Bさんに対し、労基法第37条第1項所定の割増賃金を支払う必要があります。
ここで問題となるのは、いかなる場合に法定労働時間を超えた時間外労働になるか、言い換えれば、割増賃金を支払う義務があるのは、どのような場合かということです。
これについては、「『副業・兼業の促進に関するガイドライン』Q&A」で、4つの類型を挙げて検討しており、詳細は、そちらをご参照ください。
ここでは、基本的な考え方について述べます。
まず、複数の事業場における所定労働時間を通算すると法定労働時間を超える場合、時間的に後から労働契約を締結した使用者は、契約の締結に当たって、当該労働者が他の事業場で労働していることを確認した上で契約を締結すべきことから、割増賃金を支払う義務を負います。
例えば、BさんがA社で「所定労働時間8時間」とする労働契約を締結していた場合に、C社が、後からBさんと「所定労働時間5時間」とする労働契約を締結し、Bさんが、A社とC社の双方で所定労働時間の労働をした場合、後から契約を締結したC社が、Bさんに対して割増賃金を支払う義務を負います。
また、通算した所定労働時間が既に法定労働時間に達していることを知りながら労働時間を延長するときは、先に契約を結んでいた使用者も含め、延長させた各使用者が割増賃金を支払う義務を負います。
例えば、Bさんが、A社と「所定労働時間4時間」という労働契約を締結し、新たにC社とも「所定労働時間4時間」という労働契約を締結して、A社で5時間労働し、その後C社で4時間労働した場合、A社は、通算した法定労働時間8時間を超えた「1時間分」について、Bさんに対して割増賃金を支払う義務を負います。
このように、いかなる場合に法定労働時間を超えた時間外労働となり、割増賃金を支払う義務があるのかは、
〔1〕 まず労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、
〔2〕 次に所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算することによって、
具体的に検討することになります。
以上の労働時間の通算は、実際には労使双方にとって手続き上の負担が大きいものです。
そこで、かかる手続き上の負担を軽減し、労基法を順守しやすくするため、改正されたガイドラインにおいて、副業などの簡便な労働時間管理の方法として、「管理モデル」が示されました。
これは、従業員Bさんの副業などの開始前に、A社(先契約)の法定外時間労働とC社(後契約)の労働時間について、上限規制(単月100時間未満、複数月平均80時間以内)の範囲内であらかじめそれぞれ上限を設定し、それぞれについて割増賃金を支払うという方法です。
これにより、従業員Bさんの副業などの開始後は、企業(A社またはC社)は、それぞれあらかじめ設定した労働時間の範囲内で労働させる限り、他社でのBさんの実労働時間を把握しなくても労基法を順守することが可能となります。
管理モデルの実施に当たっては、副業などを行おうとする従業員に対して、A社(先契約)が管理モデルによることを求め、従業員Bさんおよび従業員Bさんを通じて後契約のC社が応じることによって導入される流れになります。
なお、管理モデルの導入の際、ある月の労働時間が80時間を超えるときは、翌月以降において複数月平均80時間未満となるよう労働時間の上限の設定を調整する必要が生じます。しかし、これは労使双方の手続き上の負担が大きくなり、管理モデルの趣旨に反します。そのため、ガイドラインでは、「そのような労働時間を調整する必要が生じないように、おのおのの使用者と労働者との合意により労働時間の上限を設定することが望ましい」とされています。
以上のように、副業などに関する労働時間の管理は若干複雑ですが、労働者の協力を得ながら企業がこれを適切に行うことによって、人生100年時代における新たな雇用社会をつくりあげていってほしいと思います。
執筆=上野 真裕
中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。平成15年弁護士登録。小宮法律事務所(平成15年~平成19年)を経て、現在に至る。令和2年中小企業診断士登録。主な著作として、「退職金の減額・廃止をめぐって」「年金の減額・廃止をめぐって」(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話