
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
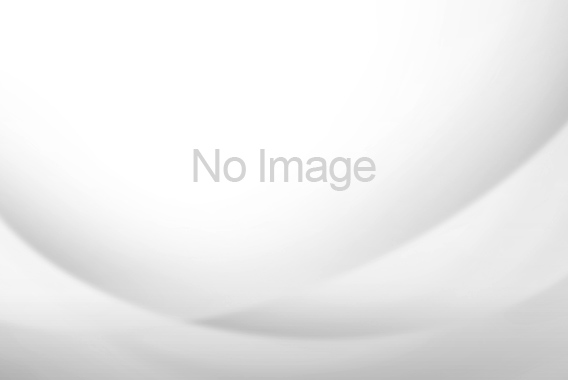 下請け業者を守るために複数の法律やガイドラインがあります。これらを活用して、言いなりにならない下請け業者になりましょう。うちは下請けだから……。こう言って発注先の言いなりになっていませんか。下請け業者はどんなことでも我慢をしなければいけないのか。そんなことはありません。下請け業者を守るための法制度があります。今回はこの法制度を知って、言いなりにならないための“理論武装”をしてみましょう。
下請け業者を守るために複数の法律やガイドラインがあります。これらを活用して、言いなりにならない下請け業者になりましょう。うちは下請けだから……。こう言って発注先の言いなりになっていませんか。下請け業者はどんなことでも我慢をしなければいけないのか。そんなことはありません。下請け業者を守るための法制度があります。今回はこの法制度を知って、言いなりにならないための“理論武装”をしてみましょう。
下請け業者を守るための法制度の1つとして、「独占禁止法」を知っている方は多いのではないかと思われます。独占禁止法では「取引上、強い力を持つ者が、取引の相手方に対し、その優越的な地位を利用して、正常な商取引では認められないような不利益を与える行為は許さない」という規制が含まれています。
では、「下請け代金支払遅延等防止に関する法律」(以下、「下請法」)はいかがでしょうか。この法律こそ、下請け業者のための法律なのです。この法律では業務委託を行う企業を「親事業者」、それを受託する企業を「下請事業者」と呼んでいます。それに従って以下では「下請事業者」という表記を使います。
下請法が“下請事業者のための法律である”という根拠としては、下請法は発注書などの書面の作成・交付・保管について定められているという点があります。
下請けいじめの典型例として、不当な請負代金の減額、給付内容の変更、受領拒否、支払期日の延期などがあります。これらの原因の1つは、発注や交渉経緯などが書面化されておらず、契約内容が不明確なことにあります。
下請法では、親事業者に発注書面(下請業者の給付内容、代金、支払期日、支払方法等を記載)の交付を義務づけています。そのため、この義務が果たされると、必然的に親事業者による理由なき代金の減額、給付内容の変更を防ぎ、支払期日が不明などといったトラブルも防ぐことができます。
また、親事業者に対し、下請け取引の経緯を記載した書類等の作成および2年間の保管を義務づけています。そのため、取引から2年以内であれば、親事業者に関係書類が保管されていますので、「資料がないから紛争解決が困難」という事態も防ぐことができるようになっています。
さらに、下請法では、親事業者の都合による下請け代金の支払い時期の変更、延期を防ぐために、たとえ下請事業者の同意があったとしても、下請け代金は下請事業者が給付をした日から60日以内に支払われなければならないこととされています。親事業者がこの支払期日までに支払わなかった場合、年14.6%の遅延損害金も支払わなければなりません。
このように代金支払いに関する親事業者の義務も定め、下請事業者を保護しているのです。
このほかにも、典型的な下請けいじめとして想定される、親事業者による下請け代金の支払い遅延、代金減額、返品、買いたたきや、不当な給付内容の変更、やり直し、受領拒否や返品の禁止などを行ってはならない旨の定めもあります。
もっとも、下請法はすべての下請事業者に適用されるわけではありません。会社の規模や取引の内容によっては、下請法の対象から外れる場合があります。
下請法では、取引当事者の資本金の区分と取引内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託または役務提供委託)の両面から、「何をもって下請事業者とするか」を規定しています。例えば、物品の製造委託、修理委託のケースを見てみましょう。親事業者が資本金3億円を超える法人事業者の場合には、資本金3億円以下の法人事業者または個人事業者が下請事業者となります。
しかし、親事業者の資本金が1000万円を超え、資本金が3億円以下である場合は、資本金1000万円以下の法人事業者または個人事業者が下請事業者となるとされています。
こうした基準を押さえ、自身の取引相手の資本金額と取引内容について確認をし、各取引につき下請法が適用されるか否かを、事前にチェックしておくべきでしょう。
下請事業者を守るための法律は、下請法以外にも数多くあります。例えば「建設業法」においても、同種の規制がなされています。
また、消費税増税分を下請事業者が不当に負担させられないための法律として、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)という法律もあります。
同法は、大規模小売事業者や資本金3億円以下の法人事業者や個人事業者などと取引を行っている法人事業者などが、消費税増税分を上乗せせずに減額や利益供与を要請する行為などを禁止しています。
このように、下請事業者を保護するための法制度に定められていること以上を無理にやる必要はありません。もう、親事業者の言いなりにならなくても良いのです。
こうした法律があるといっても、親事業者が法律を守らなければ意味がありません。そのため、下請法違反の調査のために、行政による親事業者に対する書面調査や立入検査が認められています。その結果、違反が発見された場合には、行政による勧告や公表がなされる可能性があります。コンプライアンスが重視される現代において、公表により被る損害は甚大です。さらに、一定の違反に対しては、違反者個人や会社に対し罰金という刑事罰が科せられるように規定されています。
そのため、下請法違反と思われるときには、調査の申し立てなどを積極的にすることを武器に、親事業者と交渉するのがよいでしょう。
しかし、そもそも親事業者と下請業事業者は、“戦う”関係ではなく、互いに協力し合い競争力を強めるほうが得策です。このことは、業界ガイドラインでも触れられています。そもそも親事業者と下請事業者に対立が生じること自体、不利益なことなのです。
では、どのようにすれば対立を生じない関係となりやすいのでしょうか。そのためには、まずは下請事業者が下請法や業界ガイドラインの内容を知ることが重要です。経済産業書のホームページでは、業種別に定められた「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」が公開されています。このガイドラインには、各業界の取引を前提とした具体例が記載してあり、実際の取引での留意点など、イメージをしやすいものとなっています。親事業者としても、コンプライアンス対策として事前に下請法違反を予防するために活用できます。
親事業者から発注書などの交付がない場合は、下請事業者から書式を提案しましょう。この交渉には親事業者も制裁を避けるというメリットがありますので、親事業者も交渉に応じる可能性は十分にあると思います。
そして、その交渉の場においてガイドラインを共有化し、共通認識をもちます。そうすることによって、対立構造から協力関係に関係を変化させるきっかけを生むことができます。
「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」には、親事業者と下請事業者との望ましい取引例も紹介されています。これらを参考に親事業者と下請事業者とWIN-WINの関係をつくり、競争力を高めるという問題意識を、下請事業者から提案してはいかがでしょうか。
執筆=本間 由也
1982年生まれ。2004年明治学院大学法学部法律学科卒業、2007年明治学院大学法科大学院法務職研究科法務専攻卒業。翌2008年に司法試験合格。紀尾井町法律事務所での勤務を経て、2011年1月法テラス西郷法律事務所初代所長に就任。2014年2月こだまや法律事務所を東京都国分寺市に開所、現在に至る。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話