
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
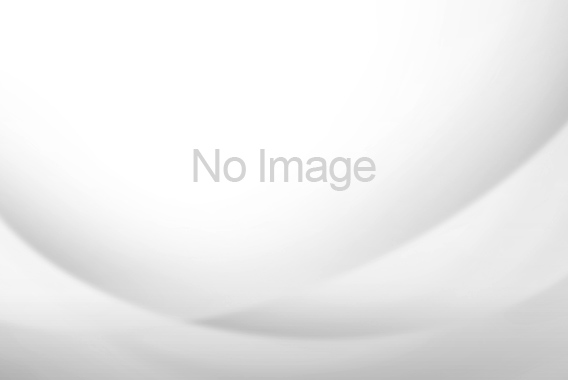
2021年4月に成立・公布された「民法等の一部を改正する法律」(以下:「2021年改正法」)が、2023年4月1日以降順次施行されます(改正事項によって施行日が異なります)。2021年改正法は、従来の民法や不動産登記法などの基本的ルールを見直すもので、適用場面は広く、特に不動産関連の相続に与える影響はとても大きいものです。
そこで第1回、第2回は、不動産関連の相続に影響する改正点のうち、不動産の登記関連、遺産分割関連の改正点について概説しました。今回は、複数人が共有している不動産などを円滑かつ適正に利用するための共有制度の見直しに関する改正点と、2021年改正法と同時に成立・公布された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下:「相続土地国庫帰属法」)」により創設された相続土地国庫帰属制度について概説します。
従来、共有物の「変更」には共有者全員の同意を要し(改正前民法251条)、「管理」に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い過半数で決するとされていました(改正前民法252条本文)。そのため、共有者に与える影響が小さくても1人の反対があれば変更できず、共有物の円滑な利用が妨げられるといわれてきました。
また、共同相続の開始により相続人間に遺産共有状態が生じるところ(改正民法898条1項。本コラム第2回参照)、数次相続(遺産分割未了のまま相続人が死亡し次の相続が開始すること)などにより相続人が多数に上る場合や相続人の一部の所在などが不明の場合、共有物の変更や管理に必要な同意を得ることはますます困難となり、共有物の利用に支障を来していると問題視されていました。
そこで、共有物の円滑かつ適正な利用を促進すべく、2021年改正法では、共有物に変更を加える行為であっても、その形状または効用の著しい変更を伴わないもの(以下:「軽微変更」)については、共有物の「管理」に関する事項と同様、各共有者の持分の過半数で決することが可能になりました(表1参照:改正民法251条1項括弧書、252条1項。2023年4月1日施行。なお、遺産共有の場合の各相続人の共有持分は、法定相続分または指定相続分により算定されます。改正民法898条2項。2023年4月1日施行)。
●表1 共有物の管理・変更・保存行為の同意要件
| 共有物に対する行為の種類 | 根拠条文 | 同意要件 | |
| 変更(軽微変更を除く) | 改正民法251条1項 | 共有者全員 | |
| 管理(広義) | 変更(軽微) | 改正民法251条1項 括弧書、252条1項 | 持分の価格の過半数 |
| 管理(狭義) | 改正民法252条1項 | ||
| 保存 | 改正民法252条5項 | 共有者単独 | |
「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」(法務省)をもとに作成
また、共有者の持分の価格の過半数で、共有物に対する短期の賃借権その他の使用・収益を目的とする権利の設定が明確化されました(改正民法252条4項。2023年4月1日施行)。具体的には、①樹木の栽植または伐採を目的とする山林の賃借権などは10年(1号)、②①以外の土地の賃借権などは5年(2号)、③建物の賃借権などは3年(3号)、④動産の賃借権などは6カ月(4号)を超えないものが対象となります。
なお、2021年改正法では、共有物の円滑な管理を図るため、共有物の管理を委ねるための管理者の選任や権限の内容についての規定が整備されました(改正民法252条の2。2023年4月1日施行)。
さらに、所在等不明共有者(必要な調査をしても氏名や所在などが不明な共有者)がいる場合、他の共有者は、裁判所の決定(共有物変更許可決定)を得て、所在等不明共有者以外の共有者の同意により、共有物に変更(軽微変更を除く)を加えることができるようになりました(改正民法251条2項、改正非訟事件手続法85条。2023年4月1日施行)。
共有物の管理(広義)についても、所在等不明共有者または賛否不明共有者(共有者が相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することにつき賛否を明らかにすべき旨を催告したが、その期間内に賛否を明らかにしない共有者)がいる場合、他の共有者は、裁判所の決定(共有物管理許可決定)を得て、所在等不明共有者または賛否不明共有者以外の共有者の持分の価格の過半数により、共有物の管理に関する事項を決定できるようになりました(改正民法252条2項、改正非訟事件手続法85条。2023年4月1日施行)。
なお、共有物の使用(改正民法249条)についても重要な改正がされています。特定の共有者が共有物を使用する場合、その共有者が他の共有者に対していかなる義務を負うかについては、従来は明確な規定がありませんでした。しかし、共有物の円滑かつ適正な利用の観点からは、共有物を使用する者と他の共有者との関係の明確化が望ましく、2021年改正法では、共有物を使用する共有者が他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務と善管注意義務を負うことが明記されました(改正民法249条2項・3項。2023年4月1日施行)。
不動産が数人の共有に属する場合において、所在等不明共有者がいても共有関係を解消できるよう、共有者の請求により裁判所がその共有者に所在等不明共有者の持分を取得させ、またはその共有者に所在等不明共有者の持分を譲渡する権限を付与する旨の裁判ができる制度が新設されました(改正民法262条の2、262条の3。2023年4月1日施行)。
相続により不動産が遺産共有状態となり、相続人の中に所在などの不明な者がいる場合には、相続開始から10年(具体的相続分による遺産分割の機会が保証される期間。本コラム第2回参照)が経過したときに限り、持分取得・譲渡制度によって共有関係を解消することができます(改正民法262条の2第3項、262条の3第2項。2023年4月1日施行)。
近年、地方を中心に土地需要が縮小し、土地に対する所有者の関心が失われ、適切に管理されなくなる土地が増えています。このような状況下で、望まずに相続した土地を手放したいと考える所有者が増加しており、これがさらなる土地の管理不全化を招き、所有者不明土地の原因になっていると指摘されてきました。
そこで、相続などにより取得した土地を国庫に帰属させることを可能とする相続土地国庫帰属制度が創設されました。もっとも、土地を手放して国庫に帰属させるということは、土地の所有に伴う管理コストを国に転嫁し、最終的には国民全体が負担することになります。そのため、相続土地国庫帰属制度においては、「通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地」が類型化され、この類型に該当しないことが国庫帰属の要件とされています(相続土地国庫帰属法2条3項各号、5条1項各号。2023年4月27日施行)。
【却下要件(相続土地国庫帰属法2条3項各号)】
土地が次のいずれかに該当するときは承認申請をすることができません。
1 建物の存する土地
2 担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
3 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
4 土壌汚染対策法2条1項に規定する特定有害物質で汚染されている土地
5 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
【不承認要件(相続土地国庫帰属法5条1項各号)】
法務大臣(法務局)は、必要に応じて実地調査などを行い、次のいずれにも該当しないと認めるときは、国庫への帰属を承認しなければなりません。
1 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る)がある土地で、通常の管理に当たり過分の費用または労力を要するもの
2 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上に存する土地
3 除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることができない有体物が地下に存する土地
4 隣接する土地の所有者その他の者と争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない土地として政令で定めるもの
5 上記のほか、通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地として政令で定めるもの
要件審査を経て法務大臣の承認を受けた者は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を収め、これによって土地の所有権は国庫に帰属します(相続土地国庫帰属法10条1項、11条1項。2023年4月27日施行)。
以上、2021年改正法のうち、不動産関連の相続に影響する事項について3回にわたって概説しました。2021年改正法の改正項目には、その他にも、不動産登記法の改正として休眠用益権・休眠法人などの担保権抹消手続きの見直しや、民法などの改正として、財産管理制度の見直し(所有者不明土地・建物管理制度の創設、管理不全土地・建物管理制度の創設)、相隣関係の規律の見直しなどがあります。
2021年改正法については、法務省の「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」というwebサイトに詳しくまとめられており、随時情報が更新されています。気になる方はチェックしてみてください。
執筆=福原 竜一
虎ノ門カレッジ法律事務所 弁護士 2009年弁護士登録。企業法務及び相続法務を中心業務とする。主な著作として、「実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパクトガイド」(編著:2019年10月:ぎょうせい)がある。2019年8月よりWEBサイト「弁護士による食品・飲食業界のための法律相談」を開設し、食に関わる企業の支援に力を入れている。https://food-houmu.jp/
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話