
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
2020年4月1日から改正された民法(以下:「新法」)が施行されます(一部規定は除く)。契約のルールは民法により定められているので、改正の影響で契約書の条項を見直しする必要が出てきます。前編では、見直すべき契約書のポイントの中で、金銭消費貸借契約やそれに付随する保証契約について解説しました。後編では、請負契約に関して、発注者や受注者の立場として、どのような点を見直すべきなのかを解説します。
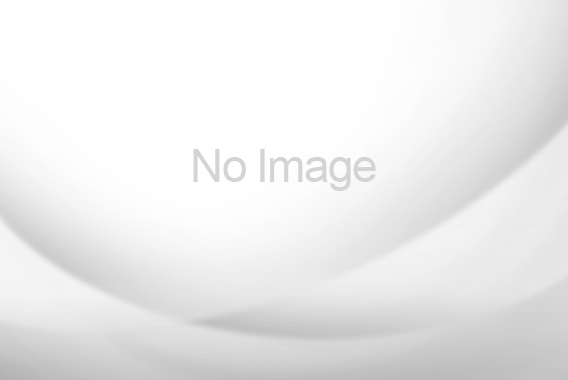 請負契約は、建物の建設、内装、リフォームなどの建築関係やソフトウエア開発などのさまざまな契約で用いられています(ソフトウエア開発契約は一部準委任契約の要素もあります)。日常の企業活動においてよく使われる契約です。
請負契約は、建物の建設、内装、リフォームなどの建築関係やソフトウエア開発などのさまざまな契約で用いられています(ソフトウエア開発契約は一部準委任契約の要素もあります)。日常の企業活動においてよく使われる契約です。
請負契約においては、発注者を「注文者」、受注者を「請負人」といいます。請負契約では、発注者は請負人の仕事の結果に対して報酬を支払う義務を、請負人は仕事を完成させる義務を負います。請負人が報酬を請求するためには仕事を完成させなければならず、たとえ仕事を途中まで行ったとしても、仕事の完成までは報酬を請求できないのが原則です。
この点について、新法では、請負契約が、(1)注文者の責めに帰すことができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合や、(2)仕事の完成前に解除された場合において、請負人の仕事内容が可分であり、それにより注文者が利益を受けているのであれば、仕事の完成前であっても利益部分に応じた報酬を請求できることが明文化されました(新法634条)。これは従来の判例を明文化したものであり、実務もこれに従って動いていたため、実務上の運用に大きな変化はありません。
ただ、新法で仕事の完成前の報酬支払請求権が明文化されたことで、請負人としては円滑に報酬請求権を行使するために、請負契約書にも完成前の報酬請求権を明文化することが考えられます。従来、建設関連の請負契約では、手付金や工事途中での一部報酬の支払いの項目を入れるケースがありましたが、それが標準になることが考えられます。
ここで注意をしなければならないのがソフトウエア開発です。ソフトウエア開発の業務は、仕事が途中まで終わっていても、それはあくまで開発途中のソフトウエアであり、最終的なソフトウエアは完成しておらず、業務上ではまったく使えないケースも少なくありません。従って、注文者であるユーザーの利益を金銭的に評価することは困難を伴います。こうなると新法の規定に従って、注文者が利益を受けていることを報酬請求の要件とすると、請負人であるベンダーとしては途中までの報酬を一切請求できない可能性があります。
そこで、このような場合、請負人としてはあえて新法に従った完成前の報酬支払請求権を契約書に盛り込まずに、請負契約が途中で終了した場合の費用精算の中で、既に完成した部分に応じた報酬を支払う旨を定めておくことが考えられます。なお、一般社団法人電子情報技術産業協会のモデル契約をひな形にソフトウエア開発の契約を結ぶケースが少なくないと思われますが、既に公表されている新法施行後のモデル契約の規定でも、上記の考え方になっています。
従来、請負契約において、請負人の仕事の内容に瑕疵(かし)がある場合は、注文者は請負人に対して瑕疵の修補や損害賠償を求めたり、契約の目的を達成できない場合は契約の解除をしたりすることができるものとされており、これは「瑕疵担保責任」と呼ばれていました。
新法では、請負人の「瑕疵担保責任」は、売買契約の責任が準用され、「契約不適合責任」という責任に整理されました(新法562条1項、559条)。契約不適合責任では、従来の瑕疵担保責任の責任追及手段に加えて、代替物の引き渡しといった履行の追完(ついかん)や代金減額請求(新法563条)もできるようになりました。
新法では、契約不適合責任について、複数の責任追及手段が規定されたことにより、請負契約書でも責任追及手段の範囲を明記しておくことが考えられます。まず、請負人の立場では、複数の責任追及手段があることにより対応が煩雑となることが想定されるため、請負契約書において、責任追及手段を限定しておくことが考えられます。
例えば、当初の請負代金は確保したいという要請があれば、代金減額請求権は除外するというということが考えられます。
一方、注文者の立場では、複数の責任追及手段を確保するほうが万一を考えれば安心です。新法で規定されたそれぞれの責任追及手段を行使することができる旨を請負契約書に明記するように主張すべきでしょう。
従来の瑕疵担保責任では、仕事の目的物を引き渡した時ないしは仕事の完成から1年以内に権利行使しなければならないとされていました。しかし新法の契約不適合責任では、注文者が契約不適合を知った時から1年以内に契約不適合の事実を通知することで足りることになりました(新法637条1項)。
これにより新法の下では、請負人が責任追及される期間が長期になる可能性が高くなります。そこで、請負人としては、契約不適合責任の追及できる期間を引き渡しから1年間に限定することが考えられます。なお、建築関係の請負契約で多く用いられる「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款」では、契約不適合責任を追及できる期間を原則として引き渡しから2年に限定する形で改正される予定です。
他方で、注文者としてはより長期にわたって責任追及ができるよう、新法の規律と同様に、契約不適合を知った時から1年以内に追及すれば足りる旨を請負契約書の特約に設けることが考えられます。
なお、請負契約のうち、住宅の新築工事については「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、一定の瑕疵についての担保責任に関して、建物を引き渡した時から10年とされており、これに反する特約で注文者に不利なものは無効とされていることに注意が必要です(民法改正整備法による改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律94条1項及び2項、2条5項)。
また、請負契約が消費者契約に該当する場合は、消費者契約法により請負人の契約不適合責任を全部免除する規定は原則として無効になることにも注意が必要です(民法改正整備法による改正後の消費者契約法8条1項1号)。
以上、民法改正と請負契約書の見直しポイントについて見てきました。請負契約は、その業界ごとに業界団体の契約書が用いられることが多い契約です。例えば、建築関係では「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款」、ソフトウエア開発では電子情報技術産業協会の「ソフトウェア開発モデル契約」などが代表例といえます。
これらの契約書は民法改正に伴って見直しが行われています(なお、「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款」は「民間(旧七会)連合協定工事請負契約約款」になります)。こうした業界団体の契約書の内容を、自己に有利に変更することは取引慣行からして容易ではありませんが、少なくとも民法改正に伴ってどの部分が変更されたかを確認しておくことは必要であると考えられます。
執筆=近藤 亮
近藤綜合法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属) 平成27年弁護士登録。主な著作として、『会社法実務Q&A』(ぎょうせい、共著)、『少数株主権等の理論と実務』(勁草書房:2019、共著)、『民事執行法及びハーグ条約実施法等改正のポイントと実務への影響』(日本加除出版:2020、共著)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話