
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
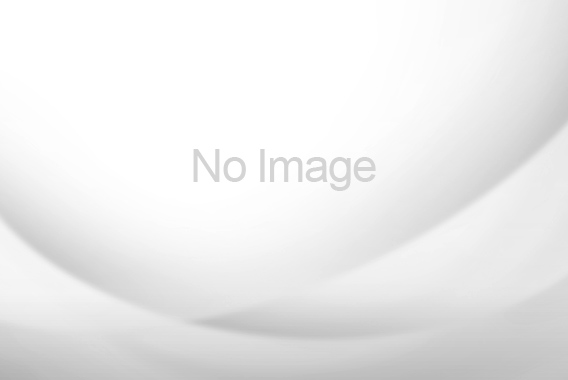
2020年5月に公表された「フリーランス実態調査結果(内閣官房日本経済再生総合事務局)」によれば、日本にはエンジニアや配達員など組織に属さず独立した事業者として働くフリーランスが462万人いると試算されています。同調査では、事業者から業務委託を受けて仕事を行うフリーランスの約4割が、トラブルを経験しているということも明らかになりました。
この背景には、1人の「個人」として業務委託を受けるフリーランスと、「組織」として業務委託を行う発注事業者との間に、交渉力やその前提となる情報収集力に格差が生じやすいためと考えられています。また、フリーランスは特定の発注事業者への依存度が高い傾向にあるという点も、要因と考えられています。
こうした状況を改善すべく、フリーランスに係る取引を適正化し、フリーランスが安定して働ける環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」(以下:フリーランス新法)が制定され、2023年5月12日に公布されました。公布の日から起算して1年6カ月を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
フリーランスに業務を委託している企業経営者が押さえておくべきフリーランス新法の概要と実務上の留意点について、前後編の2回に分けて解説します。
前述のとおり、フリーランス新法は、組織である発注事業者から業務委託を受ける個人としてのフリーランスを取引上保護するために制定されました。
フリーランス新法は、組織である発注事業者(2条6項「特定業務委託従事者」)と個人であるフリーランス(2条1項「特定受託事業者」)との間の業務委託に関する取引に適用されます。
具体的には、発注事業者(特定業務委託従事者)は、個人事業主であって従業員を使用するもの、法人であって2人以上の役員がいるか従業員を使用するもののいずれかです。また、フリーランス(特定受託事業者)は、個人であって従業員を使用しないもの、法人であっても1人の代表者以外に役員がなく従業員を使用しないもののいずれかです。
そして、業務委託とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することをいい、委託とは、物品・情報成果物・役務の仕様・内容を指定してその製造や作成・提供を依頼することをいいます。つまり、事業者間(BtoB)における委託取引が本法の対象となります。
フリーランス新法では、発注事業者とフリーランスとの間の業務委託取引が適正に行われるよう、次のような定めをしています。
第1に、発注事業者が、フリーランスに業務を委託する場合、給付(=委託した業務)の内容、報酬の額、支払期日などを書面または電磁的方法(メール、SNS)によって明示しなければなりません(3条)。
本条は、業務委託契約の内容を明確にして未然にトラブルを防止し、また、トラブルが発生した場合に、契約内容についての証拠とするために規定されました。かかる本条の趣旨は、発注事業者が組織ではなくフリーランスの場合にも当てはまるため、本条に限ってはフリーランス間の業務委託取引にも適用される点は、注意が必要です(条文上「特定業務委託従事者」ではなく、「業務委託従事者」とされているのは、その趣旨です)。
第2に、発注事業者は、フリーランスから給付を受領する日から60日以内で、かつ、できる限り短い期間内に報酬支払期日を設定しなければなりません。また、発注事業者も受託者の場合(=再委託の場合)は、発注事業者が発注元から支払いを受ける期日(実際に支払いのあった日ではなく、合意により定めた期日である点に注意)から30日以内で、かつ、できる限り短い期間内に報酬支払期日を設定しなければなりません(4条)。
本条は、発注事業者が報酬の支払期日を不当に遅く設定することから、フリーランスを保護するために規定されたものです。
第3に、発注事業者は、フリーランスへの業務委託(政令で定める期間以上のもの)に際して、次の①から⑤の行為をすることは禁止されます。また、⑥・⑦の行為によってフリーランスの利益を不当に害してはなりません(5条)。
本条は、「政令で定める期間以上」の継続性のある業務委託の場合にのみ適用されます。これは、契約期間が長くなるほど発注事業者とフリーランスとの間で経済的な依存関係が生じ、それを利用した不利益をフリーランスが受けやすい傾向にあるためです。
「政令で定める期間」については、2023年9月時点では明らかではないものの、国会での質疑で「3カ月を超えて6カ月といった長期となるほど、取引先から不利益行為というものを受けやすい」との指摘がなされていることから、このあたりの期間になると予想されます。
①フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、発注した物品等の受領を拒否すること(1項1号)
発注事業者の一方的都合により発注取り消しをして受け取らないことも、これに該当します。
②フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、契約で定めた報酬を減額すること(1項2号)
減額についてあらかじめ合意があったとしても、フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに減額した場合は、違反となります。
③フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、発注した物品等を受領した後に返品すること(1項3号)
返品は、発注事業者が、発注した物品等をいったん受け取る点で、①の受領拒否と異なります。
④通常相場に比べて著しく低い報酬の額を不当に定めること(1項4号)
いわゆる「買いたたき」のことです。不当な買いたたきにあたるかは、ⅰ、対価の決定方法、ⅱ、差別的であるかなど対価の決定内容、ⅲ、同種または類似品等の市価との乖離(かいり)状況、ⅳ、給付に必要な原材料等の価格動向などの要素を総合して判断されます。
⑤正当な理由がないのに、発注事業者の指定する物の購入・役務の利用を強制すること(1項5号)
発注する物品等の品質を維持する目的で、発注事業者が、物の購入や役務の利用を指示する場合は正当の理由あり、といえます。
⑥発注事業者のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること(2項1号)
あらかじめ定められた報酬をさまざまな名目で減額することは上記②によって禁止されますが、協力金、協賛金などの名目による金銭の支払い等の要求は、それによりフリーランスの利益を不当に害するような場合、本号によって禁止されます。
⑦フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、給付の内容を変更させ、またはやり直しさせること(2項2号)
発注事業者が、フリーランスが作業に当たって負担する費用を負担せずに、一方的に発注を取り消す場合もこれに含まれます。
執筆=上野 真裕
中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。平成15年弁護士登録。小宮法律事務所(平成15年~平成19年)を経て、現在に至る。令和2年中小企業診断士登録。主な著作として、「退職金の減額・廃止をめぐって」「年金の減額・廃止をめぐって」(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話