
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
最近、大きな話題になった芸能事務所の騒動。そもそもの発端は所属するタレントが反社会的勢力(反社)の主催するパーティーに出席したことでした。そこから発展したトラブルは、ついには経営陣の進退問題にまでエスカレートしたことは記憶に新しいところです。
反社会的勢力に関連したリスクは、こうした芸能事務所に限ったことではありません。一般の企業でも気を付けなければならない経営リスクの1つです。今回は反社会的勢力問題について解説します。
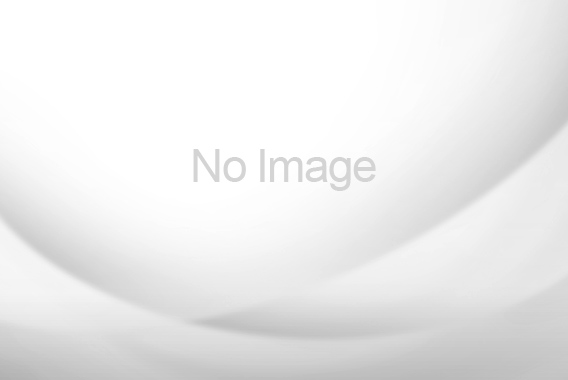 まずは、反社会的勢力とは何を意味するのか、説明できますか。いわゆる暴力団が含まれるのは容易に想像できるでしょう。さらに、暴力団は企業の体裁を装うこともあります(暴力団関係企業、フロント企業などといわれます)。これらの企業は、文字通り、企業を装っているだけですから、もちろん反社会的勢力の中に含まれます。
まずは、反社会的勢力とは何を意味するのか、説明できますか。いわゆる暴力団が含まれるのは容易に想像できるでしょう。さらに、暴力団は企業の体裁を装うこともあります(暴力団関係企業、フロント企業などといわれます)。これらの企業は、文字通り、企業を装っているだけですから、もちろん反社会的勢力の中に含まれます。
中には自分たちが暴力団ではないと宣言しているような集団がありますが、実際は暴力団と同様のことをしている場合、これらの集団を反社会的勢力から外すということが適切でないことは明らかです。さらに暴力団ではないものの、暴力団を使うような人もいます(これらの人を暴力団関係者と呼びます)。こうした存在も反社会的勢力に含める方が妥当でしょう。
反社会的勢力という言葉の定義として、以上でお話したような主体の属性から機能的に考える方法を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、反社会的勢力を定義する場合、主体の属性からではなく、暴力的な要素を見せて不当な要求をするような場合を定義に含ませる方法もあります(ただし、例えばお金を返さない人に対して、多少大きな声を上げて返済を迫るような場合もあり、これらすべてを反社会的勢力としてしまうのは危険です)。
最近は、すぐに反社会的勢力とは分からないように活動しているケースも多々あります。冒頭の芸能事務所のケースも、そうした背景があったようです。それだけに反社会的勢力リスクを回避するのは非常に難しくなっています。
それでは一般企業が反社会的勢力と接触する可能性が生じるのはどんなときでしょうか。典型例として、繁華街などで店舗営業をしている企業が、反社会的勢力から、いわゆる「みかじめ料」を求められるケースがあります。また、借金を返済してくれなかったり、売掛金を払ってくれなかったりする取引先がある企業に対して「任せてくれれば、債務者から債権を回収してやる」といった甘い言葉をささやく反社会的勢力も見られます。
もちろん、不動産を貸す、車を売る、金融機関口座をつくるといった一般的なビジネスの相手先が反社会的勢力であるケースも考えられます。こうした一般的な取引であっても、相手が反社会的勢力であれば、社会的に指弾されてしまいます。
冒頭の芸能事務所のトラブルでも、タレントは通常の業務のようにイベントに参加したのですが、主催者が反社会的勢力であり、そこからギャラをもらっていたことから、厳しく社会的な責任を問われているのです。つまり基本的には、反社会的勢力とはすべての取引を行わないことが企業には求められています。
それでは、実際に反社会的勢力による被害をどのように防止するのがいいのでしょうか。参考になるのは政府の犯罪対策閣僚会議が、平成19年にまとめた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」です。その内容を参考に防止策を説明しましょう。
同指針では、次の5つを基本原則として挙げています。
○ 組織としての対応
○ 外部専門機関との連携
○ 取引を含めた一切の関係遮断
○ 有事における民事と刑事の法的対応
○ 裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力と付き合わないようにするためには、第一に、企業のトップメッセージとして「反社会的勢力と付き合わない」ことを宣言するのが大切です。このトップメッセージがあると、従業員は「トップメッセージとして、反社会的勢力の方とは付き合えないことになっています」と宣言して付き合いを断つことができるようになります。
反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖感を与えます。行動基準などを設けずに担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得ます。それを防止するには、企業の倫理規定、行動規範、社内規則などに明文の根拠を設け、担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役などの経営トップが宣言して、組織全体として対応しなくてはなりません。
次に、定期的に講習などを行って、トップメッセージの存在を含めて、反社会的勢力と付き合ってはならないという教育を行うことも肝要です。人は忘れる生き物ですので、定期的な講習を行うことは非常に重要なポイントとなります。
会社としての姿勢を対外的に示すために、取引先などに、反社会的勢力でないことの誓約書の提出を求めることがあります。今から10年くらい前、提出を求める企業が出てきた当初は、そんな内容の書面の提出を求めることは失礼ではないかと思われたときもありました。しかし、現在ではごく当たり前のことと思われているのでご安心ください。
当初は、取引の相手方が反社会的勢力ではないと思っていたが、後に判明するような場合もあります。取引を開始する場合の契約書に、いわゆる反社条項(契約の無催告解除、損害賠償請求など)を契約書に盛り込み、自衛策を講じる企業が増えてきています。これからは、必ず契約書の中にこうした反社条項を入れるべきでしょう。
内部統制システムを構築する一環として、内部通報制度や契約に関するデュー・デリジェントを行うこともあり、これにより、反社会的勢力との付き合いを避けたり、早期に発見するのを可能ならしめたりすることになります。
以上は平時の備えですが、不当要求があった際の有事、つまり反社会的勢力と相対する状況になった場合にはどうしたらいいのでしょうか。基本的には、第三者機関に相談して、対応しましょう。
つまり、基本原則にある外部専門機関との連携です。反社会的勢力のやり口は、比較的共通する部分が多く、巧妙な場合も多いので、過去に問題解決をしたことのある第三者機関の方が対応策に詳しいからです。外部専門機関としては、警察、弁護士のほか、暴力追放運動推進センター、企業防衛協議会、各種の暴力団排除協議会などがあります。
相手の言うことを聞かないと、報復をされるのではないかと心配される方も多いとは思います。しかし、妥協してはいけません。妥協をすると、そこから新しい抜け道を見つけてくる、これが反社会的勢力です。基本原則通りに、取引を含めた一切の関係を遮断することです。
そして万一の際には、基本原則にある民事と刑事の法的対応を厭(いと)わないことです。あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、刑事事件化に関して躊躇(ちゅうちょ)しないでください。刑事事件化については、被害が生じた場合、泣き寝入りせずに、不当な要求に屈しない姿勢を反社会的勢力に対して鮮明にするためにも大切です。さらなる不当要求による被害を防止する意味からも、積極的に被害届を提出しましょう。
裏取引や資金提供といった安易な手段で解決を図ろうというのは、完全な悪手です。毅然たる態度を取る相手であると反社会的勢力が感じない限り、彼らは、あなたの下にいつか必ずやってくる――そういうものだと考えて行動をしましょう。
執筆=入江 源太
麻布国際法律事務所 代表弁護士 平成10年検察官任官。カリフォルニア州立大学デービス校LLM、隼あすか法律事務所パートナー、パイオニア株式会社インハウス弁護士等を経て現在に至る。主な著作として、『カルテル規制とリニエンシー』(三協法規出版:2014年9月、編著)、『検証判例会社法』(財経詳報社:2017年11月)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話