
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
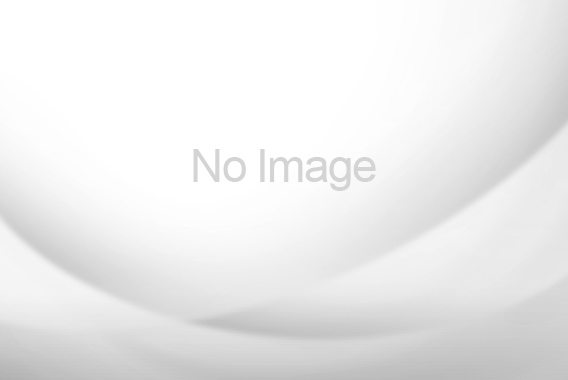 2019年4月1日から、多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現することを目的とした、いわゆる「働き方改革関連法」が順次施行されています。労働時間法制の見直しでは、(1)残業時間の上限規制、(2)中小企業にも月60時間を超える残業に関する割増賃金率の50パーセント引き上げを義務付けるなど、残業に着目した改正が行われています。
2019年4月1日から、多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現することを目的とした、いわゆる「働き方改革関連法」が順次施行されています。労働時間法制の見直しでは、(1)残業時間の上限規制、(2)中小企業にも月60時間を超える残業に関する割増賃金率の50パーセント引き上げを義務付けるなど、残業に着目した改正が行われています。
企業が労働者に残業をさせるには、労働者代表と書面による協定(三六協定)を締結し、所管の労働基準監督署に提出しなくてはなりません。ただ、書面を提出しても、締結相手である労働者代表に問題があると、同協定が無効となり、残業をさせたこと自体が違法となる可能性があります。また、労働者代表は、三六協定の締結だけでなく、就業規則の変更の際などにも選出が必要とされていますから、その選出は適正に実施しないとトラブルになりかねません。
実際、裁判に至ったケースを見てみましょう。2001年、最高裁判所で、従業員の親睦団体の代表者が自動的に労働者の過半数代表となって締結された三六協定について、無効とした原判決に対する上告が棄却され、同協定が無効であるとの判断が確定しました(最判平成13年6月22日労判808号11頁:トーコロ事件)。
また最近、下級審判決において、労働者代表として適正な手続きがなされているかが検討された事案も増えています。例えば、2017年、京都地方裁判所では、「当該事業所に属する従業員の過半数の意思に基づいて労働者代表が適法に選出されたことをうかがわせる事情は何ら認められない」として、使用者が主張した専門業務型裁量労働制について、その採用手続きが適法に行われたことを認められないと判断しています(京都地判平成29年4月27日労判1168号80頁)。
労働者代表の選出には要件があります。その要件を守って、適正に行うことが重要です。「働き方改革関連法」の施行を機会に、労働者代表に関して、理解を深めておきましょう。
まず「労働者代表」とは、労働基準法(以下:労基法)における「労働者の過半数を代表する者」を意味します。「過半数代表者」という表現が用いられることもあります。
前述の通り、使用者が「時間外労働・休日労働に関する協定(三六協定)」を締結する際、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者(労働者代表)を選出して、締結する必要があります(法36条1項)。また、就業規則の作成または変更をする場合に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者代表者の意見を聴かなければならないとされています(法90条1項)。そのほか、裁量労働制に関する労使協定を締結する場合(法32条の2以下)など、労働者代表者が必要とされる場面は多くあります。
労働者代表を適正に選出するには、2つの要件があります。「対象者」、「選出手続き」についてです。順に説明しましょう。
まずは「対象者」についてです。労働者代表は、労務管理に関して経営者と一体的な立場にある「管理監督者」(法41条2号)ではないことが要件になります(労働基準法施行規則(以下:施行規則)6条の2第1項第1号)。つまり、管理監督者に当たる可能性がある者は選出対象から外さなければなりません。管理監督者しかいない事業場では、例外的に管理監督者を労働者代表とすることが認められている場合があります(施行規則6条の2第2項)。
次に「選出手続き」は、労基法に規定する協定などを締結する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手などの方法でなければなりません。しかも、使用者の意向に基づき選出された者でないことが必要とされています(施行規則6条の2第1項第2号)。なお、「使用者の意向に基づき選出された者でないこと」との要件は、平成30年法改正により、加えられたものです。
ここで、「労働者の過半数を代表する者」における「労働者」の意味するところについては、注意が必要です。これは、管理監督者や非正規労働者、病欠・休職期間中である者、委託や請負契約の形をとる者を含む対象会社との関係で、労基法上の労働者性が認められる者などを含む、当該事業場の全労働者の過半数とされています。このため、全労働者数を適切に把握することが必要です。
経営者が確認するべき事項は、上記の2つの要件になります。労働者代表の選出に関し、各事業場の管理職に確認を一任することはせず、(1)管理監督者に該当しないこと、(2)選出手続きが適正に行われていることを、経営者自身や人事部が確認することが大切です。
また、既に労働者代表者が選任され、三六協定の締結などがされている場合でも、少なくとも次の事項を確認し、問題がある場合には、速やかに対応する必要があります。
(1)管理監督者が労働者代表となっていないか。
(2)選出手続きが、投票、挙手などのうち、どのような方法で実施されているか。
確認に当たっては、労働基準監督署に提出済みの書面、労働者に配布・掲示・回覧された資料を取り寄せて確認し、疑問がある場合には、労働代表者など関係者に対するインタビューなども実施し、実態を適切に把握する必要があります。
また、施行規則6条の2第3項では、「使用者は、労働者が労働者代表であること若しくは労働者代表になろうとしたこと又は労働者代表として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とされています。
分かりやすく説明すると、経営者の意に沿わない労働者が代表になろうとしたり、実際になって経営者の意に反した意見を述べたりしても、それが法律上、正当な行為であれば、冷遇してはならないということです。
さらに、平成30年法改正により、施行規則6条の2第4項として、「使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない」との規定が追加されました。
厚生労働省が公表している、改正労働基準法に関するQ&Aでは、この「必要な配慮」には、例えば、労働者代表が労働者の意見集約などを行うに当たって必要となる事務機器(イントラネットや社内メールを含む)や事務スペースの提供を行うことが含まれるとされています。従って、労働者代表からこれらの利用について要請があった場合に、使用者が合理的な理由なく拒むことは違法と判断される可能性があるため、対応に当たっては注意が必要です。
執筆=渡邊 涼介
光和総合法律事務所 弁護士 2007年弁護士登録。元総務省総合通信基盤局専門職。2023年4月から「プライバシー・サイバーセキュリティと企業法務」を法律のひろば(ぎょうせい)で連載。主な著作として、『データ利活用とプライバシー・個人情報保護〔第2版〕』(青林書院、2023)がある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話