
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
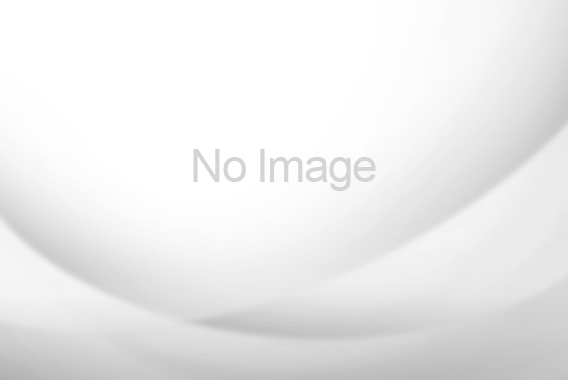
年末調整は、1年間の給与総額が確定する年末に、源泉徴収した税額の年間合計額とその年に収めるべき税額との過不足額を算出し、差額を徴収または還付して清算する手続きです。
大部分の給与所得者は、この年末調整によってその年の所得税の納付が完了することになるため、年末調整は非常に大切な手続きです。
1年を通じて勤務している人、年の中途で就職して年末まで勤務している人、死亡により退職した人、12月に給与支給を受けた後に退職した人などが対象となります。
年末調整の対象とならないのは、年の途中で退職した人、給与収入が2000万円を超える人、2カ所から給与を受けている人で、他の給与の支払者に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人などです。
年末調整のスケジュール、手順などは次の通りです。年末年始は事務量も増えるため、担当者と従業員の負担が大きくならないよう早めの準備を行い、万全の体制で乗り切りましょう。
| 時 期 | 手 順 | 作業等 |
| 10月中旬~11月下旬 | 各種申告書の配布・受理 ※令和6年分の扶養控除等(異動)申告書の配布・受理を併せて行うと効率的です。 | 従業員に次の申告書を配布・記載済みのものを回収し、従業員の方に適用される控除の種類や控除額を確認します。 ①扶養控除等(異動)申告書(令和5年分) ②保険料控除申告書 ③基礎控除申告書 兼 配偶者等控除申告書兼 所得 金額調整控除申告書 ④住宅借入金等特別控除申告書 |
| 11月下旬~12月下旬 | 年調年税額の計算・過不足額の計算と清算 | 従業員の方の所得控除と税額控除の額を確認した後、次の手順で年調年税額の計算及び過不足額の計算と清算を行います。 ①本年分の給与の金額と徴収税額の集計 ②給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後) の計算 ③扶養控除及び障害者等の控除額の合計額 の計算 ④所得控除額の合計額の計算 ⑤年間給与に係る税額(年調年税額)の計算 ⑥過不足額の計算と清算 |
| 12月下旬~1月中旬 | 過納額の還付、不足額の徴収・納付 | 清算の結果を、年末調整をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)に記載した上で、徴収税額を納付します。(納付する税額がない場合でも、給与支給額等を記載して提出する必要があります。) 納期限:令和6年1月10日(水) 納期の特例の承認を受けている場合は、 令和6年1月22日(月)です。 |
| 1月上旬~1月31日 | 源泉徴収票等の作成・提出 | 令和6年1月31日(水)までに次の書類を交付及び提出します。 ①源泉徴収票(従業員に交付) ②源泉徴収票及び法定調書合計表 (源泉徴収義務者の所轄税務署に提出) ③給与支払報告書及び給与支払報告書(総括表) (従業員の住所地の市区町村に提出) |
国税庁のパンフレットを基に筆者作成
2023年分の年末調整に関する変更点は、①住宅ローン控除区分の追加・変更、②非居住者扶養親族に係る扶養控除の適用範囲の変更、③扶養控除申告書に「退職手当を有する配偶者・扶養親族」および「寡婦又はひとり親」欄の追加の3点です。
①住宅ローン控除区分の追加・変更
住宅ローン控除は、2022年に控除率が1%から0.7%へ引き下げられました。2023年分の年末調整から、1%の控除適用者に加え0.7%の控除適用者が登場します。
住宅ローン控除の計算は複雑で計算ミスが起こりやすいので、年末調整が始まる前に、2022年に住宅を購入した人など住宅ローン控除の適用率が0.7%となる従業員がいるか、確認しておくとよいでしょう。
②非居住者扶養親族に係る扶養控除の適用範囲の変更
2022年まで扶養控除の対象となっていた人のうち、年齢が30歳以上70歳未満の非居住者の人で、1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった人(以下「留学生」といいます)、2.障がい者、3.所得者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人(以下「38万円以上の送金を受けている人」といいます)以外の人については、扶養控除の対象外となりました。
この改正は、2023年1月1日から発生する所得税に適用されているため、2022年の年末調整の際に従業員から提出された「令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載内容に変更がないか、従業員に確認しておくといいでしょう。
〇非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用要件
| 16歳以上 30歳未満 | 扶養控除の対象 | |
| 30歳以上 70歳未満 | 扶養控除の対象 | 扶養控除の対象外 |
| ①留学生 ②障がい者 ③38万円以上の送金を受けている人 | 左記以外の人 | |
| 70歳以上 | 扶養控除の対象 | |
国税庁のパンフレットを基本に筆者作成
上記該当者が扶養控除の適用を受けるためには、扶養控除等(異動)申告書の提出時または年末調整時に次の書類を確認する必要があるため、併せて従業員に周知しましょう。
〇非居住者である扶養控除に係る確認書類
| 非居住者である扶養親族の年齢の区分 | 扶養控除等申告書の提出時に確認する書類 | 年末調整時に確認する書類 | |
| 16歳以上30歳未満 | 親族関係書類 | 送金関係書類 | |
| 30歳以上 70歳未満 | ①留学生 | 親族関係書類・留学ビザ等書類 | 送金関係書類 |
| ②障がい者 | 親族関係書類 | 送金関係書類 | |
| ③38万円以上送金を受けている人 | 親族関係書類 | 38万円送金書類 | |
| 上記①~③以外の人 | 扶養控除の対象外 | ||
| 70歳以上 | 親族関係書類 | 送金関係書類 | |
国税庁のパンフレットを基本に筆者作成
注)「親族関係書類」「留学ビザ等書類」「送金関係書類」および「38万円送金書類」の詳細については、国税庁ホームページに掲載されている「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除Q&A(源泉徴収関係)」をご確認ください
③扶養控除等(異動)申告書の「住民税に関する事項」に「退職手当を有する配偶者・扶養親族」および「寡婦又はひとり親」欄が追加され、2023年分から様式が変更になっています。
所得税計算においては、合計所得金額に退職所得も含みますが、住民税の計算では合計所得金額に退職所得は含まれません。したがって、配偶者が2023年中に退職した場合、退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下であれば住民税で配偶者控除を受けることができます。また、2021年から寡婦の場合は26万円、ひとり親の場合は30万円が控除できます。
この欄は、住民税に関する控除が適切に適用されていないケースがあったため追加されたものです。該当する人の記入漏れがないよう周知が必要です。
2023年分の年末調整が終わると、2024年分の源泉徴収事務が開始されます。2024年分は扶養控除申告書の記載事項の簡略化などが予定されているため、年末に慌てないよう、国税庁ホームページなどを随時チェックしておくとよいでしょう。
執筆=松田敬一
租税調査研究会主任研究員・税理士。東京国税局課税第一部資料調査第一課、同総務課課長補佐、藤沢税務署総務課長、相模原税務署副署長、署特別国税調査官(法人・開発・総合)、東京国税局調査第二部統括官、鎌倉税務署長を経て2023年7月退職。同年8月税理士登録。
監修・編集=宮口貴志
一般社団法人租税調査研究会専務理事・事務局長。
株式会社ZEIKENメディアプラス代表取締役、TAXジャーナリスト、会計事務所ウオッチャーとして活動。元税金専門紙及び税理士業界紙の編集長。
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ