
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
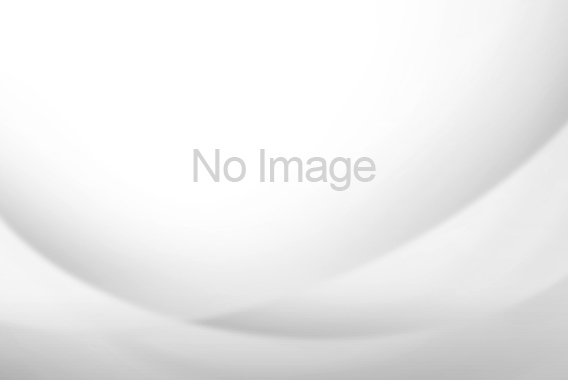 会社と契約書を交わす際、記名欄に「株式会社〇〇代表取締役△△」などと、会社名に続けて代表取締役名を記載するのが一般です。これは、代表取締役が承認した契約であると示すものです。
会社と契約書を交わす際、記名欄に「株式会社〇〇代表取締役△△」などと、会社名に続けて代表取締役名を記載するのが一般です。これは、代表取締役が承認した契約であると示すものです。
この代表取締役名ですが、上記のように「代表取締役△△」と記載する場合がある他、会社によっては「代表取締役社長△△」と記載したり、「代表取締役CEO△△」と記載したりするところがあります。会社によっては、契約書に代表取締役名を記載せず、「株式会社〇〇常務取締役□□」「株式会社〇〇営業部長××」などと記載するケースもあると思います。
単なる「代表取締役」と「代表取締役社長」などの立場にある者とでは、権限に違いがあるのでしょうか。また、「常務取締役」「営業部長」などの立場にある者は、どのような権限を有しているのでしょうか。今回は、こうした疑問について、取締役会を置いている会社を念頭に整理し解説します(指名委員会等設置会社を除きます)。
まず、会社の役職員に対するさまざまな呼称、すなわち「代表取締役」「取締役」「使用人」「会長」「社長」「副社長」「専務」「常務」「部長」「課長」「CEO」などについて整理してみましょう。
これらのうち、株式会社の運営・管理のルールなどを定めている会社法は、「代表取締役」「取締役」「使用人」についてのみ、その有する権限などを規定しています。残りはすべて、慣習などに基づき会社内部で定める「肩書」に過ぎません。そして、会社法の規定する「代表取締役」などと会社内部の肩書は、必ずしもすべての会社で相関関係が認められるものではありません。
例えば社長という肩書は、通常は代表取締役に付与するでしょうが、代表取締役が必ず社長であるかというと、そうとは限りません。複数の代表取締役がいる会社では、会社内部で序列をつけるために、それぞれに社長、副社長、専務、常務などの肩書を付与する場合があります。つまり、代表取締役であっても社長ではない者、例えば代表取締役副社長や代表取締役専務なども存在するわけです。
従って、契約書などに記載される一定の立場にある者の法律上の権限を確認するためには、「肩書」にとらわれることなく、会社法の規定する「代表取締役」「取締役」「使用人」のいずれの立場にある者かの見極めが重要です。「代表取締役」と「取締役」は就任すると登記されますから、登記によってその地位を確認できます。
代表取締役とはどういう権限を有しているでしょうか。代表取締役は、取締役の中から、取締役会によって選定されます。代表取締役の権限は、会社法の規定によれば、株式会社の業務を執行し、対外的には会社を代表するとされています。代表するとは、会社のためにした行為の効果が会社に及ぶということです。
こうした権限は、「株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為」に及びます。この「一切の権限」、すなわち包括的な権限を有する点が代表取締役の大きな特徴です。代表取締役が2人以上いるときは、各自が会社を代表します。
代表取締役の包括的な権限は、会社の定款や取締役会規則により制限できます。例えば、代表取締役社長と代表取締役専務とで決裁権限に差異を設けられます。しかし、このような内部の制限を知らない取引相手などの第三者に対して、会社は権限の制限を理由に、当該代表取締役の行為による効果を否定して責任を免れることはできません。
株式会社と契約締結などの取引を行う際には、まず、肩書ではなく代表取締役名で行われる取引、すなわち代表取締役が認めた取引であると確認することがポイントです。もちろん、代表取締役名ではなく取締役や使用人の名を連ねて契約を結ぶことも可能です。この場合に注意すべきは取締役や使用人の権限です。それについて以下に解説します。
会社法は代表取締役の他に、「取締役」と「使用人」について規定を置いています。平たく言えば「取締役」は経営者であり、「使用人」は会社の指示に基づき業務を行う者です。
少し詳しく説明すると、「取締役」は、株主総会によって選任され、会社と委任契約を結び、取締役会という機関(株式会社の運営・管理のために会社法が規定している会議体など)の構成員となって会社の経営に携わります。これに対し「使用人」は、会社と労働契約(雇用契約)を結び、会社の指示に基づいて業務を行う者で、労働法上の「労働者」に位置付けられるのが一般です。まとめると以下のようになります。
●取締役と使用人
| 会社との関係 | 法律上の位置付け | 職 務 | |
| 取締役 | 委任契約 | 機関(取締役会)の構成員 | 会社の経営 |
| 使用人 | 労働契約 | 労働者 | 会社の指示した業務 |
それでは、取締役はどのような権限を持っているのでしょうか。代表取締役とは異なり、単なる取締役(「平取締役」と呼ぶこともあります)は、取締役会に出席して会社の経営に関する重要事項の「決定」に参画しますが、その決定に基づく業務の「執行」権限は有していません。
しかし、取締役会は取締役の中から「業務執行取締役」を選定でき、この業務執行取締役は、取締役会から指定された範囲で会社の業務を執行します。一定の範囲内で、会社を代表する権限を与えられる場合も少なくありません。営業・経理など部門ごとに専務・常務などの肩書を付与する、会社によっては営業部長・経理部長などの肩書を付与し、担当業務の執行取締役を定めているところもあります。
専務・常務といった肩書を代表取締役に付与している会社もありますから、繰り返しとなりますが、こうした肩書ではなくその取締役が代表取締役であるのか、業務執行取締役にとどまるのかの確認が重要です。取引相手の決裁者が業務執行取締役にとどまる場合、その業務執行範囲は取締役会から指定された範囲となりますから、その契約締結が業務執行範囲に入っているのか、相手会社に確認すると間違いが生じないでしょう。
同様に、使用人の権限についても解説しておきましょう。取締役でもない使用人が、契約締結などの取引、すなわち対外的な業務を執行できるのでしょうか。
使用人(労働者)については、労働法が多くの規定を置いていますが、会社法は「ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人」の対外的な権限について、規定を置いています。聞き慣れない名称かもしれませんが、要は、営業・経理などの部門についてまとめて会社から任されている(委任されている)使用人を念頭に置いた規定です。「営業部長」「経理課長」といった肩書が付与されている使用人を想定するとよいでしょう。
こうした使用人について、会社法は「任された事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する」旨規定しています。そして、会社が内部的にこうした権限を制限していても、善意の第三者には対抗できない(当該制限を理由に当該使用人の行為による責任を免れることはできない)と規定しています。
この規定によれば、例えば「営業部長」が有しているのは、営業に関する一切の裁判外の行為をする権限であって、経理上の契約を結ぶ権限などは有していないこととなります。つまり「営業部長」の肩書を持つ使用人が、営業に関係しない契約の決裁者として名前を連ねている場合、その契約は効力を生じないおそれがあるので注意が必要です。
「営業部長」が営業に関する契約を結ぶ場合でも、社内的に当該契約締結権限が制限されているケースがあります。こうしたケースでは、その制限を知らない取引相手は保護されますが、無用なトラブルを避けるためには、取引相手の決裁者が使用人にとどまる場合は、念のため相手会社に決裁者の権限を確認しておくと安心です。
執筆=植松 勉
日比谷T&Y法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)、平成8年弁護士登録。東京弁護士会法制委員会商事法制部会部会長、東京弁護士会会社法部副部長、平成28~30年司法試験・司法試験予備試験考査委員(商法)、令和2年司法試験予備試験考査委員(商法)。主な著書は、『会社役員 法務・税務の原則と例外-令和3年3月施行 改正会社法対応-』(編著、新日本法規出版、令和3年)、『最新 事業承継対策の法務と税務』(共著、日本法令、令和2年)など多数。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話