
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
このたびの令和6年能登半島地震の影響により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
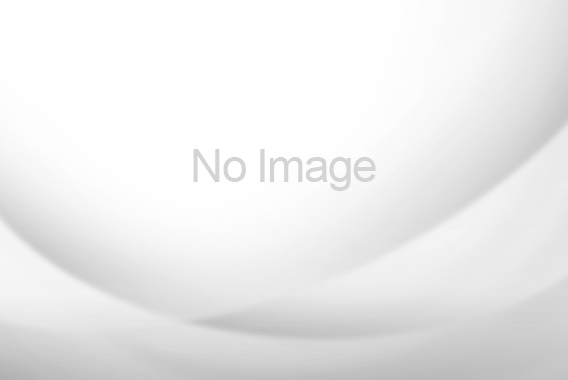
2024年1月1日に発生した能登半島地震は大きな被害をもたらし、今なお多くの被災者の方が困難な避難生活を強いられています。地震関連だけでなく、大雨や台風など、繰り返しさまざまな災害に見舞われ、その対策や復興支援は国民的な課題といえます。
こうした課題は個人だけでなく、企業も同様に抱えています。近年は大企業を中心に、災害時でも事業を継続できるようBCP(Business Continuity Planning:災害などの緊急事態における企業や団体の事業継続計画)の策定や導入が進んでいます。
もっとも、BCPを策定している企業は現時点では少数派です。帝国データバンクが2023年5月に実施した「事業継続計画(BCP)に対する意識調査(2023年)」によると、BCP策定率は18.4%にすぎません。備えのない企業が被災した場合、事業を継続できない可能性が高くなります。そうなると、従業員の雇用の維持が困難になるなど労使関係上の問題が浮上し、被災者の生活再建も難しくなるでしょう。
そこで、今回と次回の2回に分けて、災害時において事業主(使用者)が従業員(労働者)に対して守らなければならない事項などについて紹介します。能登半島地震後、厚生労働省は「令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A」(以下:Q&A)を公開しています。この中で特に重要な点を解説しますが、ぜひ全文を一読することをお勧めします。今回は、休業手当について取り上げます。
災害の影響により事業主が従業員を休業させる場合、問題となるのは、休業期間中の従業員に休業手当を支払う必要があるのか、ということです。
労働基準法26条では、労働者の最低生活を保障するため、使用者(事業主)が労働者(従業員)を休業させる場合、それが「使用者の責に帰すべき事由」によるときには、労働者に対し平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない、と定めています。
「使用者の責に帰すべき事由」とは、労働者の最低生活を保障するという本条の趣旨から、使用者に故意または過失がある場合だけではなく、広く使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むと解されています(最高裁昭和62年7月17日判決、ノースウェスト航空事件)。これについて以下の3つのケースに分けて考えます。
●ケース1:災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、従業員を休業させる場合
休業の原因は通常、事業主の関与の範囲外にあり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けられなかったものといえ、不可抗力によるものと考えられます。したがってこの場合は、「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当せず、事業主は従業員に休業手当を支払う必要はありません。
●ケース2:災害により事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないものの、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入れ、製品の納入などが不可能となり従業員を休業させる場合
この場合、災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けていないため、直ちに不可抗力によるものとはいえません。むしろ取引先、原材料の仕入れ、製品の納入などに関する事情は、基本的に使用者側に起因する経営、管理上の障害に該当するものといえます。したがってこの場合は、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当し、事業主は従業員に休業手当を支払う必要があります。
ただし、休業について、①その原因が事業の外部により発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けられない事故であることの2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しません。
このような場合、事業主は従業員に休業手当を支払う必要はありません。上記①②の要件を満たすかは、ⅰ 取引先への依存の程度、ⅱ 輸送経路の状況、ⅲ 他の代替手段の可能性、ⅳ 災害発生からの期間、ⅴ 使用者としての休業回避のための具体的努力などを総合的に勘案して判断されます(Q&AのA1-5)。
●ケース3:事業主が、これまで労働契約、就業規則、労使慣行などに基づき、使用者の責に帰すべき休業のみならず、天災地変などの不可抗力による休業についても、休業期間中、賃金、手当などを支払うこととしていたにもかかわらず、今回は災害に伴う休業について賃金、手当などを支払わない場合
このケースは、労働条件の不利益変更に該当します。事業主が、労働条件の不利益変更を行うには、従業員との合意など労働契約や就業規則などそれぞれについて適法な変更手続きを取らずに、賃金、手当などの取り扱いを変更する(支払わないことにする)ことは許されません。
被災により事業を継続できず、労働者を休業させる場合、休業手当の支払いに関する取り扱いは上記の通りです。これらを踏まえ、労使がよく話し合って、できる限り従業員の不利益を回避するように努めましょう。
その際、国の支援策についても積極的に活用することが望まれます。
Q&Aでは、災害時における国の支援策として、雇用保険制度の特例措置と雇用調整助成金が紹介されています。
まず、雇用保険制度の特例措置の内容は、以下の通りです。
災害救助法の適用地域内に所在地を置く事務所が災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職した従業員について、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、雇用保険の基本手当を受給できます。また、激甚災害法の指定地域に所在する事業所が災害で休業したことにより、被保険者が休業して賃金を受けられない場合についても、基本給を受給できます。ただし、この適用を受けるには、雇用保険の被保険者期間が6カ月以上などの受給要件を満たしている必要があります。
次に、雇用調整助成金の内容は、以下の通りです。
景気の変動、産業構造の変化その他の「経済上の理由」により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する従業員を対象に休業等を実施した上、休業手当等の支払いを行い雇用の維持を図る事業主に対し、休業手当などの一部を助成するものです。
事故または災害により施設などが被害を受けた場合は「経済上の理由」に該当しないものの、災害に伴い、ⅰ 取引先が被災して原材料や商品などの取引ができない、ⅱ 交通手段の途絶により来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない、ⅲ 電気・水道・ガスなどの供給停止や通信の途絶により営業ができない、ⅳ 風評被害により観光客が減少した、ⅴ 施設、設備などの修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能などの事情により経営環境が悪化した場合は「経済上の理由」に該当し、雇用調整助成金の対象となる可能性があります。
なお、雇用調整助成金は、前述した労基法26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するか否かによって、その取り扱いが異なることはありません。
いずれの支援策についても、詳細についての問い合わせ先は、最寄りの都道府県労働局またはハローワークとなります。
執筆=上野 真裕
中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。平成15年弁護士登録。小宮法律事務所(平成15年~平成19年)を経て、現在に至る。令和2年中小企業診断士登録。主な著作として、「退職金の減額・廃止をめぐって」「年金の減額・廃止をめぐって」(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話