
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
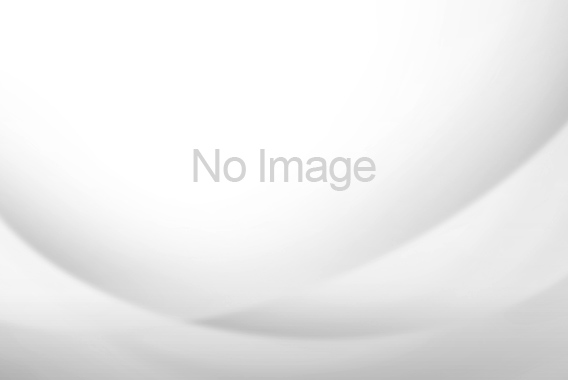
前編では2021年1月から3月末までに施行される予定の改正法令について解説しました。今回の後編では2021年4月以降に施行される予定の改正法令についてご紹介します。さらに、今回は触れませんが、介護保険法、割賦販売法についても2021年中に改正が予定されています。これらの施行日は未定ですが、関係する業務を取り扱っている企業・団体は注意を払っていただければと思います。
改正の概要
・高齢者の就業機会の確保・就業の促進
65歳から70歳までの高年齢者の就業機会を確保する措置(定年引き上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講じることが企業の努力義務として定められます。
・複数就業者などに関する公表義務
労働者数300人超の大企業は、中途採用者の割合を定期的に公表することが義務付けられます。
改正による影響、注意点
これらと関連して、雇用保険制度において、65歳までの雇用保険措置の進展などを踏まえて高年齢雇用継続給付を令和7年度から縮小するとともに、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の導入などに対する支援を雇用安定事業に位置付ける、とされています。
改正の概要
・複数意匠一括出願制度の導入
意匠ごとに願書を作成するのではなく、複数の意匠をまとめた願書も作成できるようになります。
・物品区分の扱いの見直し
物品区分表が廃止され、同表の中から1つの区分を選択するのではなく、経済産業省令に設けられる基準に従った「一意匠」として出願することになります。
・手続救済規定の拡充
指定期間の経過後であっても、その延長を請求できるようになります。優先期間の経過後であっても、正当な理由があれば、優先権の主張を伴う出願ができるようになります。また、優先権証明書の提出がされなかったとき、特許庁長官は出願人に対して、注意喚起のための通知をしなければならないことになります。
改正による影響、注意点
従前よりも意匠登録が容易となるため、製品デザインなどを扱う企業にとっては有利な改正といえます。
改正の概要
既に施行済み(2020年4月)ですが、中小企業には2021年4月1日から適用されます。
・不合理な待遇差の禁止
基本給や賞与、各種手当などのあらゆる待遇について、同一企業内での正社員と非正規労働者との間における不合理な待遇差が禁止されます。これについては、ガイドラインが公表されており、どのような待遇差が不合理と考えられるか、例示されています。
・労働者への待遇に関する説明義務の強化
非正規労働者から正社員との待遇差の内容や理由などについて説明を求められた場合、事業主は説明義務を負うことになります。労働者からの納得を得られるよう、分かりやすい説明に努める必要があるでしょう。
・行政による事業主への助言・指導などや裁判外紛争解決手続(ADR)の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続を行うこととされています。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても対象となります。
改正による影響、注意点
パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇用している中小企業においては、自社の状況が改正後の法の内容に沿ったものであるか否か、点検が必要です。専門家と適宜相談しながら、施行日までに必要な準備を進める必要があります。
※このほか、2021年4月1日には労働者派遣法や厚生年金保険法の一部改正法令も施行されますが、本記事では割愛いたします(前者は派遣元企業、後者は国民年金に加入している外国人が対象です)
※改正法自体は2020年に成立していますが、施行時期は2021年後半~2022年前半とされています
改正の概要
・不適正な方法による利用の禁止
個人情報の「利用」全般に関する規制が設けられ、違法・不当な行為を助長・誘発する恐れがある方法による利用は禁止されます。
・仮名加工情報の創設
仮名加工情報(個人情報に含まれる情報の一部削除などにより、他の情報との照合によらなければ特定の個人を識別できないように加工した情報)が創設され、取得時の目的以外の目的での使用もできるようになります。
・漏えい発生時の対応
情報漏えいなどが発生し、個人の権利利益を害する恐れがある場合、事業者は、国への報告と本人への通知が義務付けられます。
・オプトアウトによる第三者提供の制限
不正取得された個人データと他の事業者からオプトアウトにより提供された個人データについても、オプトアウト(事後的に本人からの求めに応じて停止することを条件に、本人の事前同意なく第三者提供すること)が制限されます。
・個人関連情報の創設
提供元では個人データに該当しないものの提供先では該当することが想定される情報の第三者提供について、提供先で本人の同意が得られていることの確認が提供元に義務付けられます。
・本人によるコントロールの拡充
6カ月以内に消去する短期保存データも、保有個人データとして開示・利用停止の請求などの対象となります。保有個人データの開示方法について、電磁的記録の提供についても本人が指示できるようになります。
個人データの授受に関する第三者提供記録についても、本人は開示請求できるようになります。利用停止・消去・第三者提供の停止の請求ができる場合として、個人の権利利益または正当な利益が害される恐れがある場合(事業者において利用する必要がなくなった場合、重大な漏えいなどが生じた場合)などが追加されます。
・認定個人情報保護団体の要件緩和
企業の特定の部門を対象とする団体も、認定され得ることになります。
・罰則の強化
個人情報保護委員会による命令違反や同委員会への虚偽報告などがあった場合の法定刑が引き上げられます。特に、同委員会による命令違反や個人情報データベースなど不正提供罪の罰金については、法人に対する罰金の上限が大幅に引き上げられます(50万円または30万円以下の罰金から1億円に)。
・法の域外適用、越境移転
罰則により担保される報告徴収・命令の対象に、日本国内にある者に係る個人情報などを取り扱う外国事業者が追加されます。外国にある第三者に個人データを提供する際、当該外国での個人情報保護制度などの情報を本人に提供することが義務付けられます。
改正による影響、注意点
昨今、本人が予期しない利用方法で不意打ち的に個人情報を利用し、個人情報保護委員会から指導を受ける事例などが散見されます。改正内容は多岐にわたりますが、個人情報保護の重要性によく留意しながら、適正な個人データの利活用を図っていく必要があるでしょう。
執筆=福原 竜一
虎ノ門カレッジ法律事務所 弁護士 2009年弁護士登録。企業法務及び相続法務を中心業務とする。主な著作として、「実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパクトガイド」(編著:2019年10月:ぎょうせい)がある。2019年8月よりWEBサイト「弁護士による食品・飲食業界のための法律相談」を開設し、食に関わる企業の支援に力を入れている。https://food-houmu.jp/
【T】
弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話