
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
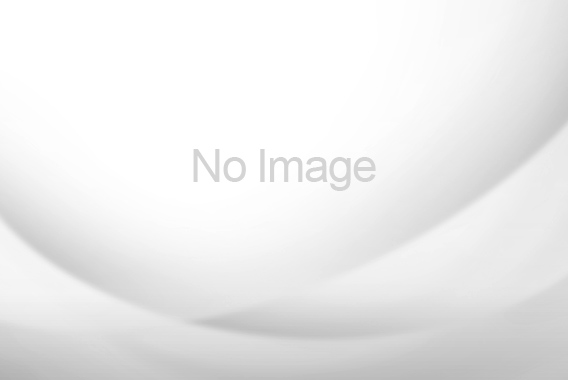
「ウェルビーイング」という言葉を耳にする機会が増えています。厚生労働省は、ウェルビーイングを「個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念」と説明しています。このウェルビーイングは日本社会にかなり浸透してきていると感じます。
一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会(NGK)では「ゴルフ界はウェルビーイングな社会の実現に貢献する!」を中長期ビジョンに掲げるなど、ゴルフ業界も例外ではありません。ウェルビーイングをひもとくと、ゴルフの本質とイコールであると分かります。今回はゴルフを通じてウェルビーイングを考えてみたいと思います。
慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の教授や、武蔵野大学ウェルビーイング学部の教授兼学部長を務める前野隆司さんは、日本の「ウェルビーイング」「幸福学(well-being study)」の第一人者です。前野教授は幸福学の基礎として、幸せになるには「やってみよう」「ありがとう」「なんとかなる」、そして「ありのままに」の4つの因子が大切であると提言しています。この「幸せの4つの因子」はゴルフで実感し、学べます。それぞれを見てみましょう。
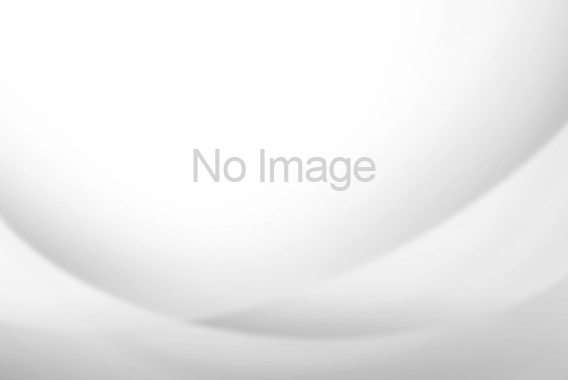
前野教授の研究グループが導き出した「幸せの4つの因子」(出典:日本電信電話株式会社「Sustainable Smart City Partner Program」より)
ビジネスパーソンの中には、接待ゴルフに駆り出された、上司に誘われて仕方なく、と渋々ゴルフを始める人も少なくないと思います。そして最初は渋々だったものの、やってみたらゴルフの楽しさにハマり、100を切りたい!社内コンペで優勝したい!と、目標に向かって頑張っている人もまた少なくないと思います。
ビジネスシーンにおいても、乗り気でないプロジェクトを任されたり、やりたくない仕事を命じられたりと、渋々やらざるを得ない場合もあるでしょう。しかしどんな仕事でも「やってみよう」精神で取り組めば、必ず自己実現と成長につながると思います。
「やってみよう」は、ゴルフにおいても仕事においても必要な、主体性やチャレンジ精神、上達や成長意欲そのものであり、米国の心理学者マズローが提唱したことでも知られている欲求5段階説の最上位「自己実現欲求」を満たす原動力となります。人は目標を掲げ、「なりたい自分」をめざして取り組み、成長を自覚したときに"幸せ"と感じるはずです。例えば、ゴルフで掲げる目標は誰もが必ずしも達成できるとは限りませんが、それでも「やってみよう」と前向きにチャレンジして、チャレンジ前よりも確実に成長し、それにつれて心身も充実するでしょう。こうした自己実現や成長こそが幸せの原点ではないでしょうか。
自己実現欲求に関しては、モチベーションの維持というテーマで、本連載第68回「ゴルフのモチベーションを維持する5つの工夫」でお伝えしています。
ゴルフでは、バンカーショットの後は砂をならす、ショットで削り取った芝生(ターフ)を元に戻し、砂を埋めて修復(目土)する、グリーン上にできたボールマーク(ボールの落下でできたくぼみ)を修復するといった行動を取ります。これらの行動はマナーとしてゴルファーに浸透しています。マナーは自分のためではなく、後続組のプレーヤーが気持ちよく、かつベストなプレーができるようにといった配慮から行うものです。
つまり「相手ファースト」(利他主義)です。そして自分自身も、前のプレーヤーが同様の行動をしてくれているからこそ気持ちよくプレーができます。このように感謝の連鎖があるのがゴルフの特長の1つといえるでしょう。記憶に新しい2024パリ五輪では、多くの競技で対戦相手をたたえ合う姿が見られました。見ていてとてもすがすがしい気持ちになります。ゴルフにおいても、競い合っている相手を応援したり、ナイスプレーを喜んだりといった要素があります。これらは自身のプレーにもプラスに働くとアスリートは本能的に知っているからでしょう。
「相手ファースト」に関しては、本連載第43回「スコアをアップさせる"相手ファースト"思考」で述べています。相手の幸せを応援したり喜び合ったりする「相手ファースト」が、巡り巡って自分に返ってくるとゴルフは教えてくれます。
ショットを曲げて林に打ち込んだ、池やバンカーに落としたといったミスは、ゴルフにつきものです。そんなときも、落ち込んだりくさったりせず、「なんとかなる」と、そこからのショットを前向きに楽しむことができれば、よい結果をもたらす確率はグンと上がります。また、結果につながらなくともストレスが少なく、気持ちよくプレー時間を過ごせるでしょう。このように「なんとかなる」という楽観主義やプラス思考は、ゴルフではとても大切です。
本連載第21回「悲観的に準備し、楽観的に行動すればゴルフは易しい」では、"慎重さ"と"楽観主義"の共存が大事であると述べました。コース戦略を練るときは、ボールは曲がらないだろうと楽観的に考えるのではなく、曲がるかも......と悲観的に考え、ボールが曲がってもOBやバンカー、池といったリスクは回避できるように攻めるルートを決めていきます。しかし、いざショットを打つときには「必ずできる」と楽観的に考え、アドレスに入ります。たとえミスショットをしたとしても、「なんとかなる」と次のプレーに切り替えて前向きに楽しみましょう。このような実践の繰り返しが、結果的によい結果をもたらすとゴルフから学べます。
「コースはあるがままにプレーせよ」。これはゴルフ規則(第3章 規則8)にうたわれている大原則です。例えば、ショットの邪魔になるからと木の枝をへし折ったり、ボールの後ろの盛り上がった地面をならしたりと、自分の打ちやすいようにコースに手を加えることをルールで禁止しているのです。不運な状況、逆境にあるとき、(キャディーのアドバイスを受けられるとしても)ゴルファーは1人でそれを打開しなければいけません。自身のベストを尽くして目の前の困難を乗り越えられたとき、自己肯定感はいっそう高まるでしょう。これも、ゴルフを通じて養えます。
不運でなくとも、他人に影響されて失敗を招くというケースもあります。同伴プレーヤーがショートホールのティーショットをアイアンで打つのを目の当たりにし、自分の飛距離ではウッドやユーティリティーで打つべきところ見えを張り、アイアンで打って案の定、グリーンに届かないといった経験はありませんか。他人の影響で自分を見失うとクラブ選択を誤りがちになります。非力で距離の出ないゴルファーでも飛距離に応じた戦略を練り、飛距離に応じたクラブを選択し、最終的にアプローチやパッティングで勝負すれば飛ばし屋に勝つことも十分可能です。つまり"自分軸"をしっかり持ち、"自分らしく"プレーすれば、よい結果を得られるのだとゴルフは教えてくれます。
4つの因子に分けて細かく見てきたように、ゴルフはウェルビーイングを実感し、学べる最良のスポーツではないでしょうか。また、ゴルフは社交的でコミュニティー形成に効果的なだけでなく、非日常を楽しみ、ボールを飛ばしたり、ターゲットに近づけたりする爽快感で気分をリフレッシュし、翌日からの活力を高められますから、ビジネスパーソンにはうってつけのスポーツだと思います。
私が出席した前野教授の講演で、幸福度と仕事のパフォーマンスについて示されたデータを最後に紹介しておきましょう。「幸福度が高い社員の創造性は3倍、生産性は31%高くなる。また、欠勤率は41%、離職率は59%、業務上の事故は70%減少する」そうです。ゴルフ好きにとっては、ゴルフができることそのものがウェルビーイングなのかもしれません。ゴルフを楽しんで幸福度を高める「ウェルビーイングゴルフ」で、仕事の生産性も高められれば、ゴルフに携わる者としてうれしい限りです。
執筆=小森 剛(ゴルフハウス湘南)
有限会社ゴルフハウス湘南の代表取締役。「ゴルフと健康との融合」がテーマのゴルフスクールを神奈川県内で8カ所運営する。自らレッスン活動を行う傍ら、執筆や講演活動も行う。大手コンサルティング会社のゴルフ練習場活性化プロジェクトにも参画。著書に『仕事がデキる人はなぜ、ゴルフがうまいのか?』がある。
【T】
ゴルフエッセー「耳と耳のあいだ」