
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
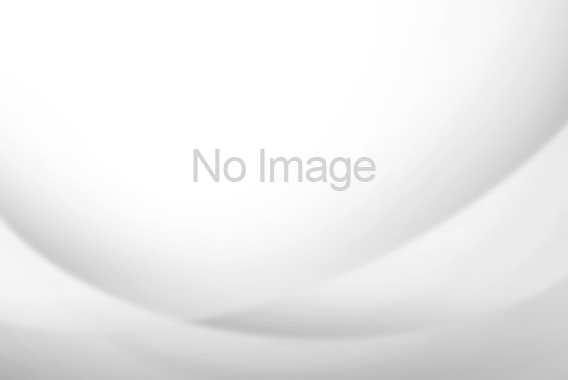 ゴルフ歴は長いものの、ラウンド中のクラブ選択やコースの攻め方を自分では決められず、キャディーさんや同伴している先輩ゴルファーの指示がないと判断できないゴルファーがいるようです。そのようなプレースタイルでは、ゴルフの面白さを半分も感じられないのではと思います。
ゴルフ歴は長いものの、ラウンド中のクラブ選択やコースの攻め方を自分では決められず、キャディーさんや同伴している先輩ゴルファーの指示がないと判断できないゴルファーがいるようです。そのようなプレースタイルでは、ゴルフの面白さを半分も感じられないのではと思います。
自分で考え、判断し、実行する、といったプロセスで、試行錯誤をしながらベストな結果をめざす。それがゴルフというスポーツの醍醐味です。人に頼るのではなく主体的に行動できるようになると、ゴルフの面白さは格段に上がります。今回は主体的に動くこと=「自立」をどのようにサポートするかについて、ゴルフを通じて考えます。
私が主管するゴルフスクールに半年ほど前に入会された年配女性のAさん。その方はゴルフ歴が10年以上のベテランで、月1回程度のペースでラウンドされています。あまり飛距離は出ないものの、レッスンではそこそこのショットが打てています。ラウンド経験も十分ということでスクールが主催するコンペに参加していただいたのですが、その際のAさんの様子に驚いてしまいました。
私はコンペの際、時間の許す限りラウンドに同行し、各組のプレーの進行を促しながら、コース戦略など気付いたことをアドバイスするようにしています。Aさんの組に同行したときのことです。Aさんは私の姿を見るや否や、「ここは何番で打てばいいですか?」、「ここはどうやって打てばいいですか?」、「次は私が打つ番ですか?」と、ありとあらゆる質問をされるのです。ゴルフ歴が10年以上で、ある程度のラウンド経験がある方とはとても思えません。聞けば、私が同行してなかったときは他の同伴プレーヤーに都度尋ねていたそうです。
かつてAさんは、前述の通り、月1回くらいのペースでご主人と共にホームコース(会員権を持っていて自身が所属するゴルフ場)をラウンドされていたそうです。そのコースはキャディー教育がしっかりしていて、プレーヤーの飛距離や腕前を把握し、プレーヤーから「何番」と言われる前に使用するクラブをお渡しするサービスが徹底されているコースだったのです。
それに慣れてしまったAさんは、かなりラウンドを重ねているにもかかわらず、使用するクラブやコースの攻略法を自分で考え、自分で判断し、実行するという経験を積む機会がなかったのです。キャディーさんが近くにいない場合はご主人が使用クラブや打つ方向などを指示し、その指示通りに打つというゴルフを長年されてきた方でした。それでは、ゴルファーとして自立できてないのは当たり前です。
ゴルフは自己責任のスポーツです。野球やテニスは、時には対戦相手次第の部分がありますが、ゴルフはすべて「自分のせい」です。故に、自分で考え、自分で判断し、自分で実行し、ベストな結果をめざすことがゴルフの醍醐味です。キャディーさんが、プレーヤーに言われる前に最適なクラブを差し出す「至れり尽くせり」のサービス。プレーヤーとキャディーさんが以心伝心の関係で、プレーヤーが自分で考えた結果、使いたいと考えたクラブと同じクラブを口で伝えなくとも理解できるというなら素晴らしいと思います。しかし、使用クラブをキャディーさんが判断して、プレーヤーが自分で考えることを放棄してラウンドをしているなら、一見親切なサービスのように見えるこの行為は、逆にゴルファーからゴルフ本来の楽しみをも奪っているのではないかと思うのです。
ゴルフスクールが提供するサービスメニューの1つにラウンドレッスンがあります。ラウンドレッスンは、スクール受講生と一緒にコースに出てさまざまなアドバイスをするものです。練習場である程度、ボールが打てるようになっても、実際にコースに出ることになると、クラブ選びやコース攻略法はもちろん、マナーなどについても分からないことばかりで不安だらけです。そのような場合にラウンドレッスンはとても喜ばれます。
このレッスンには、大きく2つの目的があります。1つは、お客さまが目標スコアを達成できるように手助けすること。もう1つは目標スコアを達成するための考え方などをお客さまが身に付けるお手伝いをさせていただくことです。この2つは似ているようで異なります。
前者は「ティーチング」です。使用するクラブを教えてあげたり、グリーン上でパッティングのラインを読んであげたりするなど、当日のプレーを具体的にサポートします。お客さまはインストラクターの指示を参考にしてプレーすれば、良いスコアが出せるというわけです。初ラウンドの方やラウンド経験の浅い方は、これにより成功体験を積んでいただき、自信につなげることができます。
一方後者は「コーチング」です。ある局面におけるクラブ選択の考え方や、パッティングのラインの読み方などを指導します。この場合、使用するクラブを教えたり、ラインを読んであげたりはしません。あくまで、答えを導き出す「考え方」を伝えるにとどめ、自分で考えるよう促します。例えば、ある状況で何番のクラブを使えばよいかを聞かれたとき、コースに設置されている距離表示などの情報を基に残りの距離を自分で判断してもらい、風の状況やグリーンまでの高低差などを加味した考え方を伝え、最終的に使用クラブを自分で判断していただくようにします。つまり、「自立型ゴルファー」になるために必要な力が身に付けられるよう指導します。
前述のAさん。実は昨年、長年一緒にゴルフを楽しんできたご主人を亡くされたことが分かりました。それからしばらくはゴルフをされていなかったそうですが、ご主人が好きだったゴルフを1人でもやりたいと発起され、スクールに入会されたのです。せっかく再開したゴルフですから、しばらくは「コーチング」を受けていただき、今まで頼ってきたご主人から自立し、早く「自立型ゴルファー」へと成長して末永くゴルフを楽しんでいただきたいと思っています。
自分で考え、自分で判断し、実行するゴルファーを「自立型ゴルファー」と表現しました。そして、これからの時代、ビジネスにおいて求められる人材も、この「自立型ビジネスパーソン」ではないでしょうか。自立型ビジネスパーソンは、上司からただ言われた通りのことをするのではなく、自ら課題を設定し、自分の考えで行動して、より良い結果をめざす人材です。このような人材は、企業にとっての財産ですから“人財”といえます。
社員を人材から人財へと育てるには、その人のレベルに応じたサポートが重要になってくると思います。新入社員には社会人としてのマナーなどの基本的な教育、つまり「ティーチング」が効果的です。一方、若手社員から中堅社員へとステップアップする際、求められるのは「コーチング」です。
そして、社員が人財へと成長した後も、「カウンセリング」が必要です。どんなに優秀な人財であっても、時にはつまずき、悩み、モチベーションが下がることもあるでしょう。そんなときに求められるのが「カウンセリング」です。ゴルフスクールにおいても、ある程度の腕前になってスクールを卒業した後も、悩んだときや調子が悪くなったときにアドバイスが受けられるレッスン制度を設けています。これがカウンセリングに当たります。
ティーチング→コーチング→カウンセリングと、部下の成長に合わせて上司の教育のスタンスを変えていくのは、ゴルフレッスンでも、ビジネスパーソンの育成でも、全く同じだと思います。
執筆=小森 剛(ゴルフハウス湘南)
有限会社ゴルフハウス湘南の代表取締役。「ゴルフと健康との融合」がテーマのゴルフスクールを神奈川県内で8カ所運営する。自らレッスン活動を行う傍ら、執筆や講演活動も行う。大手コンサルティング会社のゴルフ練習場活性化プロジェクトにも参画。著書に『仕事がデキる人はなぜ、ゴルフがうまいのか?』がある。
【T】
ゴルフエッセー「耳と耳のあいだ」