
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
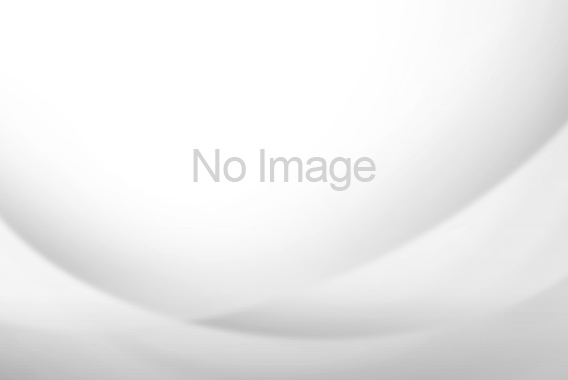
先日、ラウンドレッスンでスクールの受講者とコースを訪れた際、珍しい光景を目の当たりにしました。スタートの10分前、前の組はもうティーイングエリアでスタートの準備をしていなければならない時間、我々の前には空のカートがポツンと1台。マーシャルかコース管理のカートだろうと思いきや、そこに若い男性プレーヤー3人が遅れて登場。コーススタッフが1本のキャディーバッグを慌ててカートに積み込みました。当の本人たちは特に悪びれた様子もありません。
スタッフの1人がキャディーバッグを積み、もう1人がカートの操作方法をプレーヤーに説明し、別の1人がクラブ確認、さらに後続の我々におわびと状況説明をするスタッフと4人がかりでバタバタしていました。スタッフの説明によると、コースへの到着がスタート時間ギリギリだった上にパターをレンタルする手続きに手間取っていたとのこと。「先にスタートしましょうか?」とスタッフに提案しましたが、その日は混み合っていて先が詰まっているのと、彼らが心配なので、後ろから見て何かあれば注意してほしいとのこと。スタッフの1人は「最近こういう若いお客さんも多いんですよね……」と話していました。どうやら渋滞に巻き込まれてやむなしに遅れたのではなく、スタート時間にコースへ着けばよいと思っていたようなのです。
コロナ禍がきっかけで、広々とした屋外でプレーできるゴルフがちょっとしたブームになっています。ゴルフ場、ゴルフ練習場も共に盛況で、来場者数が軒並み増えていると聞きます。ゴルフ人気が高まり、ゴルファーが増えるのは業界にとって良いことです。が、一方でマナーを知らないゴルファーが増え、(悪意はなくとも)以前からプレーを楽しんでいたゴルファーに迷惑がかかるシーンが増えることも懸念されます。
この話、さらに驚いたことがありました。プレーヤーが3人いるにもかかわらず、カートに積まれたキャディーバッグは1本。他は見るからに古いクラブが数本とレンタルで借りたのであろうパターを、カートのパター入れに突っ込んでスタートしていったのです。数本の古いクラブにはキャディーバッグがないので、通常のようにカートには積めません。それで、仕方なしにパター入れに収めていたわけです。
私たちもラウンドしながら前の組の様子を見ていると、それぞれクラブをシェアしながらプレーしていました。最近はこういうスタイルもありかと思いましたが、まともに前に飛ぶことは少なく、右や左、そしてチョロと右往左往していました。ただ、先のスタッフが言う通りコースが混み合い全体のプレー進行が遅かったため、何とか前の組には離されずにラウンドできていたようでした。私たちも、この日のラウンドはハーフ(9ホール)で約3時間かかりました。
彼らがゴルフを楽しめていたかどうかは分かりませんが、最近、今までにはあまり見られないプレースタイルが出てきています。例えば、以前の記事で紹介したスループレー(9ホールを回った後、昼食休憩を挟まず一気に18ホールをラウンドする)や、お一人様プレーなどです。さらに今回紹介した若者たちのように、それぞれが自分のクラブを用意してコースに来るのではなく、クラブをレンタルしてそれをグループ内でシェアして使うノークラブゴルファーも現れています。
私は実は、これらを肯定的に捉えています。私はかねて、ゴルフがボウリングのようになってもいいのではないかと思ってきました。ボウリング人口は3800万人といわれています。しかし、これはマイボール・マイシューズを持つ本格的ボウラーの数ではなく、1年に1回でもボウリングをしたことのあるボウラーも含めた数字です。マイボール・マイシューズを持つ本格的ボウラーに限ると、(正確な数は分からないようですが)10万人程度だという推計もあります。これは、ボウリング人口の0.3%以下です。つまり、マイボール・マイシューズを持って本格的にボウリングを楽しむ人よりも、ボールやシューズはレンタルで済ませ、手軽にボウリングを楽しむ人たちが圧倒的に多いのです。
ゴルフもマイクラブ・マイシューズを持つ本格的ゴルファーに加え、年に数回ボウリングを楽しむボウラーのように、ノークラブ・ノーシューズでプレーの際には道具をレンタルして手軽にゴルフを楽しむゴルファーがいてもよいのではないでしょうか。こうしたゴルファーが増えればゴルフ業界はもっと活性化するでしょう。
もちろん、そのためにはクリアしなければならない課題があります。まだまだ先の話だとは思いますが、ゴルフコースに出掛けたら、クラブハウスで高いランチを食べなければならない、4人1組で回らなければならない……といった従来の常識も崩れつつあるのですから、ゴルファーたるもの「マイクラブ・マイシューズが当たり前」という常識も、そう遠くないうちに変わるかもしれません。
このようにゴルフのプレースタイルが多様化し、より多くの人々がそれぞれの楽しみ方をするのは良いことだと思います。そして、ゴルフがボウリングのように手軽に楽しめるようになるのも歓迎すべきことでしょう。そしてさまざまな楽しみ方をするゴルファーを受け入れるゴルフ場も、それぞれ特徴のあるサービスを提供し、差別化を図るのも大切だと思います。
ただし、ゴルフプレーの精神は忘れてはならないと思います。それは、第一に自己成長であり、これと同じくらい他者への配慮や心くばり、他人に迷惑をかけない精神が重要だと私は考えています。ゴルフを始めたばかりの初心者でも、他のゴルファーに迷惑をかけたいと思ってプレーする人はいないでしょう。初心者は、どのような行為が他のゴルファーに迷惑をかけることになるのかを知らないだけなのです。ですから、それらをしっかりと伝える必要があるわけです。
私が主管するゴルフスクールには、初心者向けコンテンツの1つに、ルール&マナー講座をセットにしたコースレッスンがあり、おかげさまで好評を得ています。ルール&マナー講座は開催コースに協力いただき、スタート前にコンペルームをお借りして座学で行います。スライドを使い、①プレーファースト(迅速なプレー)、②他人ファースト(他人に迷惑をかけない精神)、③安全ファースト(危険防止とコース保護)の3つのファースト&ファースト「3F」をお伝えしています。どんな行為がこれら「3F」に反するのかを具体例を挙げて説明していますので、ラウンド経験のない初心者にも分かりやすいと思います。
ゴルフスクールを受講する方々には、こうした指導が可能ですが、スクールに通わず自己流で練習しコースデビューする人たちに、どのようにしてゴルフプレーの精神を伝えていくかが今後の課題だろうと感じます。
日本の伝統芸能である歌舞伎に、近年「スーパー歌舞伎」というものが登場しました。三代目市川猿之助さん(現・二代目猿翁)が1986年に始めたもので、歌舞伎の精神を受け継ぎつつ、それまでになかった演出や手法を取り入れた「現代風歌舞伎」です。世界的に知られるようになったのはアニメの「ワンピース」を演目にした舞台でしょう。歌舞伎に興味のない層へリーチした点から、こうした活動は歌舞伎界を持続発展させていく原動力になるといわれています。ゴルフにも、ゴルフプレーの精神は受け継ぎつつ、従来のゴルフの常識にとらわれることなく、新たなゴルフの楽しみ方やプレースタイルを模索していくことは、これからのゴルフ業界に必要でしょう。
私が経営者として大切にしている言葉に「同根異菜(才)」(どうこん・いさい)があります。根っこは同じで菜(葉っぱ)は異なるという意味です。ここでいう「根っこ」とは、会社として大切にしたい共通の理念やコンセプト、ビジョン、会社のルールなどです。「菜(葉っぱ)」は、メンバー個々の才能や能力、長所、強み、そして考え方や人間性などです。つまり、会社の理念やビジョンなどは共通のものとして社員全員で守った上で、個々に異なる才能や強みを遺憾なく発揮しようということです。故に、最後の「菜」は才能の「才」といえるわけです。
これからのゴルフは「3F」をゴルファー共通の「同根」としてしっかりと伝え、それぞれのプレースタイルでゴルフを楽しみ、従来型ゴルファーも新しいスタイルのゴルファーもそれぞれを認め合い、お互いに気持ちよく楽しめる文化を築いていくべきだと思います。
執筆=小森 剛(ゴルフハウス湘南)
有限会社ゴルフハウス湘南の代表取締役。「ゴルフと健康との融合」がテーマのゴルフスクールを神奈川県内で8カ所運営する。自らレッスン活動を行う傍ら、執筆や講演活動も行う。大手コンサルティング会社のゴルフ練習場活性化プロジェクトにも参画。著書に『仕事がデキる人はなぜ、ゴルフがうまいのか?』がある。
【T】
ゴルフエッセー「耳と耳のあいだ」