
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
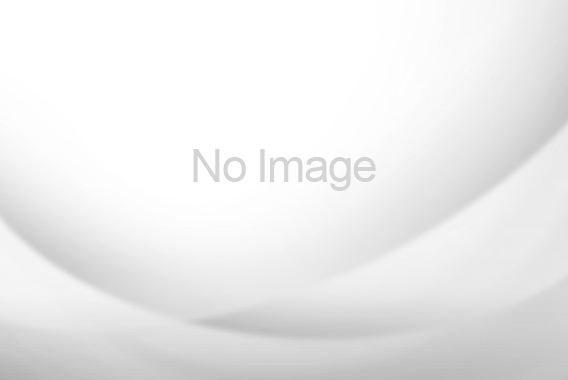 「グリーン上からカップにピンを立てたままパッティングができる」というルールに変更されて約1年がたちました。ルール改正当初は、従来通り「パッティングのときにピンは抜く」と考えるゴルファーが大多数だったのではないでしょうか。しかし、最近ではプロのトーナメントでもピンを立てたままパッティングするシーンが多く見られるようになりました。一般ゴルファーのラウンドでは、ピンは抜かないケースの方が多いように感じています。
「グリーン上からカップにピンを立てたままパッティングができる」というルールに変更されて約1年がたちました。ルール改正当初は、従来通り「パッティングのときにピンは抜く」と考えるゴルファーが大多数だったのではないでしょうか。しかし、最近ではプロのトーナメントでもピンを立てたままパッティングするシーンが多く見られるようになりました。一般ゴルファーのラウンドでは、ピンは抜かないケースの方が多いように感じています。
こうしたシーンを見るたび、プレー時間短縮を心掛ける「プレーファスト(PLAY FAST)」という考え方がゴルファーに浸透してきたのだと思います。私も、初心者を対象にしたラウンドレッスンではプレーファストの重要性を伝え、時間短縮につながるプレーの仕方を指導します。それでもプレーが遅くなった場合、移動の際に駆け足を促すようなことも多々あります。
ただ、中には、駆け足がままならない高齢のプレーヤーもいらっしゃいます。高齢者は、筋力や心肺機能が低下、神経系も衰えることから素早く行動することが難しくなります。骨密度も年齢とともに低下するため、万一転んだ場合は骨折のリスクも高くなってしまいます。したがって、高齢プレーヤーがゴルフを楽しむための環境整備もゴルフ界全体で進めなければいけません。また、プレーファストを実現するためにはその前に、高齢プレーヤー当人と同伴者による「譲り合い」「助け合い」の精神が必要になるでしょう。誰もが年を取りますが、ゴルファーならできるだけ長くゴルフに親しんでいたいはず。そこで、今回は「高齢者のゴルフ」について考えてみたいと思います。
前述のように、高齢者は素早く行動することが困難なケースが出てきます。また、思考や判断速度が遅くなったり、視力が衰え、認知速度が低下して、自分が打ったボールを見つける時間も遅くなったりすることもあるでしょう。高齢者は若い人と比べるとラウンドのスピードが遅くなるのも、ある程度は仕方がないことなのです。
しかし、ゴルフルール上は、スロープレー厳禁です。同伴競技者だけでなく、後続組全体に迷惑がかかってしまうからです。ゴルフ規則第3章「プレーについての規則」の規則6に、「プレーヤーは不当に遅れることなく~(途中略)~プレーをしなければならない」と定められていて、ゴルファーはプレーファストに努めなければなりません。この規則に違反した場合は、ストロークプレーでは2打罰、マッチプレーではそのホールの負け、その後さらに同じ違反があった場合は競技失格と厳しい罰則になっています(競技委員による裁量はあります)。
ここで注目するべきは、「プレーヤーは不当に遅れることなく…」と記載されている点でしょう。“不当に”遅れる行為をしたプレーヤーに対して厳しい罰則を与えています。しかし、高齢ゴルファーは決して「不当に」プレーを遅延させているわけではないのです。故に、高齢ゴルファーに配慮したゴルフ環境を整えることが必要で、それは我々ゴルフに携わる者全員の役割だと私は考えています。
私がコースレッスンやコンペを企画する際、高齢の方の参加が見込まれる場合はできるだけカートがフェアウエーに乗り入れられるコースを選定するようにしています。カートでボールの近くまで乗り付けられれば、セルフプレーでもクラブを遠くのカートまで取りに行かずに済み、高齢者にとって優しいからです。
乗用カートを導入しているゴルフ場でも、舗装された、いわゆる「カート路」のみを走行するルールとなっているケースが目立ちます。芝生の上をカートが走行すると、芝生を傷めてしまうという問題があるからですが、最近は芝生を傷めにくい特殊なタイヤを装着したカートも登場しています。特に暑さの厳しい夏場などは、ボールの近くまでカートで移動できれば、高齢者のみならずすべてのゴルファーにとってうれしいでしょう。
フェアウエーへのカート乗り入れの利点はもう一つあります。それは「ゴーアヘッド(go ahead)」(お先にどうぞ)が可能になるという点です。高齢者はどうしてもプレーが遅くなります。故に、時には後続組に「お先にどうぞ」と声をかけ、先にプレーしてもらうよう配慮することも必要です。ゴルフ規則の第1章「エチケット」では、前の組との間隔が空き、後ろの組を待たせてしまう場合は、後続組に先にプレーしてもらうよう声かけしましょうと記載されています。ですから、高齢ゴルファーの組には第一にプレーファスト(早く回れ)を求めるのではなく、ゴーアヘッド(お先にどうぞ)を有効に活用することを勧めるべきではないかと思うのです。
この「お先にどうぞ」を行う際、ネックになるのがリモコン式電動カートです。ご存じかもしれませんが、乗用カートは大きく分けて2種類あります。1つは自走式カート、もう1つがリモコン式の電動カートです。自走式カートは、運転者が運転して自由に走行します。リモコン式電動カートは、発進と停止をリモコンで行い、カートは決められたカート路を自動走行します。
「お先にどうぞ」という行為は自走式なら問題なく実行できます。しかし、リモコン式の場合、ラウンド中に組の順番を入れ替えることが難しく「お先にどうぞ」がしづらくなります。リモコン式電動カートは、遠くからカートの発進停止ができるので便利ですし、次のホールへの道を間違えたり、運転操作を誤ってコースアウトしたりといったリスクを回避できるという利点はありますが、高齢ゴルファーが自分のペースでゴルフを楽しむという面ではマイナスなのかもしれません。リモコン式電動カートを導入しているゴルフ場さんは、プレーヤーが自由にカートの順番を入れ替えることができるよう、改善を検討していただけるとうれしく思います。
このほか、第48回で紹介した「PLAY9」も、高齢ゴルファーにとってはうれしいプレースタイルです。「18ホール回るのは体力的にきつい。でもゴルフは楽しみたい!」という高齢ゴルファーに、9ホール(ハーフラウンド)のみを楽しんでいただき、プレー後はクラブハウスのお風呂でのんびり身体を癒やし、食事をして帰っていただくというプレースタイルです。ゴルフ場経営の観点から見ると、ハーフラウンドだと客単価が下がるのでできれば導入したくないのかもしれません。しかし、今やゴルフ市場を支えているコア層は、主に50~60歳代以上だといわれています。この年代も後十数年で75歳以上の後期高齢者となります。だからこそ、多くのゴルファーが後期高齢者の年齢になってもゴルフが楽しめる環境づくりは、ゴルフ業界にとっては必要なことなのです。
今後は、カートのフェアウエー乗り入れ可能な自走式カートが普及し、高齢ゴルファーは「プレーファスト」よりも、「ゴーアヘッド」を活用したプレースタイルが定着する。そしてハーフラウンドOKのゴルフ場が増え、多様化するプレースタイルに対応していく。そんなゴルフ環境が実現すればよいなと思います。
 ゴルフ場の設備やラウンドメニューの充実以外に、高齢者がゴルフを楽しむために必要なことが同伴競技者同士の「助け合いの精神」です。若い同伴競技者は、可能な限り高齢ゴルファーをサポートしてあげてください。カートが遠ければ必要なクラブを届けてあげる。バンカーショットの後は本人に代わってバンカーをならしてあげる。近くまでカートを動かしてあげる、などさまざまなサポートが考えられます。
ゴルフ場の設備やラウンドメニューの充実以外に、高齢者がゴルフを楽しむために必要なことが同伴競技者同士の「助け合いの精神」です。若い同伴競技者は、可能な限り高齢ゴルファーをサポートしてあげてください。カートが遠ければ必要なクラブを届けてあげる。バンカーショットの後は本人に代わってバンカーをならしてあげる。近くまでカートを動かしてあげる、などさまざまなサポートが考えられます。
プライベートなラウンドでしたら、高齢ゴルファーのための特別ルールを設けてもよいと思います。高齢ゴルファー同士でラウンドするなら、急な斜面の下などにボールが落ちた場合にゼネラルエリア(※)であっても、そのボールは放棄し、1打加えてフェアウエーの真ん中から打てるようにする、などもいいでしょう。若い人がいれば、可能な限り斜面の下へ取りに行ってあげればボールを失わずに済みます。
日本能率協会(JMA)が、2018年11月に発表した、「第9回 ビジネスパーソン1000人調査」によると、職場のチームで魅力を感じるのは、「困ったときに助け合えるチーム」が47.0%でもっとも高かったことが分かりました。次いで「メンバー同士が仲の良いチーム」が29.5%、「コミュニケーションが活発なチーム」が28.2%と続きました。多くのビジネスパーソンが「助け合える仲間」「仲の良い仲間」を職場に求めていることがよく分かります。
職場は同年代に限らず、さまざまな年齢の人や育った環境が異なる人が集う場所です。仲間意識は「助け合いの精神」によって育まれます。そして、ゴルフはその「助け合いの精神」を磨くのに適したスポーツです。ゴルフのラウンドは通常4人1組、一緒に回るプレーヤーを同伴競技者といいます。同伴競技者は、時には対戦相手であり、スコアを競うライバルではありますが「敵」ではなく、共にプレーを楽しむ仲間です。ゴルフは個人のスポーツでありながら、年齢や実力に関係なく仲間と一緒に楽しめ、自然の中で交友を図ることができる素晴らしいスポーツだと思います。
中上級者が初心者のサポートをするように、若い人が高齢者をサポートし、逆に若い人は先輩ゴルファーから色々なことを学ぶ。同伴競技者の4人がワンチームとなり、お互いに助け合ってゴルフを楽しむ。そしてお互いにゴルファーとして人間として成長していく、それがゴルフの醍醐味だと思うのです。そうしたプレースタイルを身に付ければ、職場でも、多様な人材と力を合わせて働けるようになると思います。
執筆=小森 剛(ゴルフハウス湘南)
有限会社ゴルフハウス湘南の代表取締役。「ゴルフと健康との融合」がテーマのゴルフスクールを神奈川県内で8カ所運営する。自らレッスン活動を行う傍ら、執筆や講演活動も行う。大手コンサルティング会社のゴルフ練習場活性化プロジェクトにも参画。著書に『仕事がデキる人はなぜ、ゴルフがうまいのか?』がある。
【T】
ゴルフエッセー「耳と耳のあいだ」