
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
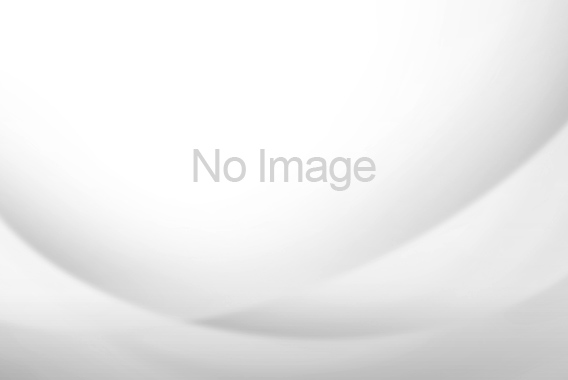 初心者はもちろん、そうでなくても、「バンカーが苦手!」「バンカーに入るとなかなか出せない!」というゴルファーも少なくないのでは。そんなバンカーが鬼門の人にとっては朗報です。今年のルール改正で「2罰打でバンカーの外にドロップできる」というルールが新たに加わりました。つまり、ペナルティーさえ受ければバンカーの外から打てるようになったのです。
初心者はもちろん、そうでなくても、「バンカーが苦手!」「バンカーに入るとなかなか出せない!」というゴルファーも少なくないのでは。そんなバンカーが鬼門の人にとっては朗報です。今年のルール改正で「2罰打でバンカーの外にドロップできる」というルールが新たに加わりました。つまり、ペナルティーさえ受ければバンカーの外から打てるようになったのです。
連載50回を迎えた今回は、バンカーにおける新ルールの解説と、その背後の「プレーヤーに求められる能力」についてお伝えします。
まず、以前からあるルール「アンプレヤブル」について説明しましょう。アンプレヤブルとは「打てません」という宣言です。ボールが木の根っこに挟まったり岩の間に潜り込んだりして、どうしても打てない状況に陥った場合、この宣言をして、次の3つの処置のうちからいずれかを選択してプレーを続けることになります。
(1) 前回打った場所に戻り、1罰打でプレーする。
(2) ピン(ホール)とボールとを結んだ後方延長線上(どこまで下がってもよい)にドロップ(※1)し、1罰打でプレーする。
(3) ボール位置からピンに近づかず、かつ2クラブレングス(一番長いクラブ2本分)の範囲内にドロップし、1罰打でプレーする。
※1 ドロップ:救済を受ける際、ボールを地面に落とすこと。旧ルールでは「肩の高さから落とす」となっていたが、新ルールで「膝の高さから落とす」に変更 |
ボールがバンカー内にある場合もアンプレヤブルは宣言できます。ただし、旧ルールでは、先の(2)か(3)の処置を選択した際、その救済エリアは「バンカー内で」という条件が付いていました。そして、1回でもバンカーショットを試みてバンカーからボールを出せなかった場合には、アンプレヤブルの処置(1)を選択しても前回打った場所がバンカー内にあるため、自力でバンカーから脱出できるまで永遠にバンカーから打ち続けなければなりませんでした。
これはバンカーが苦手な人にとっては酷なルールです。それが、新ルールでは現在の1打罰の処置(1)~(3)に、4つ目の処置方法として「2罰打でバンカーの外にドロップできる」が加わりました。正確には次の通りです。
(4)ボールとピンとを結ぶ後方延長線上のバンカー外の所に基点を決め、その基点から1クラブレングス以内で、かつピンに近づかない所にドロップし、2罰打でプレーする。
さて、この(4)の処置、みなさんは実際のプレーで活用されるでしょうか?それともバンカーショットに果敢に挑戦し、実力でバンカーからの脱出を図るでしょうか。バンカーが本当に苦手で全く出すことができない人は、迷うことなく2罰打ルールを適用し、バンカーの外にドロップする方法を選択した方が、スコアが良くなるでしょう。しかしある程度、バンカーでも対処できるゴルファーの多くは、状況を見て、どちらの方がスコアが良くなるかを考えるのではないでしょうか?
「アゴ(※2)の高さは?」「アゴまでの距離は?」「ボールのライ(※3)は?」「砂の状態は?」……など、状況を分析し、自分の実力でバンカーからの脱出が可能か否かを判断するでしょう。このとき、大切なポイントが、「今の状況を正しく把握できているか?」ということと、「自分の実力を知っているか?」という2点です。特に後者は難しいことですが、とても重要な判断要素です。
| ※2 アゴ:バンカー周りの土手の部分。グリーン周りのバンカー(ガードバンカー)の場合、グリーン側が高くなっているケースが多い。その高低差が大きい場合に「アゴが高い」と表現する | |
| ※3 ライ:ボールがある場所の状態のこと。打ちやすい状態を「ライが良い」、打ちにくい状態を「ライが悪い」と表現する。バンカーの場合、砂にボールがめり込んで一部しか見えない状態の場合、「目玉になっている」と表現する。目玉になっているライの場合、バンカーからの脱出は非常に難しくなる |
「敵を知り己を知れば、百戦危うからず」。これは、孫子の兵法書の一節です。「相手(敵)と自分のことを正しく知れば、戦に負けることはない」という教えです。この考え方は、ゴルフの上達にも、ビジネスにおける業績アップにも通じるものだと思います。
ゴルフにおける「相手(敵)」は誰でしょうか。ゴルフは自然を相手にするスポーツです。故に、ゴルフにおける「相手(敵)」とはコースそのものであり、自然そのものです。ゴルフにおいて「相手を知る」とは、「コースを知る」「自然状況を知る」ということになります。
コース全体のレイアウトを知らなければ、コース戦略を立てることはできません。また、これから打つショットにおいても、残りの距離やボールのライなどに加え、風の状態などを知らなければ、どのクラブでどう打てばよいかの判断もできません。バンカーにおいては、先ほど例に挙げた、アゴの高さやアゴまでの距離、砂の状態などを知らなければ、アンプレヤブルを宣言するのか、打つにしてもそのまま打つのか、フェースを開く(※4)などの対処が必要なのかの判断もできません。「相手(コースや自然状況)を知る」ことが、ゴルフプレーにおいて不可欠な要素だと理解できるでしょう。
※4 フェースを開く:クラブヘッドのボールを打つ面をクラブフェースといい、右打ちの場合フェースを右に向けて、より水平に近い角度にして打つこと。アゴの高いバンカーから脱出するときなど、より高い球を打ちたい場合にこのような打ち方をする |
次に「己を知る」ことについて。「己を知る」ことは「相手を知る」ことと同等に大切です。ゴルフの場合、先に述べた通り、バンカーでは自分の実力で脱出できる状況かどうかの判断が求められます。自分の実力を正しく把握できていないばかりに、この判断を誤り、みすみすミスショットを連発……といった苦い経験を持つゴルファーも多いのではないでしょうか。
ゴルフでは、自分の実力を知った上で、それ相応の攻め方が求められます。練習場のきれいに整備された人工マットの上と、芝やラフの状況が一定ではないコースの状況は当然異なります。コースプレーでの局面局面において、自分の現在の実力では無理だと判断したら、バンカーの新ルールなどを活用して賢くプレーしましょう。
ビジネスにおける「相手」とは、お客さまや競合他社です。自社の商品やサービスを買ってくださるお客さまが何を求めているか?これを知ることがとても大切です。また、競合他社がどんな商品やサービスを、どんな客層に対して売っているのかを知ることも重要です。競合他社のそれを知ることで、自社の強みや弱みも見えてきます。
ビジネスにおいて「己を知る」とは、自社の商品やサービスを知ることに他なりません。単に知っているだけでなく、強みや弱みを熟知していることが求められ、それは「相手を知る」ことによって得られます。他社に対して優位な商品やサービスがあれば、それを売りとして自信を持って世に広めるべきですし、逆に劣っている点は改善していけばよいわけです。そうでなければ、お客さまのニーズに対して的確な提案などできるはずがありません。
加えて、ビジネスパーソンとしての「自身の特性」を知っておくこと。「仕事は丁寧だけど人より時間がかかる」「口下手だけどフットワークが良く行動が早い」など、自身の長所も短所も知っている人はビジネスマンとしてデキる人だと思います。「相手を知り、己を知れば、ゴルフもビジネスも危うからず」です。ぜひ心得ておいてください。
執筆=小森 剛(ゴルフハウス湘南)
有限会社ゴルフハウス湘南の代表取締役。「ゴルフと健康との融合」がテーマのゴルフスクールを神奈川県内で8カ所運営する。自らレッスン活動を行う傍ら、執筆や講演活動も行う。大手コンサルティング会社のゴルフ練習場活性化プロジェクトにも参画。著書に『仕事がデキる人はなぜ、ゴルフがうまいのか?』がある。
【T】
ゴルフエッセー「耳と耳のあいだ」