
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
ゴルフスイングのポイントを学ぶ際、「腰のリード」という言葉を耳にすることがあるかと思います。このときの「腰」とは骨盤のことです。本連載を読んでいる人ならピンとくるかもしれません。腰のリードとは、体の重心は動かさずに股関節の体重移動を行うために骨盤を回旋させることだといえるでしょう。
スイングトップからボールインパクトにかけての振り下ろしにおいては、最初に骨盤、そして次から胸郭→左肩甲骨(右打ちの場合)→左腕(同)→クラブの順で連鎖的に動かし、大きなパワーを生み出します。ボールをより遠くに飛ばすには欠かせない動きです。この一連の動作は、聞いた段階では頭で理解した気になりますが、いざやろうと思うと難しく考え過ぎて動きがバラバラになってしまう人が多いようです。
第32回からの連載で、スタビリティ(安定性)とモビリティ(可動性)を向上させるために必要な筋肉、体の使い方、効果的なトレーニング方法を伝えてきました。しかし、体がスムーズに動くようになっても、一連の動作で力を生み出し、それをボールに正しく伝えることができなければ飛距離を伸ばすことはできません。今回はいよいよ、ゴルフスイングに必要な3要素のうちの1つ、キネティックチェーン=運動連鎖を説明します。これを理解すれば、「腰のリード」もうまく使えるようになるでしょう。
運動連鎖は、体の中心である「コア(=丹田)」から発生した運動が、末端へと伝わりながら増幅していき、最終的に大きな運動が得られるという運動メカニズムのことです。身体部分を連続した鎖に例えて、「運動連鎖の原理」と呼んでいます。
野球の投球フォームを例に説明しましょう。ピッチャーの投球動作の後半部分を思い浮かべてください。左足(右投げの場合)が着地した後、まず腹筋を使って骨盤が動き、続いて胸→肩→上腕→肘→前腕、そして手首へと、運動が連鎖的に伝わりながら徐々に速度が増し、最終的に最も大きな速度で、ボールをターゲットに向けて押し出しています。これが運動連鎖です。
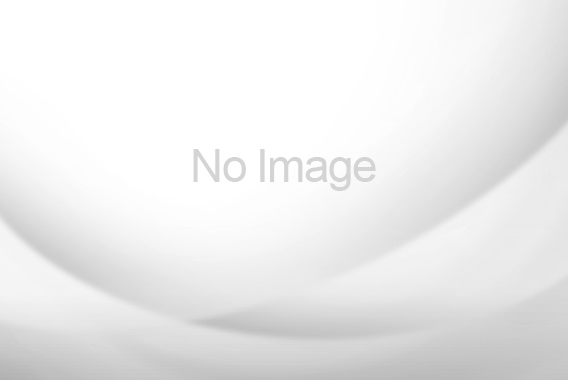
スムーズな運動連鎖で大きな運動エネルギーを生むピッチング
野球のピッチングに限らず、バッティングやボクシングのパンチ、サッカーのシュート、釣りのキャスティングなど、大きなパワーを必要とする動作では、常に運動連鎖をスムーズに実行する必要があります。もちろん、ゴルフスイングも同様です。実をいうと、この運動連鎖自体は、人間にとって日常的に行っている当たり前の動作です。歩いたり走ったり、水の入ったコップを口に運んだりといったことと同じ、無意識に誰でも行っている易しい動作なのです。
人が歩いたり走ったりするのは「易しい動作」と表現しましたが、運動連鎖のメカニズムはとても高度で、いくつもの骨と筋肉が協調し合って働く複雑極まりない動作です。人はそれを意識せず、いとも簡単にやってのけます。単純にゴルフクラブを振るという動作だけなら、誰でもできるでしょう。スタビリティ(安定性)とモビリティ(可動性)の機能がある程度上がっていれば、腰のリードも自然と動かすことができるはずなのです。
例えばふすまは、何の負荷も感じずに開け閉めできるでしょう。しかし、それが鉄でできた重たい扉だったらどうですか。腰をグッと入れ、体重をかけて扉を動かそうとするでしょう。体の動作が明確になるはずです。日常的に行っている動作でも負荷が高くなれば、それに体の動きが応じるようになります。つまり人間には、より大きなパワーを必要とするとき、体が順応するプログラムが組み込まれているのです。
なのに、ボールを前にして、いざフォームを構えてクラブを振り出したとき、その当たり前にできることを途端に難しく感じてしまうゴルファーが少なくありません。その原因は、できるはずのことをできなくする「阻害要素」にあると私は考えています。その阻害要素を把握し、排除してやれば、腰のリードは誰でもできるはず。いったい、その阻害要素とは何でしょうか?
腰のリードを妨げる阻害要素のほとんどは、肩や腕の力みであったり、腕でクラブを振ろうとする動作だったり、あるいは腕そのものを振ろうとする行為だったりします。では、なぜ力んだり腕を振ったりしてしまうのか?その原因を深掘りしていくと、以下のようなことが考えられます。
(1) 思考と感覚のズレ
(2) 身体バランスの低下
(3) 柔軟性の欠如、関節の可動域不足
(4) 筋力不足
(5) 余計な思考、余計な感情
(6) 情報過多
(1)の「思考と感覚とのズレ」の代表が、他人のスイングを見たときの印象と、自分自身が実際に行っているスイング感覚との相違です。他人のスイングは、一見腕を高く振り上げているかのように見えます。しかし、実は、ゴルフも上級者になると腕は最小限しか動かしていません。可能な限り体との位置関係を保ち、クラブヘッドに生じる遠心力や慣性力を利用してスイングしています。それを知らないでマネをして腕を動かし過ぎてしまうのです。
さらに自身の動作を正確に把握できていないケースも目立ちます。腕をそれほど使っていないつもりでも実は大きく使い過ぎていたり、力んでいないつもりで力んでいたりということがこれに当たります。こうしたズレがあるかどうかを知るには、ビデオカメラで自分のスイングを撮影するのが一番早道です。自分ではプロゴルファーのような華麗なスイングをしているつもりが、似ても似つかないスイングになっていてショックを受ける方も多いはずです。
(2)~(4)はフィジカルの問題です。コア(重心)が不安定だと運動連鎖を発揮できません。なぜならコアが運動連鎖のパワーの「発生源」だからです。柔軟性や可動域不足は、モビリティ(可動性)が十分でないことの原因となり、筋力不足はスタビリティ(安定性)の欠如につながります。
(5)の「余計な思考、感情」は、結果に対する期待、不安、恐れ、迷いなどの「心の揺らぎ」です。スイング直前にこうした思考や感情が芽生えると、思わず力んだり、腕で当てにいったりしてしまい、スイングが乱れる結果につながります。
(6)はこの時代ならではの阻害要因です。世の中にレッスン書や上達指南書は星の数ほど存在し、ネットはさまざまな情報であふれかえっています。注意したいのは、あなたが見つけた情報が必ずしも自分の特性に合った情報とは限らないということです。それらに惑わされると、本来できることができなくなり、かえってゴルフが下手になってしまうのはよくある話です。
こうしてみると、腰のリードを阻む阻害要素のほとんどが、「メンタル(心)」と「フィジカル(体)」に起因しているといっていいでしょう。心技体の「技」は、心と体を整えることで初めて発揮できるのです。
ゴルフは、グリップや構え方を学ぶことから始まり、できないことを1つひとつできるようにしていく「足し算」発想で上達していくイメージがあります。しかし、運動連鎖を妨げる阻害要素については、1つひとつ取り除いていく「引き算」発想を持つと、ゴルフは格段に易しくなります。難しく考えることはありません。運動連鎖の動きに必要な心と体を整えることに集中することで、スイングの構えも締まり、腰のリードを自覚することができるはずです。
ビジネスにおいても「足し算」ではなく、「引き算」発想を取り入れて仕事の効率が向上する可能性があります。余計な仕事、やらなくてもよい作業を、引き算で徹底的に取り除いてやれば、仕事がシンプルになり本質だけが見えるようになります。ムダをそぎ本質だけにフォーカスすれば、より集中でき、仕事のパフォーマンスは自然と上がるでしょう。
仕事もゴルフも、足りないものを足していく「足し算」ではなく、不要なものや妨げとなるものを引いていく「引き算」発想を持つと、物事の見え方が変わってきます。ぜひ、実践してください。
執筆=小森 剛(ゴルフハウス湘南)
有限会社ゴルフハウス湘南の代表取締役。「ゴルフと健康との融合」がテーマのゴルフスクールを神奈川県内で8カ所運営する。自らレッスン活動を行う傍ら、執筆や講演活動も行う。大手コンサルティング会社のゴルフ練習場活性化プロジェクトにも参画。著書に『仕事がデキる人はなぜ、ゴルフがうまいのか?』がある。
【T】
ゴルフエッセー「耳と耳のあいだ」