
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
2019年のゴルフルール改訂に、ゴルファーのみなさんもそろそろ慣れてきた頃ではないでしょうか。少しおさらいすると、ルール改訂には4つの大きなポイントがありました。(1)ルールの簡素化、(2)プレー時間の短縮、(3)規制緩和、(4)自己自律の強化、です。このうちの1つ、(3)規制緩和について、今回はより深く考えてみましょう。
「規制緩和」にかかるルール改正は以下の7点です。
[1]アドレス中にボールが動いても、その理由がプレーヤーにない場合は無罰
[2]ペナルティーエリア内でもソール(構えでクラブを地面に付けること)できる(ただし、バンカーでは不可)
[3]バンカー内のルースインペディメント(小石やゴミなど)は取り除くことができる
[4]打ったボールが自分や自分の携帯品(カート含む)に当たっても無罰
[5]2度打ちも無罰(1打とカウント)
[6]ボールの捜索中にプレーヤー自身が偶然に動かしても無罰(元の位置に戻す必要はある)
[7]距離計測器の使用が可能に(ただし、使用できるのは距離計測の機能のみ)
改正前のルールでプレーしていたゴルファーからすると、かなり“緩く”なったと感じていることでしょう。特に「故意でなければノーペナ(無罰)」とする、[1][4][5][6]が顕著だと思います。これは、ゴルファーの「悪意のない“うっかりミス”には寛容に対処しよう」という考え方が、新ルールで反映された形になります。
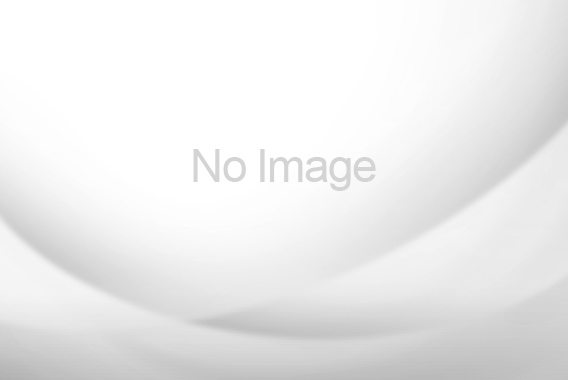 旧ルールでは、「不正はルールで規制する」という考え方がその根底にありました。つまり、審判がいないゴルフにおいて、ゴルファーはいつでも自分に有利なように不正を働くことができ、ルールで規制しなければ不正をしてしまうという「性悪説」がベースにありました。故に、故意であろうがなかろうが、プレーヤーにとって有利になると思われる行為は「ルールで規制する」となっていたわけです。
旧ルールでは、「不正はルールで規制する」という考え方がその根底にありました。つまり、審判がいないゴルフにおいて、ゴルファーはいつでも自分に有利なように不正を働くことができ、ルールで規制しなければ不正をしてしまうという「性悪説」がベースにありました。故に、故意であろうがなかろうが、プレーヤーにとって有利になると思われる行為は「ルールで規制する」となっていたわけです。
逆に新ルールは、スポーツマンシップにのっとったゴルファーが自分に有利なようにわざとボールを蹴ったり、動かしたりといった不正は働かないという「性善説」に立った考え方です。故に、故意ではない“うっかりミス”には目をつぶり、プレーヤーの「自律の精神」を尊重しようとしています。
例えば、アドレス中にクラブでボールを動かし、ボールの状態を打ちやすいように改善(ライの改善)する行為を規制するため、旧ルールでは、プレーヤーがアドレスした後でボールが動いた場合、1罰打が科せられました。その後、2012年のルール改訂で、プレーヤーが球を動かす原因となっていないことが明確であれば、罰は科さないとなっています。
また、ボールの捜索中に、プレーヤーが誤ってボールを蹴飛ばしてしまうケース。誤ったフリをして故意にボールを蹴飛ばし、打ちやすい所に動かしてしまうことも想定して、故意であろうがなかろうが、旧ルールでは1罰打が科せられました。
このように、2018年までのゴルフ規則の根底には、ゴルファーは本来、放っておくと自分に有利なように不正を働くものだという「性悪説」で考え、それをルールで厳しく規制していたということになります。
ここで改めて、性悪説と性善説について整理してみましょう。
性悪説とは、人間の本性は利己的であり、環境や欲望で「悪」に走りやすいという考え方です。一方の性善説は、人間の本性は生まれながらに「善」であるという考え方です。
性悪説は、人間は自然の成り行きに任せているとどんどん悪い方へ向かってしまう。故に、教育によって礼儀や社会規範を学ばせる必要があり、それによって善い人間に成長できると考えています。
一方の性善説では、人は生まれながらにして「善の芽」が存在すると考えています。その「善の芽」とは次の4つで、「四端(したん)の心」といわれています。
・惻隠(そくいん)の心: 同情の気持ち、思いやりの心
・羞悪(しゅうお)の心: 不正を恥じ、悪を憎む心
・辞譲(じじゅう)の心: 謙遜して、人に譲る心
・是非(ぜひ)の心: 是非、善悪を判断する心
人間は、教育や学習によって自分の中にある「四端」を伸ばすことができ、どんな人でも、偉大な人物になりうる可能性が備わっていると孟子は性善説の中で主張しています。
孟子の性善説と荀子の性悪説は、その言葉だけ見ると真逆のことを主張していると思われがちですが、両者とも儒家であり、立派な人間になるには「教育が大切である」という結論に達しています。その違いを教育方法になぞらえてみると、孟子の場合は「内面から善を引き出し、育てていく教育」といえ、荀子のそれは「外部から悪に規制を与える教育」といえるのではないでしょうか。
ビジネスにおける性悪説と性善説は、それぞれ「相手(取引先)を悪人だとして疑って接する」という考え方と、「善人だとして信用して接する」という考え方を意図することが多いです。荀子と孟子が唱えたそれとは、少々意味合いが異なりますが、人間の営みにはどちらも両面あると考えればいいでしょう。
例えば、性善説で相手を信用ばかりしていたら詐欺まがいの話に乗ってだまされた、なんてことにもなりかねません。「こういうだましの手口もあるかもしれない」と性悪説の視点でリスクマネジメントしておくことは、時として自分自身や自分の会社を守ることにつながります。
一方、性悪説に偏り過ぎる態度や振る舞いも問題があります。「何か善からぬことを考えているに違いない」などと普段から接していたら、相手からの信頼はいつまでたっても得られません。
性悪説と性善説、どちらが正しくどちらが間違っているということではなく、両者をバランスよく融合させた教育がベストではないかと私は思います。
性悪説でいう「悪」は、別の見方をすると、人間の「弱さ」であるともいえると思います。誰も見ていなければ、芝生に沈んでいるボールを、打ちやすいように動かしたくなる。ゴルファーならそのように思う人が少なくないかも知れません。それは「悪」というより、利己的欲望に負けている人の「弱さ」といえるのではないでしょうか。
ゴルフは、自分を律することで、そうした「人間の弱さ」を払拭し、「四端の心」を育んでいけるスポーツだと感じています。故意や悪意のない“うっかりミス”を寛容に対処するのは、人間が本来備えている「四端の心」を伸ばす意味で大切なことのように思うのです。
一方で、不正にはルールをもって厳格に当たらなければなりません。2019年のルール改訂においても、故意にボールを動かしたり、打ちやすいようにライを改善したりする行為には、しっかりとペナルティーを科していることをお忘れなく。
このように、ルール改訂の1つの柱である「規制緩和」によって、性悪説と性善説がうまく融合されゴルフの教育性がより高まったのではないかと私は見ています。より多くのプレーヤーが参加することで、「四端の心」を育み「自律の精神」をお互いに養えるのがゴルフの良い一面でしょう。若いビジネスパーソンが参加しやすい今、ぜひラウンドに出てくれることを期待します。
執筆=小森 剛(ゴルフハウス湘南)
有限会社ゴルフハウス湘南の代表取締役。「ゴルフと健康との融合」がテーマのゴルフスクールを神奈川県内で8カ所運営する。自らレッスン活動を行う傍ら、執筆や講演活動も行う。大手コンサルティング会社のゴルフ練習場活性化プロジェクトにも参画。著書に『仕事がデキる人はなぜ、ゴルフがうまいのか?』がある。
【T】
ゴルフエッセー「耳と耳のあいだ」