
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
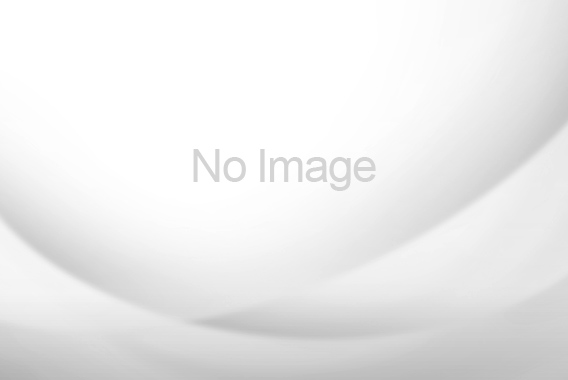
戦国時代に武将が生き残るために、また状況を有利に進めるために、有力武将への臣従、諸将の説伏、戦の和議などの「交渉」は重要な意味を持ちました。
本連載の第23回でも取り上げた黒田官兵衛は軍師として名高い武将ですが、交渉にも優れた才能を発揮しました。今回は、交渉人としての黒田官兵衛にスポットを当てます。
官兵衛は1546年、播磨国(はりまのくに/現・兵庫県)の武将・黒田職隆(もとたか)の嫡男として生まれました。職隆は地元の大名・小寺氏の家老で、官兵衛は1567年に家督を継ぎます。
その頃、播磨の東からは尾張国(現・愛知県)の織田信長が、西からは安芸国(あきのくに/現・広島県)の毛利輝元が勢力を伸ばしていました。小寺氏は両者の間に挟まれ、どちらに付くか、判断を迫られます。
ここで官兵衛は、主君である小寺政職(まさもと)に信長側に付くように進言。小寺氏の使者として1575年に岐阜城を訪れ、織田信長に謁見しました。これが、交渉人としての官兵衛の最初の仕事だといってもいいでしょう。
小寺氏の一統が臣従する意思があることを伝えると、信長は喜び、官兵衛に刀を授けました。これが、現在国宝になっている名刀「圧切長谷部(へしきりはせべ)」です。
信長の満悦は小寺氏の臣従によるところが大きいと思われますが、このあたりは官兵衛の如才のなさも感じさせます。こうして、小寺氏と共に官兵衛は信長の臣下に入りました。
そして官兵衛は、小寺氏以外の播磨の武将たちに対し、信長の側に付くように次々と説得を試みました。交渉人・官兵衛の面目躍如です。
ただ、播磨の武将の1人である荒木村重を説得するため単身で有岡城に乗り込んだところ、逆に捕らえられてしまい1年近く幽閉されることに。この経験が交渉人としての官兵衛に慎重さをもたらし、交渉力をさらに増す要因になりました。
もちろん官兵衛の能力は交渉だけではありません。戦の場でもその才を存分に発揮します。1577年の英賀(あが)合戦では、5000の軍勢で攻め込んできた毛利軍に対して約500の兵で奇襲を仕掛け、見事に敗走させました。
1581年の鳥取城をめぐる吉川経家との戦いでは兵糧攻めを、1582年の備中高松城の攻防では水攻めを成功させます。
1582年6月、本能寺で信長が明智光秀に討たれると、毛利氏と相対していた秀吉に講和を進言し、中国大返しを促したのも官兵衛。官兵衛は秀吉に付き、山崎に向かって秀吉と共に明智軍を討伐し、以降は秀吉の配下に付くことになりました。
そして、官兵衛の交渉力が遺憾なく発揮されたのが、1590年の秀吉の小田原攻めです。
天下統一にまい進する秀吉が、必ず倒さなければならない相手。それが小田原城を本拠とする北条氏でした。小田原城は、上杉謙信、武田信玄の両雄も攻め入りながら攻略することができず難攻不落といわれた城。秀吉軍も支城を次々に攻め落とし、大軍で小田原城を包囲して宇喜多秀家、堀秀政などに和睦交渉を行わせますが、北条氏は降伏しません。
膠着状態が続く中で呼ばれたのが、前年に家督を長男の長政に譲り、引退して出家していた官兵衛でした。
ここでの官兵衛の手腕は、まさに手練手管という表現がふさわしいものでした。
官兵衛はまず、妻子を使って城内の北条氏房と連絡を取ります。そして、酒とさかなを城内に贈り届けました。和睦の意思表示です。これに対し、北条氏からは鉄砲の鉛と火薬が送られてきました。
鉛と火薬は、明らかに抗戦するとの意味にも取れます。しかし官兵衛はこれを答礼とみなし、答礼で応えようと、刀を差さず肩衣とはかまの正装で小田原城に向かいます。
北条氏政、氏直の親子と面会した官兵衛は、北条の戦いを褒め、相手の警戒心を解きます。そして、籠城戦が長くは保たないことを説きます。官兵衛は、過去に城の水攻めも兵糧攻めの経験もある人物。援軍がない中で籠城を続けるとどのようなことになるか、熟知しています。
官兵衛の話を聞いた氏政と氏直は降伏を決意し、小田原城は無血開城されました。もし北条氏が抗戦を続けていたら多くの犠牲者は免れなかったでしょうし、豊臣側の負担も大きくなっていました。官兵衛の熟練の交渉が、北条側も豊臣側も救ったことになります。
その後、1600年の関ヶ原の戦いでも西軍の立花宗茂を説得して柳川城を開城させるなど、官兵衛は交渉人として力を発揮し続けました。
良い交渉は、状況を好転させます。家督を継いだ後、官兵衛が信長との謁見にもし失敗していたら、黒田氏、小寺氏の運命は違うものになっていたでしょう。また、小田原城で北条親子を説得できなかったら、陰惨な運命が待っていたことでしょう。
知略、そして交渉に優れた官兵衛は信長、秀吉、徳川家康の三英傑に高く評価されていました。
ビジネスでも発注先との価格交渉、受注元との条件交渉、パートナーシップの締結交渉、はたまたM&Aの交渉など、さまざまなシーンで臨機応変な交渉が必要になります。
交渉の面に立つ人材はシーンによって異なると思いますが、官兵衛のように状況を変えられる機会に立っているのは交渉の担当者、その人です。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント