
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
勇猛といわれる戦国武将は多くいますが、戦場で多くの敵兵を倒し、自ら無双するのはゲームの中だけの話。実際に戦ったのは、配下の家臣であり、さらにその下の兵隊です。
多くの家臣に忠誠を誓わせ、戦(いくさ)のときには命を賭けて戦ってもらえるか。そこで重要になってくるのが人の心をつかむ手法、人心掌握術です。本連載、第38回では織田信長と豊臣秀吉のイベントによって民衆や配下の心をつかんだテクニックを紹介しましたが、今回は、同じく2人を中心に家臣掌握術を紹介しましょう。
まずは“人たらし”の名人として知られる秀吉から。秀吉は、人使いのうまさを表すエピソードには事欠きません。木下藤吉郎と呼ばれて、配下などほとんど持てなかった時代から、その能力を発揮しています。
尾張国(現・愛知県)の清須城の土塀が崩れ、織田信長が修復を命じました。しかし、工事は一向にはかどりません。そこで工事責任者である普請奉行に新たに就任したのが藤吉郎でした。藤吉郎は、頭領や労働者を前に「怠けたら容赦しない」とまずムチを振るいます。
しかし、その後アメを用意するのを忘れません。「明日は酒を飲んで休んでくれ。明後日からは仕事を始めてもらうが、仕事が速かった組には賞与を与える」。そして、台に乗せて300貫文ものお金を運ばせました。これで、体を酷使する労働者たちのやる気がかきたてられたといいます。次の日酒を飲んで英気を養うと、翌日仕事に取り掛かり、その日のうちに工事を終わらせてしまいました。
秀吉は筆まめな人物としても知られ、8000通以上の書状が現存するといわれています。この書状も人心掌握に一役買っています。本能寺の変で斃(たお)れた信長の後継問題で、秀吉と柴田勝家が対立。1583年、賤ヶ岳の戦いへと発展していきます。この戦いは秀吉の勝利に終わり、信長亡き後の覇権を秀吉が握ることになりますが、一番槍(やり)として武勲を立てたのが福島政則、加藤清正ら9人の臣下でした。
秀吉は9人それぞれに感状(かんじょう/戦で立てた手柄を褒め、主君や上官が与える書きつけのこと)を送り、その働きを大いにたたえるとともに、福島政則には5千石、加藤清正ら8人には3千石の恩賞を与える旨を記しました。武将が恩賞を与えるときに感状を出すのは珍しいことではありませんが、「一番槍としての働き比類なし」と評価点を明確にし、十分な恩賞を与えたことで心をつかみます。
秀吉にはこんなエピソードもあります。羽柴秀吉軍が織田信雄・徳川家康軍と相対した1584年の小牧・長久手の戦い。この戦いは最終的には休戦に終わりましたが、戦いの途中の蟹江城攻防戦で「九鬼水軍」で知られる九鬼嘉隆が徳川軍に大敗を喫して逃げ帰るという場面がありました。
後日、嘉隆は秀吉に呼ばれ、京都の聚楽第で碁盤を囲みました。嘉隆は蟹江城攻防戦で敗走したことが気になっています。そのことを嘉隆がわびると、秀吉は非難するようなことはせず、「撤退するのも難しい戦場から、無事帰った。それこそが何よりの手柄である」と逆に嘉隆をたたえました。
ミスをした部下は、そのことを気にしているものです。そこを叱られることなく、無事だったことを評価された。嘉隆は感激し、秀吉に忠誠を尽くすことになります。
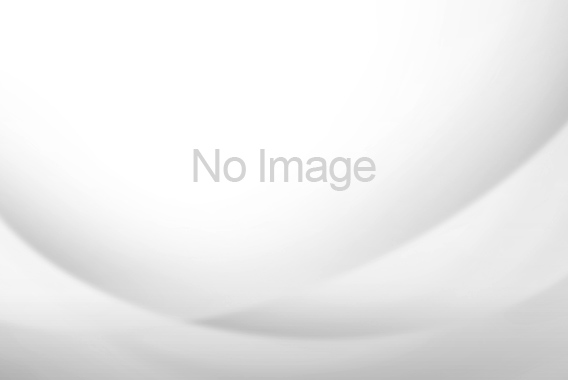 “人たらし”の秀吉とは対照的に恐怖政治のイメージがある信長。しかし、信長も強面(こわもて)だけで家臣を操っていたわけではありません。モチベーションを上げる方法も使っていました。
“人たらし”の秀吉とは対照的に恐怖政治のイメージがある信長。しかし、信長も強面(こわもて)だけで家臣を操っていたわけではありません。モチベーションを上げる方法も使っていました。
信長は部下のモチベーションを上げるために茶道を活用したのです。当時、武将の間で茶道が流行になり始めました。そこで、信長は茶会を開くことを高い身分の家臣だけに認めることにしたのです。つまり茶会の開催を織田家におけるステータスシンボルにしたわけです。秀吉も身分が上がり、初めて茶会の主催が認められたときには大いに喜んだといわれています。
また、信長は「名器狩り」と呼ばれるほど大規模に名物茶器を買い集め、名品が信長の手元に集められました。一方、茶会の主催が認められた配下も高価な茶器、珍しい茶器を競ってコレクションしようとしていました。そんな彼らに対して、武功の証しとして自ら所有する茶器を与えたのです。
例えば、柴田勝家は北陸攻略での武功が認められ、信長から「天猫姥口釜(てんびょううばくちがま)」という茶釜を贈られました。その他、秀吉、大友宗麟なども信長から茶器を下賜(かし)されています。
織田四天王の一人・滝川一益は、1582年の甲州征伐で活躍を見せ、上野国(こうずけのくに/現・群馬県)と関東管領の地位を与えられました。ですが、一益が欲しかったのは信長が持つ「珠光小茄子」という茶入。上野国と関東管領の地位を手に入れても肩を落としたという話が残っています。一国より茶器が望まれた。そんな時代に、信長は自らのコレクションを放出することでモチベーションを上げていったのです。
本連載では第1回で、信長が娘婿に迎え、秀吉が厚遇した名将、蒲生氏郷の家臣掌握術を紹介しました。その氏郷は次のような言葉を残しています。
「まずは情を深くし、それから知行(領地や報酬)を与えよ。しかし情ばかりで知行を与えなければ、同じことである。知行と情は車の両輪、鳥の両翼と心得よ」。まず情、感謝の気持ちが重要である。しかし、それだけでもいけない。情と知行、両方が必要なのだということです。
ビジネスにおいてもリーダーは配下の心をつかみ、モチベーションを上げることが大切です。秀吉の筆まめ、信長のコレクション放出など、配下の感情を動かすテクニックに学ぶところは少なくないでしょう。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント