
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
戦国武将は、一国一城のあるじ。現代でいえば、会社の経営者に比べることができる存在です。彼らが経営した「会社」は一体何をしたのでしょうか。今回からしばらくは、戦国武将を経営者に例えて戦略を読み解いていきたいと思います。まず取り上げるのは、豊臣秀吉の「秀吉株式会社」です。
秀吉が行った施策の中で、最も大規模なものともいえるのが検地でした。太閤検地と呼ばれ、ご存じのように全国で土地調査を行いました。
もちろん、それまでの戦国大名も検地を行っていました。ただ、家臣や寺社、村などに農耕地の面積、年貢などを調査・報告させる程度のもので、必ずしも農耕地の状況を正確に伝えるものではありませんでした。
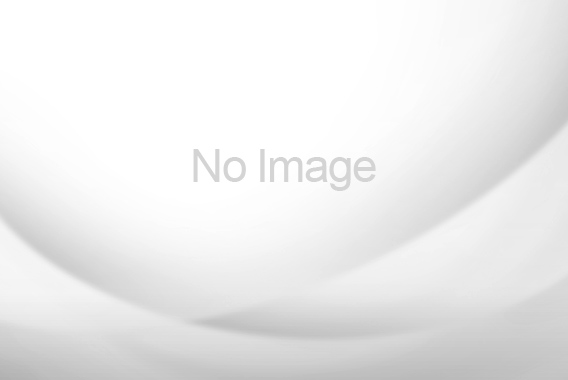 また、従来の検地では検地用の竿で農耕地の広さを測り、升で収穫量を計って年貢の量を決めていましたが、使われていた竿や升はそれぞれの大名で異なっているという問題がありました。モノの長さ、体積、重さを測る単位を度量衡といいますが、戦国時代は、全国バラバラの度量衡によって年貢が決められていたのです。
また、従来の検地では検地用の竿で農耕地の広さを測り、升で収穫量を計って年貢の量を決めていましたが、使われていた竿や升はそれぞれの大名で異なっているという問題がありました。モノの長さ、体積、重さを測る単位を度量衡といいますが、戦国時代は、全国バラバラの度量衡によって年貢が決められていたのです。
そこで秀吉が検地を進める際に行ったのが、度量衡の統一でした。秀吉は、1間を6尺3寸(約191センチ)と定め、長さの基準を統一します。また収穫量を計る際に用いる升を、京都を中心に用いられた京枡に統一しました。これで、広さも量も1つの基準で測ることができるようになりました。
秀吉の太閤検地では、京枡を使って田畑1段当たりの生産力を計りました。そして、1石5斗の生産力がある「上田」、1石3斗の「中田」、1石1斗の「下田」といったように田畑に等級をつけていきました。この田畑1段当たりの生産力が石盛(こくもり)です。
そして、1間6尺3寸で測った田畑の面積を石盛に乗じます。すると、その田畑全体の生産力が計算できることになります。こうして計算された生産力が、石高です。この石高に基づいて、秀吉は年貢の量を決めていきました。同じ度量衡を用い、全国同じ基準で年貢の量を決めるようになったのです。
これは、秀吉社長は支店(各大名)それぞれで異なっていた基準を統一したと見ることができます。組織が大きくなればなるほど、運営において基準の統一は欠かせなくなります。
例えば、人事評価。全国的な企業でA支店とB支店で評価基準が異なっていると、適切な評価とそれに伴う異動ができません。昇進や全社員のモチベーションに影響し、事業発展を阻害しかねません。評価者によって評価基準がバラつくのは非常に深刻な問題です。各大名がバラバラの竿や升で検地していたのと同じような状態です。
織田信長株式会社による楽市楽座政策などにより、貨幣経済が発展し始めたとはいえ、戦国時代の経済で最も大切だったのは、コメの収穫量です。その基準が曖昧なのは大きな問題です。全国的な大企業になった豊臣株式会社はその課題に取り組んだわけです。
秀吉は1582年、山崎の戦いで明智光秀を討った後に検地を始め、1598年に没するまで続けました。天下人としての生涯をかけて検地を行ったといってもいいでしょう。それは、経済で最も大切なコメの基準を統一し、徹底することが全国のナンバーワン企業の経営者=天下の覇者としての使命だと分かっていたのかもしれません。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント