
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
戦国時代の武将の命運は、さまざまな要因によって左右されました。中でも大きかったのは、どの武将と同盟を組むか、またどの武将の臣下に入るかという判断です。
そんな合従連衡のポイントの1つに「専門性」があります。中でも「水軍」の力をうまく活用できるかどうかは、戦国武将の運命に大きな影響を与えました。いくら陸の上で強くても、海や湖といった水の上では勝手が違います。その専門職である「水軍」の力を活用することには大きな意味がありました。
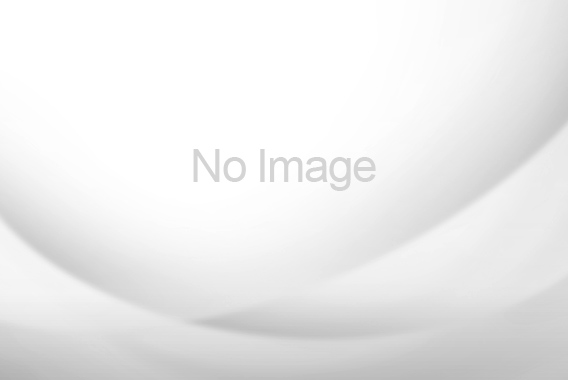 水軍の力を活用したことがポイントとなった戦いとして知られるのが、1555年の厳島の戦いです。安芸国(現・広島県)の毛利元就は、知略を駆使しながら次第に勢力を拡大していきました。周防国・長門国(現:山口県)を支配する大内家の実権を握っていた陶晴賢と相対することになります。
水軍の力を活用したことがポイントとなった戦いとして知られるのが、1555年の厳島の戦いです。安芸国(現・広島県)の毛利元就は、知略を駆使しながら次第に勢力を拡大していきました。周防国・長門国(現:山口県)を支配する大内家の実権を握っていた陶晴賢と相対することになります。
当時、元就軍は約4000人。対する晴賢軍は約2万人。元就は、圧倒的に不利な状況にありました。そこでまず、元就は「厳島に攻め込まれたら勝ち目がない」という偽りの情報を流して晴賢軍を厳島におびき寄せることにします。そして、村上水軍と交渉を始めます。
村上水軍は、根拠とする島によって能島村上氏、因島村上氏、来島村上氏の3氏に分かれていました。このうち、因島村上氏はすでに元就の側に付いています。しかし、他の2氏は旗色を鮮明にしていません。この2氏の決断が戦況を変え得ることを、元就は見通していました。
元就の三男・小早川隆景は、家臣の乃美宗勝(のみ むねかつ)を来島村上氏の頭領・村上通康の元に遣わせます。通康を味方に付けないと勝利がおぼつかないのは明らかでした。宗勝は必死の思いで「1日でよいから力を貸してほしい」と頭を下げます。
一方の陶晴賢も村上一族に声をかけていました。ただ、晴賢は書簡による依頼のみです。村上氏としても、どちらに味方するかで自らの命運が分かれます。圧倒的に多勢を誇る晴賢軍に付くか、元就軍か……。
晴賢軍は500艘(そう)もの大船団で厳島に上陸し、2万人の大軍で宮尾城を取り囲みました。ようやく村上水軍の船団が姿を現したとき、船団が向かった先は厳島ではなく、元就軍が本陣を構える対岸の火立山でした。元就軍は、狭い厳島に晴賢軍を封じ込める戦略と村上水軍を味方に付けたことにより、戦いに勝利。さらに勢力を広げていくことになります。
時は下って1576年。織田信長は臣下の佐久間信盛に命じ、敵対する大坂の石山本願寺を包囲しました。海上封鎖による兵糧攻めです。窮地に陥った石山本願寺は、元就の孫である毛利輝元に援助を求めました。輝元は村上水軍を中心とする強力な船団を大坂に向かわせます。
迎え撃ったのが、信長の臣下になっていた九鬼水軍です。信長は志摩国(現・三重県)の九鬼水軍を味方に付け、すでに幾度も戦いを行っていたのです。最初に毛利の水軍と織田の水軍が戦いを交えた第一次木津川口の戦いは毛利側の勝利に終わりましたが、1578年の第二次木津川口の戦いでは大型の鉄甲船を建造して臨んだ織田の水軍が圧勝しました。
これによって、石山本願寺の補給は困難になり、降伏の大きな要因になりました。そして、信長は大坂湾の制海権も手中に収めました。制海権は信長が本能寺の変で殺された後に豊臣秀吉が引き継ぎ、大坂城の築城につながり、商都・大坂の隆盛へとつながることになります。
毛利と織田の水軍について見てきましたが、山に囲まれた甲斐国(現・山梨県)の大名だった武田信玄も、勢力拡大の過程で伊勢の小浜景隆や伊豆の間宮武兵衛などを味方に付け、自らの水軍を組織していました。
このように、強い戦国武将が水軍を味方に引き込み活用したことは、現在のビジネスでいえば、本業ではなかったり、得意ではなかったりする業務分野に関して、外部の専門家の力を借りることに通じるのではなないでしょうか。
有力な戦国武将は誰もが陸上での戦いに通じていました。それでも、水の上は「餅は餅屋」ということで、水軍のスペシャリストを起用したわけです。高度な専門性を要する領域に関しては、自社のリソースだけでは対応することは非常に難しいでしょう。そうした領域の業務が必要になったとき、どのような手段で、その領域をカバーするべきなのか。有力戦国武将と水軍の関係を見ていると、スペシャリスト活用の大切さが感じられます。
【T】
戦国武将に学ぶ経営のヒント